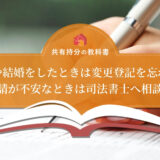共有持分を売却したいと考える方から、「買取業者に売却したいけど、トラブルが起きないか不安だ」というご相談をよくいただきます。
たしかに、共有持分の売却は通常の不動産取引と比べて権利関係が複雑なため、トラブルに発展しやすいのが現実です。
これまでの弊社へのご相談の中で、実際に見られたトラブル事例を整理すると、以下のようになります。
| 買取業者と売主の間で起こり得るトラブル |
・相場より著しく安い価格で買い叩かれる ・「他では売れない」などと不安を煽り、強引に契約を迫られる ・契約書に売主に不利な条項を盛り込まれる ・契約後に測量費や解体費など想定外の費用を請求される |
|---|---|
| 買取業者と他の共有者の間で起こり得るトラブル |
・電話や訪問による強引な営業が繰り返される ・賃料・使用料の支払いを求められる ・明け渡しや立ち退きを請求される ・共有物分割請求訴訟を起こされる |
| 売主と他の共有者の間で起こり得るトラブル | ・「なぜ相談もなく第三者に売却したのか」と不満を持たれ、関係が悪化する原因になる |
必ずしも全てのケースでトラブルが発生するわけではありませんが、共有持分という特殊な性質上、注意を払っても完全にリスクを避けるのは難しいのが実情です。
そこで、弊社が推奨しているのは次の2点です。
- 売却前に他の共有者へ一言伝えておく
- 共有持分に精通し、実績のある買取業者に依頼する
買取業者を見極める際には、以下のポイントを必ず確認してください。
- 共有持分の買取実績が豊富か
- 相続物件の取り扱いに強いか
- 宅地建物取引業の免許を持っているか
- 弁護士事務所と連携しているか
- 口コミや評判が良いか
- 売却代金を現金で受け渡してくれるか
- 移転登記と代金の受け渡しを同時に行えるか
これらはすべて、弊社へのご相談や取引を通じて見てきた「信頼できる業者の共通点」です。
共有持分の売却で不安を抱えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
買取業者と売主の間で起こり得るトラブル
共有持分を買取業者に売却する場合、売主と業者の間で深刻なトラブルに発展することは多くありません。売却後は業者が新たな共有者となり、他の共有者との交渉も業者が担うため、売主が関与する場面は基本的に少ないからです。
ただし、一部の業者のなかには、売主にとって不利な契約条件を提示したり、後々の金銭トラブルにつながるような対応をするケースもみられます。
共有持分は市場性が低く相場も掴みにくいため、経験の浅い売主が十分に確認しないまま契約を進めると、以下のようなトラブルにつながりやすいです。
- 相場より著しく安い価格で買い叩かれる
- 「他では売れない」などと不安を煽り、強引に契約を迫られる
- 契約書に売主に不利な条項を盛り込まれる
- 契約後に測量費や解体費など想定外の費用を請求される
弊社クランピーリアルエステートにも「他社で契約した後に追加費用を請求され、結局思ったより手取りが少なくなった」というご相談が寄せられることがあります。
このようなリスクを避けるには、複数の業者から査定を取り、相場を把握しておくことが重要です。
契約書は必ず内容を確認し、不明点は質問する姿勢を持ちましょう。強引な営業に対しては即答せず、落ち着いて判断することが大切です。
買取業者と他の共有者の間で起こり得るトラブル
共有持分を買取業者に売却すると、売主は共有状態から抜けられますが、残された共有者には新たなトラブルが生じやすくなります。
業者は最終的に不動産を単独で所有し自由に活用することを目的としているため、残りの共有者に対して積極的に交渉を行うのが一般的です。とくに悪質な業者にあたると、強引な営業や賃料請求など予期しない金銭的負担、立ち退きの要求や訴訟にまで発展するケースがあります。
また、持分売却を知らされていなかった共有者が突然交渉を受けると「自分の持分まで手放さなければならないのか」と不安に感じるのも自然です。とくに共有不動産に居住している場合は、生活の安定が脅かされると感じる可能性もあるでしょう。
代表的なトラブルは以下のとおりです。
- 電話や訪問による強引な営業が繰り返される
- 賃料・使用料の支払いを求められる
- 明け渡しや立ち退きを請求される
- 共有物分割請求訴訟を起こされる
以下では、それぞれのトラブル例について詳しく解説します。
電話・訪問など強引な営業を繰り返される
共有持分を購入した業者は、最終的に不動産を単独で所有し、自由に利用・処分できる状態を目指すのが一般的です。そのため残りの共有者に対して「持分を売却してほしい」と繰り返し勧誘してくる場合があります。
とくに悪質な業者の場合は、次のような強引な営業を行うケースもあります。
- 早朝や深夜に自宅へ訪問してくる
- 何度もしつこく電話をかけてくる
- 嫌がらせのように手紙を投函してくる
弊社にも「知らない業者から毎日のように電話があり、不安で生活に支障が出ている」というご相談が寄せられたことがあります。
強引な営業行為が続くと、共有者は精神的に大きな負担を抱えるおそれがあり、生活の平穏が脅かされることにもつながりかねません。
しつこい勧誘を避けるには、内容証明郵便で「交渉を拒否する意思」を明確に伝えるのが効果的です。証拠を残しておけば、後に法的なトラブルに発展した場合にも重要な証拠として利用できます。
また、売却時には信頼できる業者を選んだうえで、可能であれば事前に他の共有者へ売却することを伝えておくのもトラブル防止につながります。
賃料・使用料の支払いを求められる
共有持分の買取業者は、不動産全体の活用を目的に買い取るのが基本ですが、なかには賃料収入を得ることを視野に入れて取得する業者も存在します。
民法第249条に基づき、共有者が物件を独占的に利用している場合には、他の共有者から「使用料相当額」を請求される可能性があります。
(共有物の使用)
民法第249条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
引用元:e-Gov「民法」
共有持分を取得した買取業者にも同じ権利が認められるため、これまで親族間では問題にならなかった賃料が突然請求されるケースがあるのです。
弊社にも「突然、業者から使用料を請求されて驚いた」というご相談が寄せられたことがあります。想定していなかった請求に困惑する方は少なくありません。
代表的なケースとしては、以下のようなものがあります。
- 共有者の一人が物件に居住している場合、他の共有者から家賃相場に応じた使用料を求められる
- 物件を賃貸に出している場合、持分割合に応じた賃料を分配するよう請求される
たとえば、家賃10万円で賃貸に出している不動産の持分2分の1を業者が取得した場合、居住者や他の共有者に対して月額5万円前後を賃料として請求されるケースがあります。入居者からすれば「突然知らない人に家賃を請求された」と感じて驚くのは自然ですが、業者にとっては当然の権利といえるのです。
ただし、実際に請求される金額は必ずしも実際の利用状況を反映しているとは限りません。購入者側は賃料の詳細を把握できないため、周辺の賃貸相場をもとに請求額を算出してくるケースが大半です。そのため、請求額をめぐってトラブルに発展するケースも少なくありません。
もっとも、共有者間であらかじめ別段の合意がある場合には、請求が制限されるケースもあります。とはいえ、使用料や賃料の請求自体は法律上認められる場合が多いため、話し合いで解決できなければ最終的に裁判に発展するおそれがあります。
トラブルを避けるには、売却前に「どのような場合に請求されるか」「金額の目安はどの程度か」を把握し、必要に応じて専門家に相談しておくことが大切です。事前に準備しておけば、不要な請求や裁判リスクを避けやすくなります。
明け渡しや立ち退きを請求される
共有持分を取得した業者は、不動産を早期に現金化したり、単独所有にして自由に活用したりすることを目的としています。その過程で、共有不動産に居住している他の共有者に対し、「物件を明け渡してほしい」「立ち退いてほしい」と直接要求してくるケースがあります。
もっとも、業者には強制的に退去させる権限はなく、実際に効力を持つのは裁判所が判断した場合に限られます。したがって、単なる要求に応じる義務はありません。
しかし、弊社にも「業者から繰り返し立ち退きを迫られ、精神的に大きなストレスを感じている」というご相談が寄せられています。
このような圧力を受けた場合には、一人で抱え込まずに弁護士など専門家に相談し、冷静に対応することが重要です。
共有物分割請求訴訟を起こされる
共有持分を取得した業者の最終的な目的は、不動産を単独所有して自由に処分できる状態にすることです。話し合いで合意できない場合、民法第258条に基づいて、業者が「共有物分割請求訴訟」を提起してくるケースがあります。
(共有物の分割)
民法第258条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
引用元:e-Gov「民法」
「共有物分割請求訴訟」とは、共有状態を解消するために裁判所へ申し立てる手続きです。この権利はすべての共有者に認められるため、買取業者も取得した時点から請求権を持ちます。
訴訟が起こされると、裁判所が中立の立場で判断を下し、一般的には「換価分割」という方法が選ばれる傾向にあります。換価分割とは、不動産を競売にかけて現金化し、その代金を持分割合に応じて分配する方法です。
所有を続けたい共有者がいても競売による換価分割が命じられる場合があり、意思に反して不動産を手放さざるを得なくなるケースもあります。
弊社にも「業者から訴訟を起こされ、どう対応すればよいかわからない」という相談が実際にありました。
競売は市場価格より安く売却されることが多く、共有者にとって大きな損失になる可能性が高いです。訴訟を嫌って争うことになれば、多くの場合は弁護士に依頼する必要があり、数十万円から100万円程度の費用が発生します。
そのため、訴訟に至る前にできる限り交渉や和解の道を探り、必要に応じて弁護士など専門家に相談しておくことが重要です。
売主と他の共有者の間で起こり得るトラブル
共有持分の売却は、法律上は各共有者が自由に行える行為です。
(所有権の内容)
民法第206条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をすることができる。
引用元:e-Gov「民法」
買取業者に売却した後、売主は共有状態から解放されるメリットがあります。一方で、残された共有者は新たに業者と交渉しなければならず、負担や不安が増えるデメリットもあるのです。
とくに「共有不動産を占有している」「不動産を売却することに反対している」といった共有者にとっては、業者からの交渉に応じたくないと考えるのは自然です。
また、相続によって共有となった親族間では「なぜ相談もなく第三者に売却したのか」と不満を持たれ、関係が悪化する原因となるケースもあります。
さらに業者が新たに共有者になると、残る共有者が賃料請求や立ち退き要求、訴訟に巻き込まれるリスクもあり、その矛先が売主に向けられる場合もあるでしょう。
弊社クランピーリアルエステートにも「売却後に親族からしつこく連絡があり困っている」といったご相談がありました。
法律的には自由に売却できるとはいえ、事前に共有者へ事情を説明し、理解を得ておくことがトラブル防止につながります。
共有持分の売却トラブルを避けるための買取業者の選び方
共有持分の売却は、権利関係が複雑なため、通常の不動産取引よりもトラブルに発展する可能性が高い分野です。安心して取引を進めるためには、信頼できる買取業者を見極めることが欠かせません。
業者の実績や免許の有無、法的なサポート体制などを事前に確認しておけば、売却後のリスクを減らせます。
とくに以下のような点をチェックしておくとよいでしょう。
- 共有持分の買取実績が豊富か
- 相続物件の取り扱いに強いか
- 宅地建物取引業の免許を持っているか
- 弁護士事務所と連携しているか
- 口コミや評判が良いか
- 売却代金を現金で受け渡してくれるか
- 移転登記と代金の受け渡しを同時に行えるか
以下では、これらのチェックポイントを詳しく解説します。
共有持分の買取実績が豊富か
共有持分の売却では、まず「買取実績がどれだけあるか」を確認することがポイントです。通常の不動産取引に比べて権利関係が複雑なため、経験の浅い業者では査定額が不明確になったり、契約後に共有者との交渉を進められなかったりするリスクがあります。
一方で、共有持分の買取実績が豊富な業者であれば、過去の事例をもとに査定額の根拠や交渉の流れを具体的に説明が可能です。実績の多さは、そのままトラブル回避力や専門知識の裏付けになるといえるでしょう。
確認方法としては、公式サイトに買取件数や事例が掲載されているかをチェックするのが基本です。「どのような不動産を扱ったか」「どのように交渉を解決したか」といった情報があれば、その業者が共有持分に特化したノウハウを持つかどうか判断できます。また、会社概要や個人情報保護方針を明記しているかも信頼性を測る重要なポイントです。
反対に、公開実績が少ない業者は対応に不慣れである可能性が高く、後になって追加費用を請求されたり、共有者との交渉がこじれて長期化したりするおそれがあります。こうしたリスクを避けるためにも、十分な実績を持つ業者を選ぶことが大切です。
相続物件の買取にも強いか
共有持分は夫婦や家族での共同購入から生じる場合もありますが、発生原因として最も多いのは「相続」です。
相続では相続人同士の意見が対立したり、相続登記がなかなか進まなかったりするケースが多く、売却や管理が滞るリスクがあります。そのため、相続案件の実績が豊富な業者を選ぶことが、円滑な売却のポイントとなるでしょう。
特に、2024年4月から相続登記は義務化されました。登記を怠った場合は10万円以下の過料が科されるほか、登記未了のままでは売却手続き自体が進められない可能性もあります。
登記が済んでいない状態からでも司法書士と連携して手続きをサポートできる体制があるかどうかは、業者を見極めるうえで重要なポイントです。
さらに、相続不動産の売却では相続税や贈与税の問題が絡むケースも珍しくありません。税理士と提携している業者であれば、税務面まで一括で相談できるため、余計なトラブルを回避しやすいといえるでしょう。
相続によって発生した共有持分を売却する際は、「相続案件の実績が豊富か」「専門士業と連携しているか」を確認しておくことが大切です。
宅地建物取引業の免許を持っている
不動産取引を行うには、宅地建物取引業法に基づく「宅地建物取引業免許」が必要です。
(宅地建物取引業の免許)
宅地建物取引業を営もうとする者は、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなければならない。
引用元:e-Gov「宅地建物取引業法」第3条
無免許業者は宅建業法違反となり、行政処分や刑事罰の対象です。保証金制度などによる保護が受けられず、トラブル発生時に損害回復が難しくなる可能性があります。
免許の有無は、国土交通省や各都道府県が公開している検索システムで確認が可能です。
免許番号を公式サイトや広告に明記しているかどうかは、信頼性を判断するうえでの大切なポイントです。
ただし、免許があるからといって必ずしも安心できるとは限りません。
ただし、免許があるからといって必ずしも安心できるとは限りません。ごく一部の業者のなかには「囲い込み」と呼ばれる行為を行うケースも報告されています。
これは、表向きは「買い取れる」と言いながら具体的な手続きを進めず、他の買主を排除して物件をキープし、結果的に売却が長引いて値下げを迫られる可能性があるというものです。
もちろん、すべての業者に当てはまるわけではなく、信頼できる業者であれば迅速かつ適正に取引を進めてくれます。そのため、免許の有無だけでなく実績や対応姿勢を総合的に確認することが大切です。
弁護士事務所と連携している
共有持分の売却では、他の共有者との交渉がこじれたり、使用料や明け渡しをめぐって法的トラブルに発展したりするケースがあります。そのため、弁護士事務所と連携している業者を選ぶことは、安心して取引を進めるための重要な条件です。
契約書の内容や金銭の取り決めについても、弁護士が監修していれば売主に不利な条項を盛り込まれるリスクを減らせます。また、共有者から訴訟や強い要求を受けた場合に、弁護士と連携して迅速に対応できる体制があるかどうかは大きな判断基準となるでしょう。
ただし、業者が「顧問弁護士と提携」とうたっていても、実際の関与範囲はさまざまです。単に業者の法律相談に対応するだけで、契約書のチェックや交渉に同席しないケースもあり得ます。したがって、契約や交渉にどの程度弁護士が関与するのか、売却後のフォロー体制まで整っているのかを事前に確認しておくとよいでしょう。
また、確認しておきたいのが費用面です。弁護士費用を買取業者側が負担してくれるのか、それとも売主が別途支払う必要があるのかは、取引の安心度に関わります。
実績のある業者では顧問契約の一環として追加費用なしで対応してくれるケースもありますが、そうでない場合は売主負担になることもあります。
弁護士へ個別に依頼する場合は数万円〜数十万円程度かかるのが一般的なので、契約前に「弁護士費用は誰の負担か」を明確にしておくことが大切です。
また、その弁護士が不動産や相続などの分野に精通しているかどうかも重要なポイントです。専門性の高い弁護士と提携している業者であれば、万一のトラブルでも安心して任せられるでしょう。
口コミや評判が良いか
共有持分の売却は、一般的な不動産売買よりもトラブルが起こりやすいため、実際に取引をした人の声を確認して業者の信頼性を見極めることが重要です。
公式サイトの情報だけで判断せず、第三者が運営するレビューサイトやSNSなど、複数の情報源を照らし合わせるようにしましょう。
特に注意が必要なのは、以下のようなネガティブな口コミです。
- 査定額が相場より極端に低かった
- 強引な営業を受けた
- 契約後に追加費用を請求された
こうした声が目立つ業者は避けるべきでしょう。
一方で、以下のようなポジティブな評価が多い業者は、安心感があります。
- 担当者の説明が分かりやすかった
- 想定より高値で売却できた
- 契約から決済までスムーズだった
ただし、インターネット上の口コミには削除や印象操作が行われている場合もあるため、1つのサイトや投稿だけをうのみにするのは避けましょう。必ず複数の媒体をチェックし、全体的な傾向をもとに総合的に判断してください。
売却代金を現金で受け渡してくれるか
売却代金の受け取り方法は、取引の安全性に直結する重要なポイントです。通常は銀行振込が主流ですが「急ぎで資金が必要」「即日現金化したい」といった売主にとっては、現金払いに対応できる業者が心強いでしょう。
注意が必要なのは、小切手など現金以外の方法を提示されるケースです。換金できない小切手を渡されたり、不渡りで現金化できなかったりするリスクがあり、最悪の場合は代金を受け取れない可能性があります。
そのため、共有持分の売却では現金払いに対応しているかを事前に確認しておくことが重要です。
もっとも、多額の現金をその場で受け渡すこと自体にも、防犯上のリスクがあります。現金払いを希望する場合は「対応できるかどうか」だけでなく、「どのように受け渡すのか」まで確認しておきましょう。
移転登記と代金の受け渡しを同時におこなえるか
共有持分の売却で注意したいのが、移転登記と売却代金の支払いを同じタイミングで行う「同時決済」に対応しているかという点です。
移転登記を先に済ませてしまうと、代金が支払われないまま不動産の権利だけ失ってしまうリスクがあります。悪質な業者の典型的な手口でもあるため、契約前に必ず確認しておきましょう。
同時決済を行う業者であれば、司法書士や金融機関の立会いのもとで登記移転と代金授受を同日に処理してくれるため安心です。
一方で「登記と代金の受け渡しは別日になる」といった説明をされた場合には要注意です。登記を先行させる条件を受け入れると、代金を支払わずに物件だけ奪われるリスクが高まるため、そのような業者とは契約を進めず、別の業者を検討するのが賢明です。
安全に売却を終えるためには、単に「同時決済に対応しているか」だけでなく「どのような仕組みで実行されるのか」まで事前に確認することが大切です。
共有持分を買取業者に売却するメリット
不動産の共有状態は長引くほどトラブルに発展しやすく、解消の手段として「買取業者への売却」を選ぶ方も少なくありません。仲介のように買主探しに時間をかける必要がなく、スピーディーかつ確実に現金化できるのが大きな特徴です。
共有持分を買取業者に売却するメリットは以下のとおりです。
- スピーディーに現金化が可能
- 仲介手数料がかからない
- 原則として契約不適合責任が免責される
- 他の共有者に知られずに売却が可能
これらの特徴は仲介にはない強みであり、「なるべく早く資金化したい」「共有状態からスムーズに抜け出したい」といったニーズにも対応できます。
ここからは、それぞれのメリットについて解説します。
スピーディーに現金化が可能
通常の不動産仲介では、買主探しから契約・決済に至るまで数ヵ月を要するのが一般的です。しかも、共有持分は需要が限られるため、そもそも買い手が見つからず長期化するケースも少なくありません。
その点、買取業者は自社での活用方法や転売先をあらかじめ確保しているため、買主探しに時間をかける必要がなく、査定から契約・決済までを短期間で完了できます。
業者によっては最短で数日〜1週間程度で現金化できる場合もあり、相続税の納付期限が迫っているケースや急な資金需要にも柔軟に対応できます。
時間をかけずに資金化できるという点は、「共有状態から一刻も早く抜け出したい」というニーズに応える有効な手段といえるでしょう。
仲介手数料がかからない
通常の不動産売却を仲介会社に依頼した場合、売買が成立すると「仲介手数料」が発生します。
宅地建物取引業法では上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合は速算法として「売却価格×3%+6万円+消費税」で計算します。例えば売却価格が1,000万円なら、最大で約39.6万円の仲介手数料を支払う必要があります。
一方で、買取業者に直接売却すれば仲介会社を介さないため、この仲介手数料は一切不要です。
もちろん、買取は仲介に比べて売却価格がやや低くなる傾向はありますが、手数料が差し引かれない分、実際に手元に残る金額は想定より多くなるケースもあります。
売却にかかるコストを抑えたい人にとって、直接買取は効率的で確実な方法といえるでしょう。
原則として契約不適合責任が免責される
民法562条では、売却した不動産が契約内容に適合しない場合、売主は「契約不適合責任」を負うと定められています。
(契約不適合責任)
売買の目的物が種類・品質または数量に関して契約の内容に適合しないときは、買主はその不適合を理由として契約の解除や損害賠償を請求できる。
引用元:e-Gov「民法」第562条
契約不適合責任とは、売買の対象物に欠陥や権利関係の不備があり、契約の内容と異なる状態で引き渡された場合に売主が負う責任です。該当すれば、買主から損害賠償や契約解除を求められるリスクがあります。
特に共有不動産は、建物に欠陥がなくても「他の共有者の同意がなければ建て替えや処分ができない」といった制約があり、契約不適合とされやすい性質を持ちます。
しかし、買取業者との取引では「契約不適合責任を免責する」と定めるのが一般的であり、売主が売却後に責任を問われることは通常ありません。免責されていれば、売却後に修繕費や補償を請求される心配もなく、安心して手続きを進められます。
売却後の責任を負わずに済むことは仲介にはない特徴であり、共有状態を早期に解消したい人にとって有効な選択肢といえるでしょう。
もっとも、免責条項が契約書に明記されているかは必ず確認しておくことが大切です。書面で明文化されていれば、後々のトラブルをより確実に防止できます。
他の共有者に知られずに売却が可能
民法206条では、共有者は自分の持分について自由に処分できると規定されています。
(共有者の権利)
各共有者は、その持分を自由に処分することができる。
引用元:e-Gov「民法」第206条
つまり、共有持分の売却は他の共有者の同意を得る必要がなく、自分の判断だけで進められるのです。
仲介による売却では、広告や販売活動を行うために共有者へ知られる可能性があります。一方、買取業者へ直接売却する場合は、広告を出さずに取引が完結するため、他の共有者に知られずに共有状態を解消できる点はメリットといえるでしょう。
もっとも、売却後に他の共有者から「なぜ相談もなく売ったのか」と不満を持たれることもあります。特に親族間での共有の場合は、関係悪化につながるリスクを理解しておくことが大切です。
そのうえで、他の共有者に知られずに手続きを進めたい、トラブルを避けて早期に持分を現金化したいといったニーズには、買取業者への売却が有効な選択肢となるでしょう。
買取業者を利用せずに共有状態を解消する方法
共有不動産は民法上のルールに基づいて管理・処分されており、共有者同士の合意や裁判所の手続きによって共有状態を解消することが可能です。
買取業者に売却するのは有効な方法ですが、それ以外にもさまざまな選択肢があります。共有者間で協力する方法や、司法手続きを通じて強制的に解消する方法など、状況に応じた解決策を検討することが重要です。
代表的な方法は以下のとおりです。
- 共有者全員で合意して不動産全体を売却する
- 共有者間で持分を売買する
- 他の共有者に持分を贈与する
- 土地を分筆して単独所有にする
- 共有物分割請求訴訟を起こす
- 自分の共有持分を放棄する
ここからは、それぞれの方法について特徴や注意点を解説します。
共有者全員で合意して不動産全体を売却する
共有状態を最も円満に解消できる方法が、共有者全員の合意に基づいて不動産全体を売却することです。物件を一括で売却すれば市場価値に近い価格で取引できる可能性が高く、売却代金は各共有者の持分割合に応じて公平に分配されます。共有持分のみを売却する場合と比べて、買主にとっての利便性が高いため、早期売却にもつながりやすいのが特徴です。
もっとも、不動産全体の売却は民法上「共有物の変更行為」に該当し、民法251条により共有者全員の合意がなければ成立しません。単独で勝手に売却すると違法となり、訴訟など深刻なトラブルに発展するおそれがあります。
また、相続によって多数の共有者が存在するケースでは、合意に時間や労力がかかりがちです。遠方に住む共有者との連絡調整や、意見の対立によって売却そのものが長期化するリスクがあるため、事前に協議体制を整えておくことが重要です。
さらに、売却益の分配をめぐって争いが生じないよう、事前に「代金は持分割合に応じて分配する」といったルールを取り決めておくと安心でしょう。
共有者間で持分を売買する
共有状態を解消する比較的シンプルな方法が、共有者同士で持分を売買する手段です。例えば兄弟で共有している土地で、一方が他方の持分を買い取れば単独所有が実現します。外部に持分が流出しないため安心感がありますが、資金負担の偏りや価格設定を巡ってトラブルになる可能性も否定できません。
また、民法252条では「共有物の管理に関する事項は持分価格の過半数で決する」と定められているため、過半数以上の持分を取得すれば利用や管理に関する決定権を得られます。
共有者間で持分を売買する方法は主に次の2つです。
他の共有者に自分の持分を買い取ってもらう
他の共有者に自分の持分を売却すれば、現金を得つつ共有状態を解消できます。ただし、相手に十分な資金がなければ成立しないため、事前に購入意思と支払い能力を確認することが重要です。
契約条件を明確にし、必要に応じて不動産鑑定士や不動産会社などに査定を依頼しておくと安心でしょう。
自分が他の共有者の持分を買い取る
他の共有者の持分をすべて買い取れば、単独所有となり不動産を自由に活用できるようになります。ただし、多額の資金を必要とし、すべての共有者が売却に応じることが前提です。
1人でも反対する共有者がいれば実現できないため、売却価格や条件を巡って事前に十分な話し合いを行うことが不可欠です。
他の共有者に持分を贈与する
資金のやり取りを避けたい場合には、他の共有者に持分を贈与する方法もあります。親から子、兄弟間といった親族間で選択されるケースが多く、共有状態を円滑に解消できる方法です。
ただし、無償譲渡となるため、贈与税の課税対象となり、多額の税負担が発生する可能性があります。例えば評価額が高額な場合、税率が20〜55%に達するケースもあり、現金を伴わない贈与では納税資金を確保できずトラブルに発展するおそれがあります。
このような負担を軽減するために「相続時精算課税制度」や「暦年課税の非課税枠(年間110万円)」の活用できるかどうかを確認しておくことが望ましいでしょう。
税務リスクを十分に把握したうえで、必要に応じて税理士など専門家に相談することをおすすめします。
土地を分筆して単独所有にする
土地の場合は、登記上の地番を分けて物理的に分割する「分筆登記」によって単独所有を実現できます。分筆することにより、各共有者が独立した所有権を持ち、自由に利用・処分できるようになります。
例えば、300㎡の土地を3人で共有している場合、それぞれ100㎡ずつに分筆すれば単独所有が可能です。
ただし、分筆には測量費や登記費用がかかるほか、土地の形状や接道条件によっては分割が認められないケースもあります。特に都市部では建築基準法の接道義務(建築基準法42条)などの制限を受けることもあるため、事前に司法書士や土地家屋調査士などに相談しておくことが重要です。
共有物分割請求訴訟を起こす
話し合いがまとまらない場合の最終手段が「共有物分割請求訴訟」です。裁判所が関与し、現物分割・代償分割・換価分割のいずれかの方法で強制的に共有状態を解消します。
競売となった場合、市場価格より低い価格で売却されるのが一般的で、共有者全員にとって不利な結果になる可能性が高くなります。そのため、訴訟に至る前にできる限り協議や調停で解決を模索することが望ましいでしょう。
| 分割方法 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 現物分割 | 不動産を物理的に分割し、それぞれを各共有者が単独所有する方法 | ・接道面積や日当たりなどで価格差が出るため考慮が必要 ・建物がある場合は境界設定が難しい |
| 代償分割 | 1人が単独所有する代わりに、他の共有者へ持分割合に応じた対価を支払う | 単独所有する人に大きな資金負担が生じる |
| 換価分割 | 不動産を売却し、その代金を共有者で分割する | 市場価格より低くなることが多く、全員にとって不利になりやすい |
共有物分割請求訴訟は、共有状態を法的に確実に解消できる有効な手段です。しかし、現物分割・代償分割・換価分割のいずれも当事者に大きな影響を及ぼします。訴訟を検討する際には弁護士に相談し、最適な解決方法を慎重に見極めることが大切です。
自分の共有持分を放棄する
経済的利益を得る必要がない場合には、自分の共有持分を放棄する方法もあります。持分を放棄すれば管理費や維持費といった負担から解放され、共有状態に関わり続ける必要がなくなります。
ただし、当然ながら代金を得ることはできず、資産的価値を失う点には注意が必要です。例えば、持分の評価額が数百万円あったとしても一切の対価を受け取れないため、実質的に財産を手放すことになります。経済的損失を伴うため、生活への影響を踏まえて慎重に判断する必要があるでしょう。
また、放棄の意思表示だけでは効力がありません。そのため、法務局で「持分放棄の登記」を行うことが必須です。
なお、放棄した持分は割合に応じて自動的に他の共有者に帰属します。贈与のように特定の共有者だけに移すことはできません。
共有持分の買取業者における売却相場
弊社にも「共有持分の売却価格は、市場価格に持分割合をかけた金額になりますか?」というご相談が多く寄せられます。
共有持分を買取業者に売却する場合、相場は市場価格に持分割合をかけた金額の2〜5割程度にとどまるケースが一般的です。これは、共有持分が単独で自由に活用できない権利であることに加え、再販や利用に制約が多いためです。
特に、相続人同士で意見が対立しているケースや、立地条件が悪い不動産では、査定額が相場の下限に近づく傾向があります。
例えば、3,000万円の不動産を3人で共有している場合、持分1/3の理論上の価値は1,000万円ですが、実際の売却価格は200万〜500万円程度となるのが一般的です。
一方で、都心などの好立地や開発が見込まれる地域では、相場より高く買い取られる可能性もあります。ただし共有持分の買取価格は、物件の条件や共有者の関係性などによって変動するため、一律に判断することはできません。
そのため、売却を検討する際は複数の買取業者に査定を依頼して比較することが不可欠です。実際に査定額が2〜3倍近く異なるケースもあるため、最低でも2〜3社に見積もりを取り、価格の妥当性を確認することをおすすめします。
なお、一般の個人が共有持分を購入することはほとんどなく、不動産仲介会社でも取り扱いを断られるケースが大半です。つまり、共有持分は需要が低く、売れづらい権利だという点を理解しておく必要があります。
弊社クランピーリアルエステートでも、全国の共有持分を専門的に買い取っています。「相場より安くなるのでは」と不安な人も、無料査定を利用すれば実際の売却可能額を確認できます。
共有状態から早期に抜け出したい方は、ぜひ一度ご相談ください。
まとめ
共有持分を買取業者に売却することは、共有状態から早期に抜け出せる有効な選択肢の1つです。しかし一方で「安値での買い叩き」「強引な営業」「立ち退き請求」「訴訟」など、業者とのやり取りや残された共有者との関係でトラブルが生じるリスクも存在します。
こうしたリスクを避けるためには、宅建業免許の有無、買取実績、口コミや評判、弁護士との連携体制などを確認し、信頼性を見極めることが大切です。
信頼できる業者に依頼すれば、共有者間で意見がまとまらない場合でも、迅速かつ適切に現金化や問題解決を進められます。共有持分の売却を検討する際は、複数の買取業者に査定を依頼し比較するとよいでしょう。
弊社クランピーリアルエステートは、宅建業免許を有し、弁護士とも連携しながら共有持分の買取を専門的に行っています。トラブルに不安を感じている人も、まずは無料査定からお気軽にご相談ください。