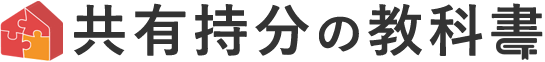賃借権とは、文字どおり「賃料を支払う代わりに不動産を借りる権利」で、借りる側の権利を守るために借地借家法という法律で規定されています。
賃貸借契約でトラブルが起こった場合、貸す側も借りる側も借地借家法の理解が重要といえるでしょう。
共有不動産を貸し出したいときは、共有者の同意が必要です。貸し出す期間にもよりますが、長期の賃貸借なら共有者全員、短期の賃貸借なら共有持分の半数が同意している必要があります。
ちなみに、現在貸し出し中の不動産でも、共有持分だけであれば売却できます。売却したい共有持分がある場合は、専門買取業者に相談してみるとよいでしょう。
>>【最短12時間で価格がわかる!】共有持分の買取査定窓口はこちら

- 賃借権とは「賃料を払う代わりに、所有者に不動産の使用許可をもらう権利」
- 所有者の承諾があれば賃借権の譲渡・又貸しも可能。
- 共有不動産を貸し出すには共有者の同意がいる。
- 賃借権は「賃料を支払う代わりに契約の範囲で土地・建物を使用する権利」
- 「借地借家法」は賃借人(=借りる人)の権利を強化するための法律
- 所有者の承諾があれば共有持分において賃借権の譲渡や又貸しは可能
- 共有不動産を貸すときには「共有者全員の同意」or「持分の過半数」が必要
- 不動産の貸し借りは当事者双方が「賃借権」を理解することが重要
賃借権は「賃料を支払う代わりに契約の範囲で土地・建物を使用する権利」
賃借権とは「賃料(=対価)を支払ってものを借りるときに発生する権利」です。貸し借りに関する契約における、借りる側の権利になります。
不動産においては、これとは別に「使用貸借」という言葉があります。これは、家族や親戚に住宅を無償で貸すことを指す言葉で、借りる側に賃借権は発生しません。
賃借権が発生するのは、対価を支払う契約の場合のみと考えましょう。
使用貸借は賃借権とは異なる権利になるため、こちらの記事を参考にしてください。
 共有持分における使用貸借の概要や強制退去させる条件|賃料請求が困難な理由も解説!
共有持分における使用貸借の概要や強制退去させる条件|賃料請求が困難な理由も解説!
共有持分のみに賃借権を設定することはできない
土地や建物を複数人で持つことを共有といい、それぞれの所有権を共有持分といいます。
そして、貸し借りという行為には「貸す人=所有者」と「借りる人=賃借人」が必ずいます。そのため、所有権そのものを貸すという行為はそもそも成り立ちません。
また、共有持分は土地を実際に区分けしているわけでもありません。「1,000万円の土地のうちAとBで1/2ずつ、500万円分の持分」という、価格を基準に考えるものです。
これらのことから、共有持分のみに賃借権を設定することはできないといえます。
賃借権を「準共有」することはできる
賃借権も準共有できる権利となります。複数人で1つのものを借りるということは日常でもあると思いますが、それと同じイメージです。
本来、共有という言葉は「共同で所有する」という意味です。つまり、所有権にしか使えない言葉ともいえます。そのため、法律では所有権以外の権利を共同でもつときは「準共有」といいます。
言葉の違いはありますが、扱いとしては同じものです。所有権のときは「共有」で、それ以外の権利のときは「準共有」と呼ばれる、と覚えておきましょう。
所有者が不動産を分割しても賃借権は引き継がれる
共有の土地の場合、土地を分筆(切り分けて別々の土地にすること)して共有関係を解消することがあります。自分が借りている土地が分筆された場合、賃借権はそれぞれの土地の所有者と改めて契約することになります。全員がそろっての契約しても、所有者ごとに個別に契約しても大丈夫です。
このとき、分筆したことで自分の建物がある土地とない土地に分かれてしまう恐れがあるため注意が必要です。感覚的には「建物がなくなった土地の賃借権」は消滅してしまうようにも思えますが、実際はどうでしょうか。
この場合、分筆はあくまで土地所有者の都合によるものなので、借地人の権利が狭められるのは妥当ではないという判例があります。つまり、分筆の結果で建物のないスペースが切分けられても、その部分の賃借権は維持されると考えられます。
賃借権と地上権の違いは「権利の対象」が人か土地かの違い
不動産の賃借権を調べるときに、地上権という言葉を見た方もいると思います。この2つの用語が並んでいるとき、賃借権は「土地の賃借権」を指していることがほとんどです。つまり、どちらも「土地を借りる権利」という意味で使っています。
地上権は「土地に対して直接的に支配・使用する権利」です。一定の目的であれば所有者並の権限があります。
土地の賃借権は「所有者に対して土地の使用許可をもらう権利」です。どのように使うかの決定権は所有者にあります。
地上権のような「物に対する権利」を物権、賃借権のような「人に対する権利」は債権といいます。基本的に物権は債権より優先されますが、近年では借りる側の保護するために賃借権は強化され、物権に近い権限を持つケースもあるため注意が必要です。
地上権については別の記事で詳しく解説しているので、そちらも参考にしてみてください。
 地上権とはどんな権利?共有不動産における法定地上権の発生基準などを解説します
地上権とはどんな権利?共有不動産における法定地上権の発生基準などを解説します
土地が目的の「借地権」と建物が目的の「借家権」の違い
不動産を借りるときの権利として、借地権や借家権という言葉を耳にした方もいると思います。
上記の項目で触れた土地の賃借権や地上権など、土地を借りるときに発生するのが「借地権」です。
それに対して、住居・店舗・オフィスビルなどの建物を借りるときにいわれるのが「借家権」です。法律の中に「借家権」という言葉はありませんが、不動産用語としてよく使われるもので、建物の賃借権と考えましょう。
不動産の賃借権を調べるとき、これらの言葉の定義がわからず苦労される方も多いと思います。基本的な知識として、下記の3つをしっかり把握しておきましょう。
- 不動産を借りる権利=「借地権」と「借家権」
- 借地権=「土地の賃借権」と「地上権」
- 借家権=「建物の賃借権」
「借地借家法」は賃借人(=借りる人)の権利を強化するための法律
賃貸借契約においては、貸す側より借りる側の立場が弱くなりがちです。しかし、不動産は生活や経済活動の基盤であるという性質上、借りる側の権利を守るように法整備されてきました。
「借地借家法」は、そのような経緯で作られた法律です。過去にあった「借地法」や「借家法」を統一して、現代に合わせた内容になっています。
「借地借家法」では、どのように賃借人の権利が守られているのかを見ていきましょう。
借地権は「借地上の建物を所有」すれば主張できる
不動産の権利は、登記することで公に認められます。当事者間の合意だけでは、第三者に主張しても認められません。登記がなければ、トラブルが起きても権利の事実を証明できないのです。
借地権も本来であれば、登記によって初めて主張できます。しかし、借地権登記には土地所有者の協力が必要です。これでは、借地人の権限が土地所有者に握られている状態と変わりません。
立場の優劣を解消するため、借地借家法では「借地上の建物の所有登記」があれば借地権も認められるとしました。
借地借家法第10条
借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
借地上の建物に関する権利は土地所有者には関係ないので、協力がなくとも登記できます。つまり、借地借家法によって借地人は自分の行動だけで借地権を主張できるようになったのです。
借地契約の終了時には「建物の買取」を土地所有者に請求できる
借地契約が更新されないときや、借地上の建物を譲渡するときに借地権と共に譲渡することを土地所有者が拒否した場合、借地上に建てたものを土地所有者に買取してもらう制度があります。
「建物買取請求権」といい、借地人の意思表示があれば土地所有者は拒否できません。
しかし、期間の定めがある定期借地契約の場合は、特約がなければ請求できません。他にも細かな条件で請求できないことがあるので、請求する際は不動産に強い弁護士に相談することをおすすめします。
借家権は「建物の引渡し」で成立する
借地権は「借地上に建物を所有することで認められる」と説明しましたが、借家権は「建物の引き渡し」が完了した時点で成立します。
借地借家法第31条
建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。
建物の引き渡しは「鍵の受け渡し」によって成立します。また、契約書に日にちを記載しておくことも一般的です。
借家契約の終了時には「建物に付け加えた造作の買取」を建物所有者に請求できる
借家契約の場合は、契約期間中に建物に付け加えた造作を建物所有者に買取してもらう「造作買取請求権」が発生します。
造作とは建物の内部を構成する要素で、扉・窓・畳・床といったものや、水道や空調などの設備を指します。
条件として、それらの造作を付け加えるときに建物所有者から同意を得なければなりません。また、契約のときに造作買取請求を禁止する特約を結んでいる場合もあるため注意しましょう。
「不動産の不法な占有」に対して借りている人が直接排除できる
第三者が不法に土地や建物を占有しているとき、賃借人が直接これを排除できるという規定があります。
民法第605条の4
不動産の賃借人は(中略)対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
1.その不動産の占有を第三者が妨害しているとき その第三者に対する妨害の停止の請求
2.その不動産を第三者が占有しているとき その第三者に対する返還の請求
賃借権を持たない第三者が勝手に住んでいたりするとき、賃借権があれば所有者を通さずに立退き請求や訴訟を起こせます。
占有状態が長く続くと「賃借権の取得時効」が成立する
占有とは「ものに対して直接的に支配・管理する行為」ですが、第三者でも長期間占有していると「ものに対する権利」を取得するとされています。
民法第162条
1.20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2.10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。民法第163条
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。
民法第162条は所有権についての規定で、第163条は賃借権を含むその他の権利を指しています。
「所有(賃借)するつもりで義務を果たし、かつ暴力や意図的な隠しごとをしていない」と判断されれば20年で取得時効は成立します。占有開始時から「自分のものである」と信じていた場合は10年で成立します。
もし所有権や賃借権が第三者に侵されている場合、その権利を取り戻すには早く行動しなければなりません。
土地の賃貸契約は期間の定めや目的によって種類がわかれる
土地の賃借権には、その目的や期間によっていくつかの種類に分けられます。
法律改正前の「旧法借地権」と、改正後の「普通借地権」「定期借地権」があります。定期借地権はさらに3つに分けることが可能です。
それぞれどんな借地契約なのか見ていきましょう。
1992年8月以前の借地権は旧借地法が適用される
借地借家法は、1992年8月に改正された新しい法律のため、それ以前にあった借地権に関しては、古い法律の規定が引き続き適用されるため注意しましょう。
「旧法借地権」ともいわれ、現在の借地権との違いは建物を堅固建物(石造やコンクリート造など)と、非堅固建物(木造など)に分けていることです。それぞれで契約期間が違い、また期間満了後に契約更新することを前提としています。
【堅固建物の場合】
| 契約時に期間を定めない場合 | 契約時に期間を定める場合 | |
|---|---|---|
| 最初の契約期間 | 60年 | 30年以上 |
| 契約更新ごとの期間 | 30年 | 30年以上 |
【非堅固建物の場合】
| 契約時に期間を定めない場合 | 契約時に期間を定める場合 | |
|---|---|---|
| 最初の契約期間 | 30年 | 20年以上 |
| 契約更新ごとの期間 | 20年 | 20年以上 |
旧法借地権から現在の借地借家法へは自動的に切り替わらないので、必要であれば旧法の契約を解除して現行の借地借家法で契約し直す必要があります。
普通借地権は更新が前提になる
1992年8月1日以降に契約した借地権は、現行の借地借家法が適用されます。
このうち、期限の定めのないものが「普通借地権」です。旧法と同じように契約の更新が前提ですが、建物の種類による区別はなくなりました。期間についても全体的に短くなっています。
| 契約時に期間を定めない場合 | 契約時に期間を定める場合 | |
|---|---|---|
| 最初の契約期間 | 30年 | 30年以上 |
| 初回更新時の期間 | 20年 | 20年以上 |
| 2回目以降の更新の期間 | 10年 | 10年以上 |
期間を定める定期借地権は3種類ある
現行の借地借家権では、期間を定める「定期借地権」があり、この中にはさらに3つの種類があります。
「一般定期借地権」と呼ばれるものは、50年以上の年数で期間を設定し、期間満了時には更新せず更地にして土地を返還する契約になります。建物買取請求もできません。
「事業用定期借地権」は期間を10年以上50年未満とし、ショッピングモールなどを想定しているので居住目的の利用はできません。こちらも期間満了後は更地にして返す必要があり、建物買取請求権をおこなえません。
「建物譲渡特約付借地権」は30年以上の期間を定め、期間満了後は土地所有者が建物を買取することをあらかじめ決めておく契約です。他の定期借地権や普通借地権とも併用できます。
期間を定めることで、土地所有者が安心して貸し出せるようになり、土地の流動性が上がることで借りる側も借りやすくなるという好循環が生まれます。
建物の賃貸契約は契約期間を定めるか否かの2種類
建物は、土地と比べると賃貸契約のバリエーションは多くありません。
一般的な賃貸借契約である「普通借家契約」と、契約の更新がない「定期借家契約」があります。定期借家契約は、2000年に施行された比較的新しい制度です。
それぞれの特徴を見ていきましょう。
更新が前提となる普通借家契約
普通借家契約では、借主に更新の意思がある限り契約の解除はされません。
期間の最低年数は1年以上で、実際には2年契約であることが一般的です。1年未満の期間で契約しても「期間の定めがない契約」とみなされます。
建物所有者側からの契約解除は、6ヶ月以上前の通告の他、解除の理由やこれまでの経緯などから「正当である」と判断されなければいけません。
期間を定める定期借家契約
普通借家契約では借りる側の立場が強く、所有者が建物に対して自由度が低いという問題がありました。借主が問題のある人物だったり、建物が老朽化して取り壊しをしたくても契約解除は簡単にできません。このような問題を解決するため、あらかじめ期限を決めておく定期借家契約が制定されました。
定期借家契約は基本的に契約の更新はせず、1年未満の契約も可能です。
一般的な賃貸より安い家賃の物件も多く、借りる側としても短期で借りたい場合はメリットがあります。
賃借権の解除や更新が認められる正当な事由
「借地借家法」において、所有者から契約解除や更新拒否をする場合、判断基準は以下の4つです。
土地でも建物でも同じ基準で、当事者双方の事情を総合的に考えて判断されます。
- 所有者及び借地人が土地の使用を必要とする事情
- 契約が設定されたときや賃料の支払状況などこれまでの経緯
- 利用状況
- 立ち退き料の有無やその内容
悪意のある賃料の未払いが続くなど、余程のことがない限りは賃借人の方を優先して考えられます。
所有者の承諾があれば共有持分において賃借権の譲渡や又貸しは可能
共有持分は権利関係が複雑なため、売却で手放したいと考える人も少なくありません。
共有持分だけでも売却可能で、共有持分専門の買取業者もいます。しかし、対象の不動産が例えば「借地権付き建物」だと、売却可能か不安な方もいるでしょう。
この場合に重要なのは「自分の不動産と一緒に借地権も売却できるのか」という点ですが、土地所有者の承諾さえあれば借地権も売却できます。建物についても同様で、建物所有者の承諾があれば借家権を売却できます。
自分の持分だけを売却するなら共有者の同意はいりません。所有者の許可さえあれば大丈夫なので、もしもその交渉が難しいときは、共有持分専門の買取業者に相談してみるのも1つの手段といえるでしょう。
また、賃借権を設定して借りている土地や建物を又貸しすることも、同じように所有者が承諾していれば可能です。
共有者同士での譲渡であれば所有者の承諾は不要
準共有している賃借権の持分を譲渡するとき、その相手が同じ賃借権の共有者あれば土地所有者の承諾はいりません。
これは、賃借人に新たに第三者が入るわけではないので「所有者にとって不利益はない」と考えられるためです。
需要の面から見ても、賃借権の共有持分を購入してくれる人は多いとはいえません。共有者ならば、もともと持っている自分の権利を一本化することになるので、交渉もスムーズに進みやすいでしょう。
「所有者に不利にならない」のであれば裁判所に譲渡・又貸しの許可がもらえる
所有者に許可がもらえなくても、裁判所に申立てすると譲渡や又貸しを認められるケースもあります。
借地借家法第19条
借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において(中略)借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる~
裁判所が許可を出すにあたっては、譲渡・又貸しが必要である理由、賃借権の残り期間やこれまでの経緯を総合的に判断します。
賃借人が亡くなった場合は賃借権が相続される
賃借権の譲渡や又貸しは可能と解説しましたが、賃借人が亡くなった場合、賃借権はどうなるのでしょうか。
この場合は賃借権が消滅せず、相続人へ引継がれることになります。そのため、所有者と相続人の間で賃料の支払いや契約の継続について協議する必要があります。
相続人が「自分たちは住んでいないから関係ない」と放置していると、不払いの賃料に対して支払い義務が発生してしまいます。遠隔地などで手続きが面倒であれば、弁護士や司法書士に委任することも検討しましょう。
賃借人が亡くなったときでも内縁の配偶者は住み続けることができる
亡くなった賃借人が内縁の配偶者と同居していた場合は、相続人がいるかどうかで判断が変わります。
相続人がいない場合、内縁の配偶者が賃貸借の契約を引き継げます。
借地借家法第36条
居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において(中略)建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する(中略)一月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
賃借権が相続人に相続された場合でも、裁判では「内縁の配偶者が住み続けられる」とする傾向にあるため、賃料の支払いをどうするかなど、相続人と内縁の配偶者で話し合うことが必要です。
共有不動産を貸すときには「共有者全員の同意」or「持分の過半数」が必要
共有不動産を貸し出したいと思ったとき、他の共有者から反対されてしまうというケースがよくあります。
他の共有者の承諾がなくとも貸し出しできればいいのですが、実際にはそうはいきません。共有不動産を賃貸に出すには、共有者の同意がなければできないのです。
それでは、いったいどれだけの同意を得られれば貸し出すことができるのか、その内容を解説します。
全員の同意が必要な「変更行為」と共有持分の過半数が必要な「管理行為」がある
共有不動産に対しておこなう行為には、全員の同意が必要な「変更行為」と共有持分の過半数が必要な「管理行為」があります。
変更行為は不動産の価値や形を大きく変える行為で、建物の新築や土地の造成、長期の賃貸借契約が挙げられます。管理行為は部分的なリフォームや、5年以内の短期賃貸借契約などです。
管理行為に必要な「共有持分の過半数」に人数は関係なく、持分の何割かで判断されます。誰かの持分が1/2を少しでも超えていれば、その人だけで実行可能です。
「借地借家法が適用される賃貸借契約」は変更行為とされるのが一般的
借地借家法が適用される賃貸借契約の場合、定期借家契約以外は「変更行為」と判断されます。最低年数の存在や契約の更新を前提とすることから、ほぼ確実に長期化するためです。
ただし、共有者間で「賃料収入にしか使わない」という同意がある場合、共有者全員の不利益にならないときは過半数の同意で契約が有効になることもあります。
事例によって解釈はさまざまなので、共有不動産を貸し出すときは共有者全員から同意を得たほうがよいでしょう。
「一時的な賃貸契約」は借地借家法が適用されない
短期間の使用を目的として借りる場合、借地借家法は適用されず、貸し出す方も管理行為として持分の過半数があれば契約可能です。
事例としては、自宅の改装工事中の仮住まいや選挙事務所などがあります。
借地借家法では、定期借家契約でもないかぎり1年未満の契約は「期間の定めがないもの」とされますが、これはあくまで賃借人を守るための制度であり、当事者間で短期の賃貸借であると明確に認識されていれば、適用外となります。
賃貸借契約における主な管理行為
借地借家法が適用される賃貸借契約はほとんどが変更行為になると説明しましたが、これはあくまで契約を結ぶときの話です。
共有不動産を貸し出すときは、賃貸契約を結ぶとき以外にも所有者の意思決定が必要になります。
その代表的な場面をいくつか解説していきます。
賃貸借の「解除の意思決定」
賃貸借を解除する行為は、持分の過半数で可能です。
所有者側からの賃貸借契約の解除は困難ではありますが、不可能ではありません。賃借人側が賃料を滞納するなど過失があれば認められます。
共有者間の意見が対立しても、持分の過半数があれば全員の同意を得ずに賃貸借を解除できます。
一般的な賃料の変更
当事者間の協議や交渉によって、賃料が変わることはありえます。所有者側から値上げを申し入れることがあれば、賃借人から値下げを要求されることもあるでしょう。
賃料の価格変更に関しても、通常は管理行為とみなされます。
しかし、賃料変更によって共有者に与える影響が大きい場合は、変更行為とみなされることがあります。事例によって細かな違いがあるサブリース契約に多い事例なので、そのような契約をしているときは不動産会社や弁護士に事前に確認してみましょう。
賃借権譲渡の承諾
賃借権の譲渡を賃借人から相談されたとき、その承諾も管理行為として持分の過半数で決定できます。
賃借権の譲渡は、賃料の支払いなど契約内容はそのままであるため、変更行為と考えるほど共有者への影響は大きくないと判断されるためです。
このように、変更行為か管理行為かの基準は共有者にどれだけ影響があるかが重要となります。
「不法な占有者への明け渡し請求」は共有者単独でできる
管理行為や変更行為について解説しましたが、これらとは別に共有者の1人が単独でできる「保存行為」があります。保存行為とは、共有不動産の価値を維持しつつ、他の共有者にも不利益がない行為です。
不動産に対して何の権利もない占有者がいた場合、共有者であれば誰でも単独で排除できます。
事例としては、賃借権がないのに入居している場合、許可もなく資材置き場として土地を利用している場合の明け渡し請求などがあります。
不動産の貸し借りは当事者双方が「賃借権」を理解することが重要
不動産の貸し借りは、じつは意識をしていないだけでとても身近な話題です。
貸し出すという行為は不動産の権利を部分的に渡すことに変わりません。なんとなくで契約を結ばずに、どのような制約が生まれるか理解しておくことが大切です。
また、借りる側も自分がもつ権利をしっかりと把握しておくことはとても重要です。そうすれば、何かトラブルが起きたとしても適切な対処がとれます。弁護士などのサポートを受けながら、自分の生活を守るためのアクションを起こしましょう。
賃借権についてよくある質問
賃借権とは「賃料を支払う代わりに契約の範囲で土地・建物を使用する権利」です。貸し借りに関する契約における、借りる側の権利になります。
いいえ、できません。共有持分とは、共有不動産における各共有者の所有権を指すものであり、所有権を貸すことはできません。ただし、賃借権の名義人を複数人にすることは可能です。所有権以外の権利を共有するときは「準共有」と呼ばれます。
短期(5年以下)の賃貸借契約なら、共有持分の過半数が同意すれば締結できます。5年超の賃貸借契約は、共有者全員の同意が必要です。ただし、借地借家法が適用される賃貸借契約は、契約期間が5年以下でも共有者全員の同意が必要になります。
借地借家法が適用される場合、賃借人が強く保護されるため、特別な事情がない限りは賃貸借契約が都度更新されます。したがって、実質的に長期の賃貸借となるため、共有者全員の同意が必要になります。
地上権は「土地を直接的に支配する権利」であり、権利の対象が土地そのものである「物権」です。一方、賃借権は「土地を他者に貸し出して使わせる権利」であり、権利の対象が人である「債権」になります。