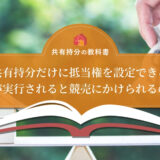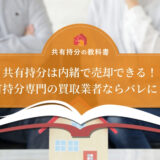不動産の売買や贈与などをしたときは、所有者の情報を明らかにするために法務局で登記をする必要があります。
共有不動産における各共有者の所有権である「共有持分」の場合も同様で、共有持分の登記は「持分移転登記」といい、不動産全体の登記は「所有権移転登記」といいます。
持分移転登記も所有権移転登記も、主な費用は「登録免許税」と「司法書士報酬」の2種類が発生します。
登記する共有持分の価格によって費用は異なりますが、数万〜数十万円はかかるのが一般的です。
共有持分を売却するときは、共有持分専門の買取業者に相談することをおすすめします。高額買取と最短数日の現金化が可能なうえ、持分移転登記の手続きや費用についてもアドバイスがもらえるでしょう。
>>【最短12時間で価格がわかる!】共有持分の買取査定窓口はこちら

- 共有持分の登記にかかる主な費用は「登録免許税」と「司法書士報酬」の2つ。
- 登記を自分ですると費用を抑えられる。
- 持分移転登記と所有権移転登記のいずれも費用は同じ。
共有持分の登記にかかる主な費用は「登録免許税」と「司法書士報酬」の2つ
登記にかかる費用は主に「登録免許税」と「司法書士への報酬」の2種類です。
しかし、土地家屋調査士への依頼が必要となる登記では、その報酬が発生する場合もあります。
登録免許税は登記の種類によって金額が変わり、軽減措置もあるのでまずは自分がどの登記をするのか調べましょう。
登記目的別の登録免許税と軽減措置
登記をする不動産が共有持分だとしても、基本的な方法や必要書類などは通常の登記と変わりません。
ただし登記の対象が共有持分の場合、登記費用は持分割合に応じて納めることが登録免許税法で定められています。
登録免許税法第3条
登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。この場合において、当該登記等を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。引用:e-Govポータル「登録免許税法第3条」
登録免許税の金額は、基本的に以下の計算式で求められます。
- 登録免許税=課税標準額×税率
登録免許税は不動産の売買する価格とは関係なく、市役所などが決定する「固定資産税評価額」をベースに計算します。
「売買」や「相続」による登記の場合、不動産の価額である「固定資産税評価額」が課税標準額です。
ただし「住所変更」や「抵当権の抹消」といった場合の課税標準額は「不動産の個数」となり、不動産1個につき1,000円です。
登録免許税を求める際の税率や軽減措置は、登記の種類や不動産の状況によって変わるため、詳細は国税庁のページを参考にしてください。
参照:国税庁
所有権移転登記の登録免許税
すでに誰かが所有している不動産の所有権を移転させる場合「所有権移転登記」が必要です。
具体例としては、中古住宅や誰かが所有していた土地の売買などがこのケースに該当します。
所有権移転登記に必要な登録免許税は、以下の計算式で求められます。
- 登録免許税=不動産の価額×20/1000
登記する不動産が土地の場合、令和3年3月31日までに登記をすれば税率が15/1000に軽減されます。
所有権保存登記の登録免許税
新築の住宅など、過去に誰も所有していない不動産を取得するときは「所有権保存登記」が必要です。
所有権保存登記に必要な登録免許税は、以下の計算式で求められます。
- 登録免許税=不動産の価額×4/1000
また所有権保存登記では、次の条件を満たせば、税率が1.5/1000となる軽減措置が受けられます。
個人が、令和4年3月31日までの間に住宅用家屋を新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記引用:国税庁
ただし、登記後に証明書を提出しても軽減措置は受けられないので、必ず登記前に申請しておきましょう。
また、新築建物だと市役所などが出す固定資産税評価額がない場合がありますが、この場合は建物の床面積をベースに固定資産税評価額を算出します。
詳しくは法務局のページを参考にしてください。
参照:法務局ホームページ
抵当権設定登記の登録免許税
住宅ローンを組む場合など、不動産に抵当権を設定するときは「抵当権設定登記」が必要です。
抵当権設定登記に必要な登録免許税は、以下の計算式で求められます。
- 債権金額×4/1000
また抵当権設定登記でも、下記条件を満たせば、税率が1/1000に軽減されます。
個人が、令和4年3月31日までの間に住宅用家屋の新築(増築を含む。)又は住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記引用:法務局ホームページ
抵当権設定登記における軽減措置は、新築に限らず中古の不動産でも同様の条件です。
司法書士への報酬
司法書士へ登記を依頼する場合、報酬は司法書士と依頼者との間で決まります。
そのため金額はケースによって異なりますが、司法書士報酬の相場は6~10万円程度が多いです。
ただし、共有持分の登記をする場合、司法書士事務所によっては共有者全員へ報酬を請求するので相場以上に費用がかかるケースもあります。
依頼後に司法書士と費用に関して揉めないためにも、見積もりの時点で「共有持分の登記」をする旨をきちんと伝えておきましょう。
土地家屋調査士への報酬がかかる場合もある
登記によっては、土地家屋調査士への報酬がかかる場合があります。
土地家屋調査士への依頼が必要になる登記は、主に「表題登記」と「地目変更登記」の2種類です。
この2つの登記は、司法書士へ依頼をすることもできますが、より事情に精通している土地家屋調査士へ依頼するのが一般的です。
土地の用途を変更するなら地目変更登記が必要
もともと登記簿に登録されている土地の用途を別の用途へ変更する場合「地目変更登記」が必要です。
例えば、農地として登記されている土地を宅地として利用したい場合などには、この地目変更登記が必要になります。
地目変更登記は、土地の利用用途を変更した時点から1ヵ月以内におこなわなければなりません。
期限を過ぎると10万円以下の過料が課せられてしまうため注意しましょう。
地目変更登記は通常の登記よりも専門的な項目が多く、自分で登記をするのは非常に大変です。
例えば、農地を農地以外に変更する場合、農地法の知識が必要になるため、土地家屋調査士へ依頼をするのがおすすめです。
ちなみに地目変更登記の場合、登録免許税はかかりません。
建物を新築したら建物表題登記が必要
新築住宅など初めて登記される不動産を新規で登記する場合「建物表題登記」が必要です。
建物表題登記は建物の完成、または購入後1ヶ月以内に必ず行わなければなりません。
不動産登記法でも、建物表題登記を怠ると10万円以下の過料を課せられると定められています。
この建物表題登記にも、登録免許税は課税されません。
持分移転登記と所有権移転登記の費用は同じ
持分移転登記と所有権移転登記の違いは「登記する不動産が単独名義か?共有名義か?」という点だけです。
そのため、持分移転登記と所有権移転登記の登記費用は変わりません。
持分移転登記と所有権移転登記の違いについては、以下の記事でくわしく説明しているので参考にしてください。
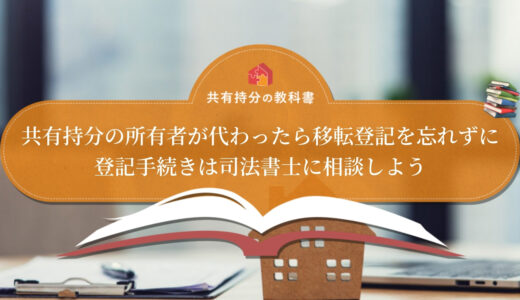 共有持分の移転登記が必要な状況を詳しく解説!登記費用や税金についても説明します
共有持分の移転登記が必要な状況を詳しく解説!登記費用や税金についても説明します
登記費用を安くするには自分で登記をする
「登録免許税」は登記をする際に納めなければならない税金です。
そのため、登記費用を抑えたいのであれば、司法書士報酬を削るしかありません。
登記を司法書士に任せつつ費用を抑えたい場合、報酬について交渉してみるか、費用の安い事務所へ依頼をするとよいでしょう。
もし登記費用を抑えたいのであれば、司法書士に頼らず自分で登記するのがベストです。
この項目では、司法書士へ依頼せずに自分で登記する方法を解説します。
登記を自分でするときの手順
登記を自分でするときの手順は次のとおりです。
- 申請書と必要書類を集める
- 申請書を作成する
- 申請書と必要書類を提出する
- 法務局から登記完了証及び登記識別情報を受け取る
建物表題登記と地目変更登記以外であれば申請期限はありませんが、なるべく早く登記を済ませたほうがよいでしょう。
登記をしないままだと、前の所有者が抵当権を設定してしまうといったトラブルに発展する恐れがあります。
より詳しい登記の流れは、法務局のページを参考にしてください。
参照:法務局ホームページ
登記に必要な書類と費用
登書類とその発行手数料は、基本的に以下のとおりです。
- 住民票・・・300円
- 固定資産税評価証明書・・・300円
- 印鑑登録証明書・・・450円
ただし、登記原因によって必要書類は異なります。
また、発行手数料は自治体によって違う場合もあるので、必ず登記前には必要書類と費用を管轄の自治体に問合せしておきましょう。
司法書士に依頼するのが確実で早い
ここまで説明したように、司法書士に依頼しなくても自分で登記ができます。
ただし、法務局では窓口で登記の申請内容を確認していないため、もし書類や記入内容に間違いがあったときは再び法務局へ出向かなければなりません。
また、オンライン申請などもありますが、法務局は平日しか登記申請を受付していないため、仕事をしていると時間を取れない方も多いです。
ですので、手続きに不安があったり平日に時間が取れない場合は、費用をかけてでも司法書士へ登記を依頼した方がよいかもしれません。
参照:法務局ホームページ
ケース別の登記費用例を紹介
登記費用の仕組みはわかりましたが、実際に登記すると何円くらいかかるのでしょうか。
ここでは2つの具体例を使って、登記費用がどのくらいかかるのか紹介します。
- マイホームを新築購入した場合
- 不動産を相続した場合の登記費用
ちなみに今回は軽減税率やその他諸費用は考慮せず、登録免許税のみを算出しています。
マイホームを新築購入したときの登記費用例
新築のマイホームを3,000万円で購入した場合の登録免許税は約21万円です。
※建物の価額が2,000万円、土地の価額が1,000万円と想定。
内訳は以下のとおりです。
- 新築建物の登録免許税:2,000万×3/1000=6万
- 土地の登録免許税:1,000万×15/1000=15万
司法書士に依頼する場合、さらに6~10万円程度の報酬もかかります。
不動産を共有名義で相続したときの登記費用
3,000万円の不動産を2人で1/2ずつ相続した場合の登録免許税は約12万円です。
内訳は以下のとおりです。
- 登録免許税:3,000万×4/1000=12万
登記にかかる金額は持分割合に応じた金額を支払うのが一般的です。
また司法書士に依頼する場合、さらに6~10万円程度の報酬が必要です。
なお相続による土地の所有権移転登記は免税措置があるので、国税庁のページを参考にするとよいでしょう。
参照:国税庁
共有持分を名義変更するときも登記が必要
共有持分を名義変更するときも登記が必要です。
名義変更は、その不動産を管轄する法務局へ申請をします。
管轄の法務局と自宅が離れているときなどは、郵送やオンライン申請を利用するとよいでしょう。
名義変更の明確な理由が必要
平成17年に不動産登記法が改正され、名義変更の登記申請をする際に「登記原因証明情報」という書類の添付が義務化されました。
登記原因証明情報には、名義変更が必要となった原因を詳細に記載しましょう。
登記原因の主な例としては、以下のようなケースが挙げられます。
- 離婚によって共有持分をAがBへ財産分与した
- AがBへ売却した
- Aの死亡により財産をBが相続した
共有名義を単独名義に変更する方法
共有持分の贈与や売買において契約書の作成は義務化されていませんが、後のトラブルを防ぐためにも契約書を作成することをおすすめします。
また、共有持分の放棄は他共有者の同意がなくても可能ですが、登記には他共有者の協力が必要になるため、事前に伝えておいたほうがよいでしょう。
共有名義から単独名義に変更する方法は様々ですが、その中でも共有者間でおこなう代表的な方法を3つ解説します。
共有持分を贈与する
共有持分を他共有者へ贈与することで単独名義にできます。
贈与とは、金銭などの対価なく無償で相手に財産を分け与えることです。
なお共有持分を贈与をすると贈与税が課せられるため注意が必要です。
ただし、年間に贈与された財産の合計額が110万円以下であれば控除が適用されるので活用するとよいでしょう。
共有持分を売買する
共有持分を共有者同士で売買することで共有名義から単独名義にできます。
この場合、共有者同士で自由に金額を決められますが、市場相場よりも大幅に低い金額に設定してしまうと贈与税が課せられることがあるので注意しましょう。
なお登記するときの登記原因には「売買の経緯」を記載すれば問題ありません。
共有持分を放棄する
共有持分そのものを放棄することで、共有名義から単独名義にできます。
共有持分を放棄すると、放棄した持分は他共有者へ持分割合に応じて帰属します。
つまり、他共有者は意図せず新たに共有持分を受け取ることになるのです。
また放棄によって不動産を取得すると税法上は贈与とみなされるため、贈与税が発生することがあるので注意が必要です。
また、共有持分の放棄そのものは自由にできますが、その登記は他共有者の協力が必要になるため事前に了承を得ておいたほうがよいでしょう。
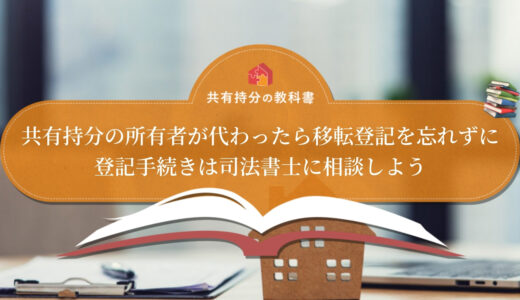 共有持分の移転登記が必要な状況を詳しく解説!登記費用や税金についても説明します
共有持分の移転登記が必要な状況を詳しく解説!登記費用や税金についても説明します
共有持分の登記費用は基本的に持分割合に応じて負担する
登記をする不動産が共有持分でも、基本的な手順や費用、必要書類などは通常の登記と変わりません。
ただし、登記費用は持分割合に応じて支払うことが登録免許税法で定められています。
登記にかかる費用は主に「登録免許税」と「司法書士報酬」ですが、費用を抑えたいときは司法書士へ依頼せずに自分で登記すれば、司法書士報酬を払わずに済みます。
「登録免許税」は登記のときに必ず課せられる税金ですが、この記事で紹介した軽減措置などを活用すれば費用を抑えることも可能です。
軽減措置は、登記前に申請をしないと受けられない場合もあるので、申請前に国税庁のホームページや法務局の窓口で確認しておきましょう。
共有持分の登記についてよくある質問
共有持分とは、複数人が共有する不動産において「各共有者がどれくらいの所有権をもっているか」を指すものです。「持分1/2」というように、割合で表記します。
不動産の所在地や広さといった情報と、権利関係を登記簿に記載することをいいます。不動産の売買や相続などで権利関係に変更があった場合、法務局で登記申請をおこないます。
はい、自分でも登記手続きは可能です。ただし、添付書類の準備や申請書の記入は法律の知識も必要になるため、登記の専門家である司法書士に代行してもらうのが一般的です。
費用の相場と内訳は、必要書類の取得費として数百~数千円、司法書士報酬として数万~十数万円ほど、登録免許税は「課税標準額(不動産の評価額)×4/1000」です。個別の事情によって大きく異なる可能性もあります。
原則、持分割合に応じて共有者全員が分担します。持分割合が1/2ある人は、登記費用も全体の1/2負担します。