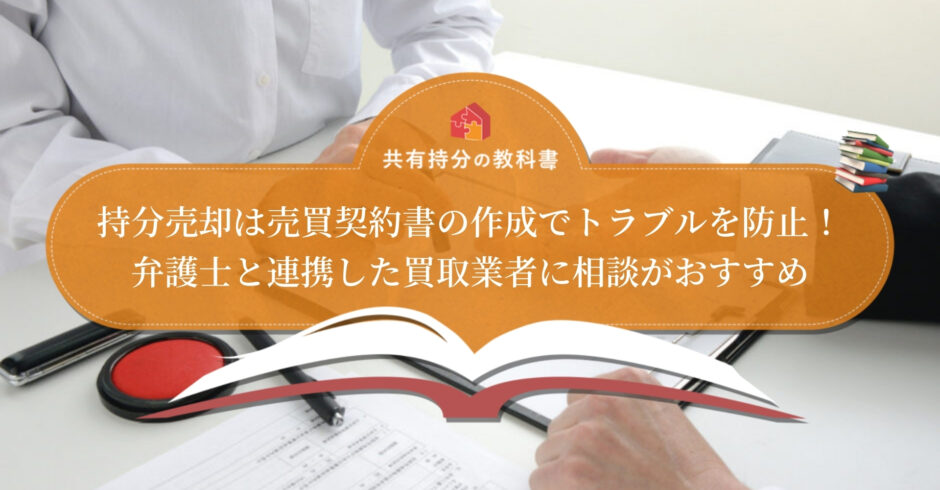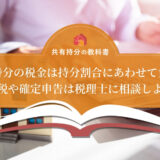共有持分の売却時には、売買契約書を作成するのが一般的です。
売買契約書には、物件に関する情報や売買代金の他、引渡し日や契約違反時の対応など、売主と買主が合意した取引内容を事細かに記載する必要があります。
売買契約書の作成は義務ではありませんが、トラブルを防ぐためにも必ず作成しておきましょう。
個人間での売買なら弁護士に作成を代行してもらい、不動産業者との売買なら業者側が作成するのが一般的です。
どちらの場合も、規約内容が自分の認識とずれていないかしっかりと確認することが大切です。弁護士と連携している共有持分の買取業者なら法律的に間違いのない売買契約書を作成してもらえるので、安心して任せられます。
>>【弁護士と連携した買取業者】共有持分の買取査定窓口はこちら

- 売買契約書とは「売主」と「買主」で不動産の売買契約を締結するときに必要な書類。
- 売買契約書を紛失してしまったときの対処法は「代替書類を集める」or「不動産会社や取引相手に再発行依頼する」。
- 当事者間での売買契約書の作成は認められているが、リスクが高いため弁護士に作成を依頼したほうがよい。
売買契約書とは「売主」と「買主」で売買契約を締結するときに必要な書類のこと
売買契約書とは「売主」と「買主」で売買契約を締結するときに必要な書類のことです。
売買する際に、さまざまな約束事やルールを当事者間で決めることを「売買契約」といいます。
その売買契約で決められた、権利関係や結果などを書類にしたものが「売買契約書」です。
売買契約書自体に作成義務はないが契約内容や権利関係を明確化するため作成される
じつは、売買契約書自体には作成義務がなく、法律上では口約束だけでの売買契約も認められています。
しかし、不動産の売買には高額な金銭のやり取りが発生するので、権利関係を明確にしておくことが重要です。
もしも、売買契約書なしで不動産の売買をしたとすると、権利関係や金銭問題によるトラブルが起きてしまうでしょう。
売買契約書は2通作成し「売主」と「買主」それぞれが保管するケースが多い
不動産を売買するときは「売主」と「買主」が存在します。
ですので、売買契約書の原本を2通作成し、それぞれが保管するケースが多いです。
また、売買契約書の原本を1通だけ作成し、コピーをとって保管することも法的には可能です。
しかし、後々にトラブルや紛争が起きる可能性もあるので、売買契約書の原本を2通作成しそれぞれ保管することが無難な選択だといえるでしょう。
売買契約書は不動産会社や仲介業者が作成する
不動産会社や仲介業者を介して不動産を売買するとき、売買契約書はその業者が作成します。
というのも「宅地建物取引業法」という法律で、不動産会社は売買契約書を作成するよう義務付けられているからです。
ですので、不動産会社や仲介業者を介して不動産を売買するときは、不動産会社が売買契約書を作成してくれます。
宅地建物取引業法第37条
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し(中略)契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく(中略)書面を交付しなければならない
引用:e-Govポータル「宅地建物取引業法第37条」
業者を介さず個人間で売買する場合は双方で話し合って用意する
前の項目で、不動産業者を介して売買するときは、不動産会社が売買契約書を作成することを説明しました。
しかし、不動産業者を介さず個人間で不動産を売買するときは、双方で話し合って売買契約書を用意する必要があります。
なぜなら民法には「契約自由の原則」があるため、売主・買主どちらにも作成義務はないからです。
ですので、個人間で不動産を売買するときは、双方の納得が得られる方法で売買契約書を用意しましょう。
1 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
引用:e-Govポータル「民法第522条」
売買契約時には「重要事項説明書」もあわせて作成される
不動産業者を利用し、売買契約を結ぶ際には「重要事項説明」がおこなわれます。
重要事項説明とは、宅地建物取引業法によって定められた手続きで、買主に対して「不動産に関する法令上の制限」や「契約に関する事項」などが説明されます。
この重要事項説明は、不動産業者を介して売買するときには必ずおこなわれます。
また、重要事項説明の内容を書類にしたものが「重要事項説明書」です。
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買(中略)の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に(中略)書面(中略)を交付して説明をさせなければならない。
引用:e-Govポータル「宅地建物取引業法第35条」
重要事項説明書の作成は宅地建物取引士がおこなう
重要事項の説明及び、重要事項説明書の作成は「宅地建物取引士」によってのみ、執りおこなわれます。
ですので、個人間での不動産売買をおこなう場合、重要事項説明書は作成できません。
もしも、買主が住宅ローンを組む場合、重要事項説明書は必須になるので個人間売買をする際には十分に注意しましょう。
共有不動産を売却するときの売買契約書には共有者全員の署名捺印が必要
共有不動産を売却する場合、売買契約書には共有者全員の署名捺印が必要です。
なぜなら、法律によって「共有不動産の売却には所有者全員の同意が必要」と定められているからです。
また、共有不動産の売却に共有者全員が同意していたとしても、共有者全員が一堂に会することは難しいかもしれません。
そのような場合は代理人を設定し、委任状を作成するとよいでしょう。
売買契約書は不動産売却時の確定申告に用いられる
不動産売却をして利益を得た場合「課税譲渡所得金額」を計算し、確定申告する必要があります。
不動産売却時の課税譲渡所得金額は以下の式とリストで計算できます。
| 取得費 | 売却する不動産を購入したときの代金 |
|---|---|
| 譲渡費用 | 仲介手数料や測量費など不動産売却にかかった諸費用 |
| 譲渡金額 | 売却によって手にした金額 |
上記の表の「取得費」に、売買契約書に記載されている「不動産購入代金」が入ります。
売買契約書がなくても確定申告できるが通常より多くの納税が必要
確定申告時に「売買契約書がない」つまり、取得費が不明だった場合「不動産購入代金」の代わりに「売却価格の5%」が代入されます。
例えば、5,000万円で購入した不動産を、譲渡費用100万円かけて、4,000万円で売却したとすると
です。
この場合は「損失」となるため課税はされません。
しかし、取得費が不明だとして「不動産購入代金」の代わりに「売却価格の5%」の「250万円」で計算すると
です。
この場合、不動産売却によって取得があったとみなされ、納税が義務付けられてしまいます。
このように、売買契約書がなくても確定申告はできますが、確定申告で損をしてしまう可能性が高いです。
売買契約書を紛失してしまったときの対処法
売買契約書は重要な書類ですが、紛失してしまうかもしれません。
もしも、不動産の売却を考えているのに、売買契約書が見当たらなかったらどのように対処するべきか次の項目から解説します。
代替書類を集める
不動産売却の際「取得費」を計算するために売買契約書は必要です。
しかし、状況によっては売買契約書がなくても代替書類で確定申告がおこなえるケースもあります。
代替書類として認められる可能性のある書類を以下のリストにまとめました。
- 不動産購入時の領収書
- 不動産購入時のチラシ
- 仲介業者の計算明細書
- 通帳の振込記録
- 抵当権設定登記の債権額
- 住宅ローンの返済予定表
不動産売却を考えている際に、売買契約書が見当たらなかった場合、これらの書類をもとに確定申告がおこなえる可能性があります。
不動産会社や取引相手と連絡して「再発行」or「コピーをもらう」
売買契約書を紛失した場合、売買した不動産会社や取引相手に連絡をとることが重要です。
売買契約書の再発行には、買主・仲介業者によって書類を再確認した上で、署名捺印が必要です。
また、売買契約書のコピーをもらう方法もあります。
不動産会社は、最低5年は売買契約書を保管する義務があるので、不動産会社に依頼すればコピーをもらえるかもしれません。
ですので、売買契約書の紛失に気づいたら、早めに不動産会社や取引相手に連絡をするとよいでしょう。
個人間で売買する際の売買契約書の記載内容と作成依頼先
不動産を個人間で売買するときは、売買契約書をどのように用意するか当事者間で決める必要があります。
また、売買契約書は当事者間でも作成できます。
なお「重要事項説明書」は宅地建物取引士でないと作成できないため、個人間の売買には注意が必要です。
決まった書式はないが記載すべき内容はきまっている
売買契約書には決まった書式はありませんが、記載すべき内容は決まっています。
以下のリストは、売買契約に記載すべき内容の一例です。
- 売買物件の表示
- 売買代金・手付金等の額・支払日
- 所有権の移転と引き渡し
- 負担の削除
- 付帯設備等の引き継ぎ
- 手付解除
- 引き渡し前の物件の滅失および毀損
- 契約違反による解除
- 瑕疵担保責任
- ローン特約
- 反社会的勢力の排除
- 特約事項
しかし、必ずしも「このリスト通りに書けば問題は絶対発生しない」わけではなく、不動産の状況や、売買契約の内容などによって記載内容が変わりますので、売買契約者本人による作成はおすすめできません。
売買契約書の作成は記載事項が多く内容も複雑なため弁護士に依頼すべき
法的には、売買契約書の作成は当事者でもできます。
しかし、実際に作成しようとすると、記載事項や記載内容は状況に応じて書き換える必要があるため、当事者による売買契約書の作成は大変困難です。
また、個人間の売買ということは取引相手が必ず存在します。
万が一、書類の作成で不備があれば、取引相手とトラブルの原因になってしまいます。
このような理由から、売買契約書の作成は弁護士に依頼するべきです。
弁護士に依頼する場合の相場は「3万円から10万円」
売買契約書作成の弁護士報酬の相場は「3万円から10万円」といわれています。
しかし、売買する不動産の状況や依頼する法律事務所、地域などによって大きく相場は変動します。
ですので、実際に依頼する場合は、いくつかの法律事務所に見積り依頼するとよいでしょう。
また、弁護士報酬は「売主」と「買主」で折半して支払うのが一般的です。
売買契約書に作成義務はないが契約内容や権利を明確にするため作成しよう
売買契約書に作成義務はありませんが、契約内容や権利を明確にするため作成されるケースがほとんどです。
また、不動産会社を介して売買する場合、売買契約書は不動産会社が確実に作成してくれます。
しかし、個人間で不動産売買するときは、双方の納得のいく方法で売買契約書を用意する必要があります。
売買契約書は専門家でなくても作成できますが、難易度が高く不備があるとトラブルの原因にもなってしまいます。
トラブルを避けて不動産売買を円滑に進めるためにも、売買契約書の作成は弁護士に依頼すべきでしょう。
共有持分の売買についてよくある質問
共有持分とは、複数人が共有する不動産において「各共有者がどれくらいの所有権をもっているか」を指すものです。「持分1/2」というように、割合で表記します。
はい、売却できます。自分の共有持分であれば自分の意思のみで売却可能で、他共有者に確認を取る必要もありません。ただし、共有不動産全体を売却したいときは、全共有者の同意が必要です。
共有持分の取り扱いに不慣れな大手不動産会社より、共有持分を専門としている買取業者のほうが高額で買い取ってもらえるでしょう。また、離婚協議などでトラブルになっている場合は、弁護士と連携している専門買取業者に相談するのがおすすめです。→弁護士と連携した買取業者はこちら
共有持分の売買価格は、本来の価値から半額程度になるのが一般的です。ただし、売却相手や物件ごとの条件によっては高額になる場合もあり、すべての状況に共通する価格相場が決まっているわけではありません。
不動産会社を利用して売却する場合は、依頼した不動産会社が準備してくれます。個人間売買の場合は当事者(主に売主)が作成しますが、弁護士や司法書士など、法律の専門家に作成のみ代行してもらうこともあります。