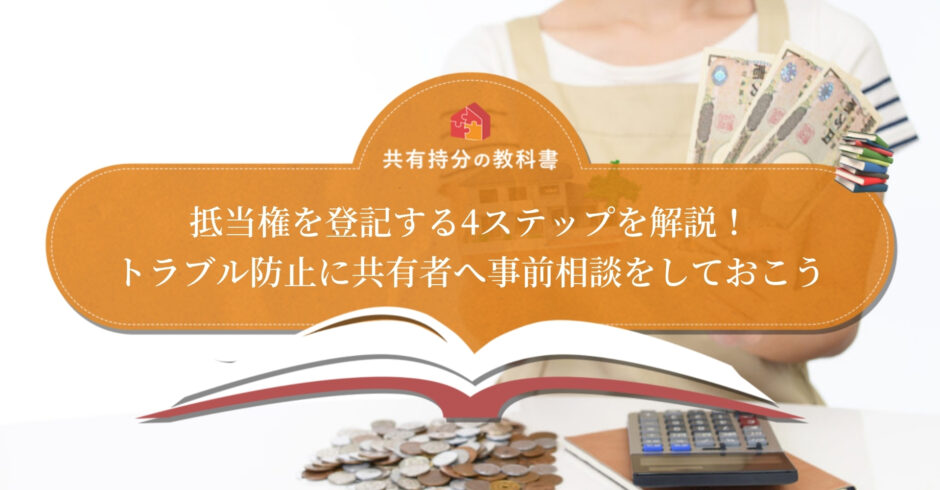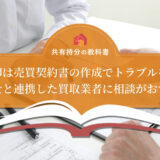住宅ローンを借り入れるときなど、不動産に抵当権を設定する場合があります。
抵当権とは、返済滞納があったときに対象の不動産を差し押さえる権利です。金融機関は高額の金銭を融資する場合、抵当権の設定を条件にすることがほとんどです。
共有不動産において、自分の共有持分だけに抵当権を設定することもできます。
「共有持分への抵当権設定」に他共有者の同意はいりませんが、トラブルを防ぐためには事前相談をしておくとよいでしょう。
抵当権の設定には、法務局での登記手続きが必要です。自分で申請することも可能ですが、ミスなくスムーズに申請するためには司法書士に依頼するのがおすすめです。

- 抵当権設定登記は自分でもできるが、ミスしたときのリスクが大きいため司法書士に依頼しよう。
- 他共有者の同意がなくても共有持分に抵当権を設定できるが、トラブルのもとになるので事前に相談すべき。
- 共有持分の抵当権が実行されると不動産を失ってしまう可能性もある。
抵当権とは「債権者が融資する際」に「債務者の不動産を担保に設定」できる権利のこと
抵当権とは「債権者が融資する際」に「債務者の不動産を担保に設定」できる権利のことです。
債権者とはお金を貸す側、債務者とはお金を借りる側のことをいいます。
債権者は住宅ローンや融資の返済が滞ったときのために、債務者の不動産を担保として設定できます。
もしも、返済が滞り抵当権が実行されてしまうと、不動産が差し押さえられる恐れがあります。
ちなみに、住宅ローン融資の条件として抵当権の設定が求められる場合が多いです。
抵当権設定登記とは抵当権の設定を明確にする登記のこと
抵当権設定登記とは抵当権の設定を明確にする登記のことをいいます。
抵当権設定登記をおこなわないと、債権者は不動産を担保にしている事実を証明できないため、抵当権を実行できません。
ですので、抵当権設定登記は融資の際に必ずおこなわれます。
また、抵当権設定登記は債務者と債権者の間で融資があったその日に登記されます。
不動産の一部や持分の一部だけには抵当権を設定できない
不動産の共有持分に抵当権設定できますが「不動産の一部」や「持分の一部」には抵当権を設定できません。
なぜなら「不動産のどこの部分」に抵当権が設定されたか特定ができないからです。
ですので、共有持分に対する抵当権設定は認められていますが「不動産の一部」や「持分の一部」に対する抵当権は設定できません。
同じように、共有持分においても「自分のもつ共有持分のうち半分だけに抵当権を設定する」ということはできず、対象の共有持分全体に抵当権が設定されます。
共有持分に抵当権が設定されるのは「持分を担保にして融資を受けた場合」や「共有名義で住宅ローンを利用した場合」
共有持分に対して、抵当権が設定される主な理由としては「持分を担保にして融資を受けた場合」や「共有名義で住宅ローンを利用した場合」があげられます。
共有持分を担保にして融資を受ける場合、その共有持分が抵当権に設定されるのは当然だといえるでしょう。
また、不動産購入時に共有名義で住宅ローンを利用した場合も、共有持分に抵当権設定される場合があります。
例えば、夫婦で家を購入するとき妻と夫それぞれが住宅ローンを利用する「ペアローン」では共有持分が発生し、それぞれの共有持分に抵当権が設定されます。
「共有持分への抵当権設定」に他共有者の同意は不要だが事前相談はすべき
不動産全体の権利を所有していなくても、共有不動産の一部の権利を所有していれば、その共有持分を担保に融資を受けられます。
また、自らの共有持分を抵当権設定する場合、他共有者の許可や同意も必要ありません。
しかし、融資返済が滞り抵当権が実行されてしまうと、共有不動産が競売されてしまう可能性があり、他共有者にも影響がでるので事前に相談すべきでしょう。
「共有持分の抵当権」が実行されると不動産全体を失ってしまう可能性がある
もしも、他共有者の共有持分に設定されている抵当権が実行されてしまうと、その共有持分は競売にかけられてしまいます。
他共有者の共有持分が競売にかけられたからといって、すぐに共有不動産を明け渡さなければならないとは限りませんが、なんらかの対処は必要です。
最悪の場合、共有不動産そのものを失ってしまう可能性もあります。
共有持分が競売にかけられたときの対処法は以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
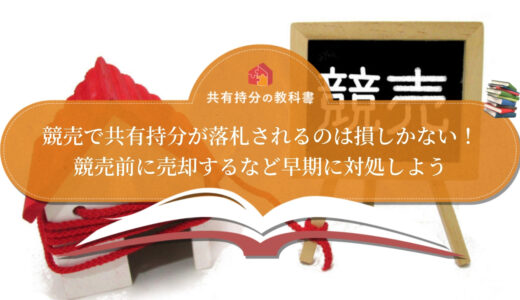 他共有者の共有持分が「競売となったとき」の5つの解決法|競売に陥る前にできることも解説します
他共有者の共有持分が「競売となったとき」の5つの解決法|競売に陥る前にできることも解説します
抵当権設定登記は司法書士に依頼するのが一般的
抵当権設定登記は司法書士がおこなうケースがほとんどですが、法律的には債務者でも登記申請は可能です。
しかし、抵当権設定登記は司法書士に依頼したほうがよいでしょう。
なぜなら、抵当権設定登記は債務者だけでおこなうのではなく、債権者も関係しているからです。
もしも、債務者が登記申請をおこなってミスがあった場合、債権者から多額の損害賠償を請求される恐れがあります。
なお、債権者が紹介する司法書士に依頼するケースもあります。ただし、料金が法外に高くないかなど、信用できる司法書士であるかは確認しておきましょう。
抵当権設定登記に必要な書類は「印鑑証明書」「抵当権設定契約証書」「本人確認書類」
この項目では、抵当権設定登記に必要な書類を解説していきます。
法務局などで取得できる書類のほかに、本人確認書類なども用意する必要があります。
もしも、書類について不明点があれば司法書士や債権者にたずねるとよいでしょう。
印鑑証明書は3カ月以内に発行されたものを使用する
債務者本人が設定登記に応じたことを確かにするため、発行から3カ月以内の印鑑証明書が必要です。
印鑑証明書は役所の窓口でも取得できますが、マイナンバーカードがあればコンビニで取得できる場合もあります。
以下のリンクから、コンビニ交付が対応している市区町村や印鑑証明書の取得方法などを調べられます。
参照:コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付「コンビニ交付」
抵当権設定契約証書は債権者が用意する
抵当権設定契約証書とは、抵当権に設定される不動産が債権者の担保になっている事実を表す契約書のことです。
抵当権設定契約証書は債権者が用意してくれるので、債権者の指示通りに必要事項の記入をしましょう。
本人確認書類は運転免許証や健康保険証などが使える
抵当権設定登記に利用される本人確認書類は「運転免許証・健康保険証」などです。
普段から本人確認書類を携帯していない人は、設定登記をおこなう際は忘れずに用意しましょう。
抵当権設定登記の流れは4ステップ
抵当権設定登記は債務者だけではおこなわず、債権者と協力しながら手続きを進めます。
抵当権設定登記の流れは、次の4ステップにわかれます。
- 債権者と金銭消費貸借契約を結ぶ
- 金銭消費貸借契約をもとに抵当権設定契約を結ぶ
- 書類を提出し法務局で登記申請をおこなう
- 法務局で登記事項証明書を取得し債権者に提出する
次の項目から、具体的な抵当権設定登記の流れを解説していきます。
ステップ1 債権者と金銭消費貸借契約を結ぶ
抵当権を設定する前に、金銭消費貸借契約を結ぶ必要があります。
金銭消費貸借契約とは融資を受けた債務者が、将来的に一定の利息を付けて債権者に返済する契約のことです。
また、簡略化して「住宅ローン契約」と呼ばれるケースもあります。
抵当権は金銭の融資をする契約ではないので、抵当権を結ぶ前提として金銭消費貸借契約を結びます。
ステップ2 金銭消費貸借契約をもとに抵当権設定契約を結ぶ
ステップ1で説明した金銭消費貸借契約をもとに抵当権設定契約を結びます。
このステップで抵当権設定契約書を作成するケースがほとんどです。
契約書をよく読んで、契約内容をしっかりと把握することが重要です。
ステップ3 書類を提出し法務局で登記申請をおこなう
「抵当権設定契約証書」や「発行から3カ月以内の印鑑証明書」「本人確認書類」を法務局に提出し登記申請をします。
登記申請には窓口申請や郵送申請、オンライン申請があります。
ステップ4 法務局で登記事項証明書を取得し債権者に提出する
ステップ3までの手続きが完了したら、抵当権設定登記の完了を証明するために、登記事項証明書を取得し債権者に提出します。
登記事項証明書とはデータ化された登記簿の内容を専用の用紙に印刷したものです。
登記事項証明書は法務局の窓口でも請求できますが、簡単なパソコン操作だけで取得できるオンライン申請がおすすめです。
法務局のホームページからオンライン申請できます。
参照:法務局ホームページ「登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です」
抵当権設定登記にかかる費用は「登録免許税+司法書士報酬」
抵当権設定登記の手続きにかかる費用は「登録免許税+司法書士報酬」です。
登録免許税とは、登記手続きの際にかかる税金のことです。
登録免許税は
例えば、1,000万円の融資を受ける場合の登録免許税は
特定の条件を満たした住宅ローンであれば「×0.1%」になる
住宅ローンを受ける際に「登録免許税の税率の軽減措置」が適用される場合があります。
この軽減措置が適用される住宅の登録免許税は「×0.4%」ではなく「×0.1%」で求められます。
また、この登録免許税軽減措置は住宅にしか適用されないので、土地もあわせて購入するときは注意が必要です。
ちなみに、この軽減措置は2021年3月現在、2022年3月31日までが適用期間となっています。
司法書士報酬の相場は「5万円から10万円」程度
抵当権設定登記の司法書士報酬は「5万円から10万円」といわれています。
しかし、融資を受ける金額や依頼する司法書士事務所、地域などによって大きく相場は変動します。
ですので、実際に依頼する場合は、いくつかの司法書士事務所に見積り依頼をするとよいでしょう。
司法書士報酬の他に書類取得費用が必要
司法書士に依頼する場合、司法書士報酬とは別に実費を支払います。
印鑑証明書などの書類取得費用や、場合にとっては交通費や出張費も実費に含まれます。
司法書士に依頼する場合は、書類取得の諸費用についても相談しておきましょう。
抵当権設定登記は司法書士に依頼するのがよい
共有持分に抵当権を設定できますが、融資返済が滞ってしまうとトラブルになりかねないので、事前に他共有者と相談してから設定するのが重要だといえます。
また、法的には債務者本人でも抵当権設定登記はおこなえますが、ミスをしたときのリスクが非常に大きいため司法書士に依頼すべきでしょう。
抵当権設定を依頼する場合は、いくつかの司法書士事務所に見積り依頼し、一番信頼のできる司法書士事務所に依頼しましょう。
共有持分の抵当権設定登記についてよくある質問
共有持分とは、複数人が共有する不動産において「各共有者がどれくらいの所有権をもっているか」を指すものです。「持分1/2」というように、割合で表記します。
不動産に抵当権を設定したことを、登記簿に記載する手続きです。登記簿に記載することで、抵当権を第三者に主張できます。
抵当権とは、借入金の返済が滞ったとき、金融機関が不動産を差し押さえられるようにする権利です。抵当権を設定することで金融機関は貸し倒れのリスクを軽減します。
はい、できます。共有持分を担保に融資を受ければ、共有持分に抵当権を設定することになります。
当事者である債権者と債務者(共有持分の名義人)が申請します。ただし、一般的には双方から依頼を受けた行政書士が手続きをおこないます。