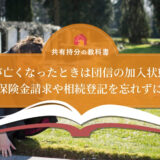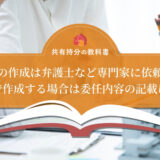離婚時に「共有名義の住宅ローンはどうなるのか?」と悩んでいる方は多いのではないでしょうか。結論からいうと、夫婦のうちどちらかが家に住み続けるのか、それとも双方ともに住む予定がないのかによって対処法は異なります。
それぞれのパターンで共有名義の家や住宅ローンがどうなるのかを、まずは表で整理しました。
| 状況 | 主な対処法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 一方が家に住み続ける | ・ローンを借り換えて単独名義に変更する ・一括返済する ・債務引受 |
・ローンを借り換える場合は、新規借入時と同様に厳しく審査される ・一括返済するにはまとまったお金が必要 ・基本的には認められない |
| 双方とも住まない | 家を売却してローン返済に充てる | ・アンダーローンなら完済可能 ・オーバーローンなら任意売却や資金補填が必要 |
もちろん「共有名義のままにしておく」という選択肢もありますが、実際には以下のようなトラブルが多く発生するため、おすすめできません。
- 家の管理や売却をめぐって元配偶者と意見が対立する
- 相手が住宅ローンを滞納した場合に一括返済を求められる
- 将来的に相続で共有者が増え、権利関係が複雑化する
こうしたリスクを避けるためにも、離婚時には共有状態を解消しておくことが大切です。本記事では離婚時の共有名義の住宅ローンについて、「住み続ける場合」「売却する場合」に分けて詳しく解説するとともに、共有名義を放置するリスクなども解説します。
クランピーリアルエステートでは、全国1,500以上の士業と連携しているため、法的なサポートが必要となる複雑なケースにもワンストップで対応可能です。離婚をきっかけに共有名義の不動産をどうすべきか悩んでいる方は、ぜひ一度ご相談ください。
離婚後も共有名義は可能だが、トラブルの原因になるため避けるべき
夫婦で借り入れた住宅ローンや共有名義の家は、離婚後も共有名義のままにしておけます。しかし、住宅ローンや家を共有名義のままにしておくと、下記のようにさまざまなトラブルを引き起こす火種になりかねないため、共有名義のまま放置するのはおすすめしません。
- 家の管理や売却を巡って元配偶者と意見が対立する
- 元配偶者が住宅ローンを返済できなくなった場合に肩代わりさせられる
- 将来的に相続で新たな共有者が増えて権利関係がさらに複雑化する
せっかく離婚で人生をリスタートしても、共有名義の住宅ローンや家が残っていると元配偶者との縁を断ち切れず、常にトラブルの火種を抱えることになります。その結果、金銭面だけでなく精神面でも大きな負担を背負うことになるでしょう。
そのため、夫婦の共有名義の住宅ローンや家は、離婚時に住宅ローンや家を単独名義に変更したり、家の売却益で住宅ローンを完済したりなどの方法で、共有状態を解消するべきです。
離婚後もどちらかが家に住み続ける場合
離婚後もどちらかが家に住み続ける場合は、住宅ローンや家の名義人を家に住み続ける方の単独名義に変更し、共有状態を解消するのが得策です。単独名義に変更すれば、共有名義のままにしておくことで起こり得るトラブルを未然に防げます。
離婚後もどちらかが家に住み続ける場合の対処法としては、以下の4つが挙げられます。
- 住み続ける方の単独名義でローンを借り換える
- 住宅ローンを一括返済する
- 引き続き共有名義のままで支払い続ける
- 「債務引受」によって住み続ける方がローンを肩代わりする
ここからは、それぞれの方法について1つずつ詳しく解説していきます。
住み続ける方の単独名義でローンを借り換える
離婚後もどちらかが家に住み続ける場合は、住み続ける方が単独名義で住宅ローンを借り換える方法が最も現実的でおすすめの解決策です。住宅ローンの借り換えによって、家から離れる方は家の所有権やローンの返済義務から完全に開放されるため、共有名義のままにしておくことで起こり得るトラブルを未然に防げます。
家に住み続ける方も、住宅ローンの残債を返済する代わりに、元配偶者の同意なしで不動産を自由に活用・売却できます。ただし、住宅ローンの借り換えでは、新規借入時と同様に契約者の収入状況や信用情報などが厳しくチェックされます。
そのため、住み続ける方の収入が少ない場合や信用情報に傷が付いている場合は審査に通らない可能性があることも頭に入れておきましょう。
住宅ローンを一括返済する
住宅ローンの残債が少ない場合は、住宅ローンを一括返済するという方法も選択肢の1つです。住宅ローンを一括返済すれば、金融機関とのローン契約が終了し、不動産に設定されていた抵当権が抹消されます。
抵当権とは、住宅ローンなどの借入れをしたときに、金融機関が貸したお金を確実に回収するために不動産に設定する担保権のことです。もし返済ができなくなった場合、金融機関は抵当権を使ってその不動産を競売にかけ、売却代金から貸したお金を回収します。
ローンを全額返済して抵当権が抹消されれば、名義人の変更も金融機関の承諾なしで自由に行えるようになるため、共有名義から単独名義への変更もスムーズに進められます。
また、一括返済すると、残りの返済期間内に支払う予定だった利息がすべてなくなるため、返済総額を大幅に減額できるのもメリットです。しかし、住宅ローンの一括返済には多額のまとまった資金が必要になります。
無理をして一括返済をすると急な出費に対応できないリスクがあるため、一括返済後にいくら残るのか、今後の生活に影響がないか考慮して慎重に判断することが大切です。
引き続き共有名義のままで支払い続ける
離婚後も共有名義を解消せず、引き続き住宅ローンの返済を続けるという選択肢もあります。しかし、共有名義のままでは不動産を自由に活用・売却することはできません。そのため、家に住み続ける方は活用・売却の同意を得るために元配偶者と話し合いをしたり、連絡をやり取りしたりする必要があります。
ほかにも、不動産を共有名義にしておくことには、前述したようにさまざまなリスクが伴うため、あまりおすすめはできません。
- 住宅ローンを元配偶者が滞納し続けた場合は、残債の一括返済を求められる可能性がある
- 維持費の支払いを巡ってトラブルになる恐れがある
離婚後のトラブルを防ぐためにも、共有名義の住宅ローンや不動産は単独名義に変更しておくのが望ましいです。
「債務引受」によって住み続ける方がローンを肩代わりする
債務引受とは、住宅ローンの返済義務を第三者が債務者の代わりに引き受けることです。家に住み続ける方が住宅ローンの返済を引き受け、不動産も単独名義に変更することで共有名義を解消できます。
債務引受で共有状態を解消するには、金融機関に相談して所定の審査に通過する必要があります。しかし、債務引受は金融機関にとってのリスクが大きいことから、離婚のみを理由とした債務引受はほとんど認められないのが実情です。そのため、あまり現実的な方法ではないといえるでしょう。
共有名義ローンの家を売却する場合
離婚後に共有名義の住宅ローンの家に誰も住まないのであれば、家を売却して住宅ローンの返済に充てるのが賢明な選択肢です。住宅ローンが残っていても家の売却は可能ですが、抵当権を設定している金融機関の同意を得て抵当権を抹消する必要があります。
また、売却の流れは家の売却益で住宅ローンを完済できるか否かで異なります。家の売却を検討する際は不動産会社で売却価格を査定してもらい、金融機関で住宅ローンの残債を確認して完済できるか否か確認しておくことが大切です。
家の売却益でローンを完済できるケース
家の売却価格が住宅ローンの残債を上回る、いわゆる「アンダーローン」の状態であれば、家の売却益で住宅ローンを完済できます。アンダーローンの場合は、家の売却と同時に住宅ローンを完済できるため、金融機関から抵当権抹消の同意を得るのが容易で、通常の不動産売却と同じ手続きで進めることが可能です。
また、アンダーローンの状態であれば、住宅ローンを完済した後も手元に現金が残るため、財産分与の話し合いもスムーズに進むことが多いです。
・家の売却価格が3,000万円
・住宅ローンの残債が1,600万円
3,000万円-1,600万円=1,400万円
手元に残った1,400万円を700万円ずつ2人で分け合う
家の売却益でもローンが完済できないケース
家の売却価格がローンの残債を下回る、いわゆる「オーバーローン」の状態であれば、家の売却益でも住宅ローンを完済できません。住宅ローンを完済できない場合、金融機関が抵当権を抹消することを認めることは原則ありません。
そのため、夫婦間で売却に合意したとしても、それだけでは自由に家を売却できないのが基本です。オーバーローンの状態で家を売却したい場合は、以下のような方法で対処する必要があります。
- 不足分を自己資金や親族からの援助で補填する
- 金融機関と交渉して家を任意売却する
家の売却代金に自己資金や親族からの援助を上乗せすることで住宅ローンを完済できる場合は、金融機関が抵当権の抹消に応じてくれる可能性があります。そのため、通常の不動産売却と同じ流れで手続きを進めることが可能です。
一方で自己資金や親族からの援助で補填するのが難しい場合は、金融機関と交渉して任意売却を検討します。任意売却とは、住宅ローンを滞納して残債を完済できない場合に、金融機関(債権者)の同意を得て家を売却する方法です。
任意売却の許可が下りれば、金融機関が抵当権の抹消に同意してくれるので売却が可能になります。ただし、金融機関の同意を得るのはそう簡単なことではありません。
特に、売却価格とローンの残債の差額が大きい場合、金融機関は任意売却に難色を示すケースが多いです。仮に任意売却が認められたとしても、売却益で返済しきれなかった住宅ローンは引き続き返済をしていかなければならないため、完済するまで双方に返済義務が生じます。
・家の売却価格が2,000万円
・住宅ローンの残債が3,000万円
2,000万円-3,000万円=-1,000万円
任意売却後の残債1,000万円を引き続き返済する
離婚後も住宅ローンを共有名義のままにしておくリスク
離婚後も住宅ローンは共有名義のままにしておけますが、以下のようなリスクが残ります。
- 自由に売却や貸出、リフォームなどができない
- 相手がローンを滞納すると一括返済を求められる可能性がある
- 不動産の維持費がかかり続ける
- 離婚してもお互いの関係が切れない
- 共有者が増えて権利関係が複雑になる可能性がある
ここからは、それぞれのリスクについて1つずつ詳しく解説していきます。
自由に売却や貸出、リフォームなどができない
離婚後も住宅ローンを共有名義にしたままでは、不動産の売却・貸出・リフォームなどが自由に行えません。共有名義の不動産は各共有者が持分に応じた所有権や不動産全体の使用権を持っているため、不動産に対して単独でできる行為は法律で制限されています。
民法上、共有物に対する行為はその性質に応じて「保存行為」「管理行為」「変更行為」の3つに分類されています。
| 共有物に対する行為の種類 | 内容 | 具体例 | 他の共有者の同意の要件 |
|---|---|---|---|
| 保存行為 | 共有物の現状を維持するための行為 | ・雨漏りの修繕 ・屋根や壁などの破損箇所の修繕 ・不法占拠者に対する建物の明け渡し請求 |
各共有者が単独で実行可能 |
| 管理行為 | 共有物の性質を変えない範囲内で、その利用や改良を目的とする行為 | ・短期の賃貸借契約の締結・更新・解除 ・賃料の請求・回収 ・給湯器やエアコンの交換 |
持分価格の過半数の同意が必要 |
| 変更行為 (軽微な変更) |
形状(外観、構造等)や効用(機能や用途など)の著しい変更を伴わない行為 | ・間取りの変更を伴わない内装のリフォーム ・外壁の塗り替え ・砂利道からアスファルト舗装への変更 ・土地の分筆・合筆 |
持分価格の過半数の同意が必要 |
| 変更行為 (軽微な変更以外) |
形状(外観や構造など)や効用(機能や用途など)を変更する行為 | ・不動産全体の売却 ・建物の解体 ・増築・減築・改築 ・大規模なリフォーム ・不動産全体に抵当権を設定 ・長期の賃貸借契約の締結・更新・解除 |
共有者全員の同意が必要 |
保存行為は単独で実行できますが、管理行為や変更行為は他の共有者の同意が必要になります。離婚後も共有名義のままにしておくと、不動産の活用や売却を行う際に元配偶者からの同意を得なければなりません。
元配偶者と連絡が取れなかったり意見が対立したりすると、不動産の活用や売却が難航してしまいます。結果、有効活用できないまま維持費だけがかかり続ける「負の財産」と化してしまうリスクもあるのです。
それを避けるためにも、離婚時は家に住み続ける方が不動産を単独で所有し、不動産を自由に利用できるようにしておきましょう。
相手がローンを滞納すると一括返済を求められる可能性がある
夫婦共有名義の住宅ローンは、夫婦双方が連帯して全額を返済する義務を負っています。もし一方がローンを滞納した場合、金融機関は契約に基づき、もう一方にローンの一括返済を求めることができます。
金融機関から一括請求された場合、基本的には拒否できません。そのため、一括請求された場合はそれに従って返済する義務が生じます。たとえ離婚時の話し合いで「相手が住宅ローンを全額支払う」と約束していたとしても、それは夫婦間での取り決めに過ぎません。
金融機関とのローン契約には効力が及ばないため、法的な返済義務は双方に残ります。もし、一括請求に応じられなければ、金融機関は抵当権を行使して不動産を競売にかける可能性があります。
競売にかけられると、市場価格よりも大幅に安い価格で売却されるため、残った売却代金でローンを完済できないことが少なくありません。さらに、売却手続きや引っ越し時期を自分で決められないため、離婚後も住み続ける予定であった場合も強制的に退去しなければならないデメリットもあります。
また、競売で得られた代金を充てても住宅ローンの残債に足りない場合、その不足分は前述したように引き続き返済しなければなりません。つまり、家を失ったうえに借金だけが残る可能性があるのです。
共有名義を続ける限り、完済まで上記のようなリスクがつきまといます。こうした事態を防ぐためにも、離婚時に住宅ローンの共有状態を解消し、家を売却して完済するか、住み続ける人の単独名義に変更しておくことが重要です。
不動産の維持費がかかり続ける
住宅ローンが共有名義のままでは、不動産も共有名義のままになります。共有名義の不動産にかかる管理費や修繕費、固定資産税などの費用は、共有者全員が自身の持分割合に応じて負担する義務があるため、離婚後もこれらの費用の負担が継続します。
たとえ離婚時の話し合いで「相手が不動産の維持費を全額負担する」と約束していたとしても、法的な支払い義務は消滅しません。離婚後に家から離れる方からすれば、住んでいない家の維持費を負担し続けることは金銭的・精神的に大きな負担となります。
それを避けるためには、離婚時に住宅ローンの共有名義を解消し、不動産を離婚後も引き続き住み続ける方の単独名義に変更しておきましょう。そうすることで、家から離れる方は不動産の所有権を完全に手放せるため、維持費の負担からも解放されます。
離婚してもお互いの関係が切れない
前述の通り、共有名義の不動産の管理や処分には他の共有者の同意が必要で、維持費も共有者全員に支払い義務が生じます。そのため、離婚後もこれらに関する連絡のやり取りや話し合いの必要性が出てきます。
離婚後もお互いの関係が切れないのは、精神的に大きな負担と感じる人も少なくありません。実際に弊社にも、離婚後も共有名義の不動産関連で元配偶者と連絡を取り合うのがストレスになり、売却のご相談をいただく事例も多数ございます。
お互いにスッキリとした気持ちで新たなスタートを切るためにも、住宅ローンと不動産は単独名義に変更しておくべきでしょう。
共有者が増えて権利関係が複雑になる可能性がある
共有者が亡くなった場合、その相続人が新たな共有者になります。相続人が複数いる場合は全員が共有者になるため、権利関係がさらに複雑になってしまうのです。
権利関係が複雑になると、不動産の管理や処分についての意見をまとめるのが難しく、共有者間でトラブルが生じる可能性が高まります。結果的に、不動産を有効活用できないまま維持費だけが発生し続ける「負の遺産」と化してしまいやすいのです。
また、共有者の人数が多いほど維持費の負担調整が困難になるうえ、滞納する人が出てくるリスクも高まるため、支払いを巡ってトラブルに発展する可能性も高まります。
このように共有名義の不動産を放置すると相続のたびに権利関係が複雑化し、子供や兄弟姉妹など将来相続人になる可能性がある人に迷惑をかける恐れがあるのです。それを避けるためにも、離婚時に不動産を単独名義に変更し、権利関係をきっちりと分けておきましょう。
まとめ
離婚後も住宅ローンや家を共有名義のままにしておくと、家を自由に活用・売却できなかったり、不動産の維持費がかかり、続けた元配偶者が住宅ローンを滞納した場合に一括請求されたりするなど、さまざまなリスクが伴います。そのため、家や住宅ローンが共有名義の場合は、離婚時に必ず共有状態を解消しておきましょう。
どちらか一方が家に住み続ける場合は、住宅ローンの借り換えや一括返済などで住み続ける方の単独名義に変更するのが得策です。どちらも家に住まない場合は家を売却し、その売却益で住宅ローンを完済するのが望ましいでしょう。
ただし、オーバーローンの場合は原則として金融機関から売却の同意が得られないため、不足分を自己資金や親族からの援助で補うか、任意売却の許可を得る必要があります。離婚後のトラブルを未然に防ぐためにも、離婚時は住宅ローンや家の共有名義の解消に向けて夫婦でしっかりと話し合うようにしましょう。