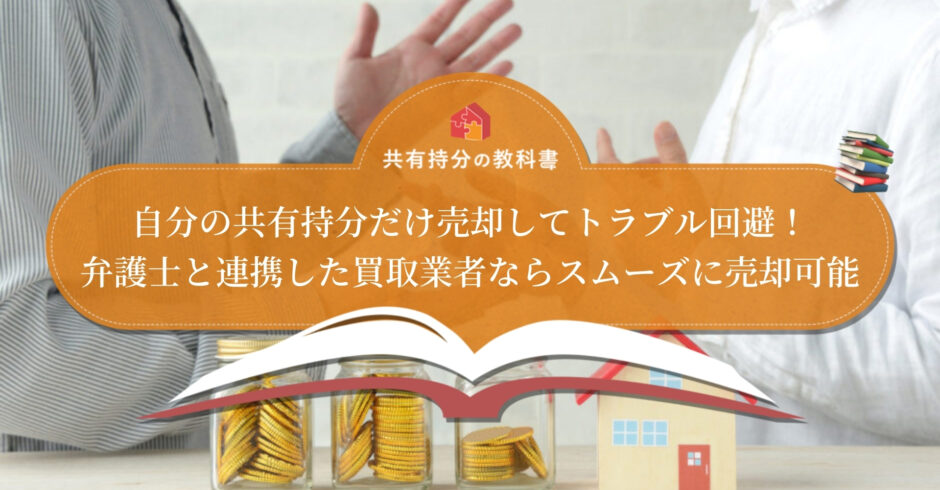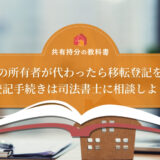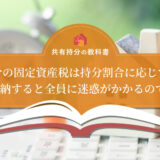「共有不動産を売却したいのに、他共有者に反対されて売却できない」といったトラブルも少なくありません。
なぜなら、共有不動産を売却するには共有者全員の同意が必要なので、意見が対立すると売却できないからです。
トラブルなく売却するには、共有不動産全体ではなく、自分の共有持分だけを売却するとよいでしょう。
とくに、弁護士と連携した共有持分専門の買取業者に買取してもらえば、抱えているトラブルも適切に解決しながら共有持分を現金化できます。
無料査定を利用すれば、最短12時間で価格がわかります。不動産と法律の専門家から、トラブルなく売却するためのアドバイスをもらいましょう。

- 共有不動産全体は個人で売却できず、共有者全員の同意が必要。
- 共有不動産の売却トラブルを解決するには、共有者間での話し合いの他、訴訟や審判・各種公的制度を使おう。
- 共有持分のみなら個人で売却可能であり、既にトラブルが起こっている共有不動産の悩みも解消される。
共有不動産全体を個人で売却することは法律的に不可能
はじめに抑えておきたい点として、複数人で共有している土地や建物といった、共有不動産を個人で自由に売却することはできません。
共有不動産とは、次のような理由で複数人の名義になっている不動産のことです。
- 亡くなった親から兄弟で相続した土地
- 夫婦や親子で一緒に購入したマイホーム
このような共有不動産は他の第三者と共同所有しているので、法律上では「共有物」という扱いになります。
共有不動産は自分1人で占有している不動産ではないため、個人での売却は認められていません。
共有不動産の売却トラブルを避けるために、まずは共有不動産を個人で売却できない理由を理解しておくとよいでしょう。
共有不動産自体は共有者全員の同意がないと売却できない
「共有している土地や建物は共有者全員の同意がないと売却できない」ことが民法で定められています。
民法第251条
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。引用:e-Govポータル「民法第251条」
条文の「変更」とは共有物全体に対して、売却や取り壊しなど一度おこなえばもとに戻せないような行為を指します。
そのため、共有者のうち誰か1人でも反対すれば、共有不動産を売却することはできません。
共有持分だけであれば個人で自由に売却できる
ひとつの不動産を複数人で共有する場合、土地や建物を分割せずに所有権だけを分けます。
分けられた所有権を「共有持分」といい、共有持分を持っている人を「共有者」や「持分権者」といいます。
共有持分は共有不動産とは異なり、個人の権利です。
そのため、共有持分は共有者各自の意思で自由に売却することも可能です。
次のようなケースの場合、対処方法として共有持分単体の売却をする人は少なくありません。
- 離婚をするため共有不動産を処分したいが、相手に反対されている
- 共有不動産を売却する許可を取りたいが、他共有者と連絡がつかない
共有不動産売却におけるトラブル事例と解決法
共有不動産全体を売却する場合、共有者同士で意見が合わずトラブルになるケースは多くあります。
しかし、共有者同士は家族や親族である場合も多く、関係の悪化や裁判沙汰になるのを避けたい人も少なくないでしょう。
また、トラブルが深刻化すると精神的負担はもちろん、裁判費用などの金銭的負担が生じる恐れもあります。
ここでは、どのようなケースで売却トラブルが起こるのかについて、具体的な事例と解決方法をみていきましょう。
共有不動産の売却を他共有者から反対されるケース
共有者全員が納得して、共有不動産をスムーズに売却できるケースは非常に少ないです。
共有不動産に住んでいる住人がいる場合などは「住居を手放したくない」という理由で、他共有者から反対を受けるでしょう。
そうすると、共有不動産全体での売却はできません。
共有不動産の売却を他共有者から反対された場合、不動産そのものを分割するという手段があるので解説します。
共有不動産を分割することで自由に売却できる
それぞれの共有者には、共有物の分割を求める「共有物分割請求」をする権利が民法で認められています。
民法第256条
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。(以下略)引用:e-Govポータル「民法第256条」
共有者のだれかが共有物分割請求をおこなうと、共有者は全員、共有不動産を持分割合に応じて分けるための話し合いをする必要があります。
分割した後の共有不動産は個人の所有物になるため、自由に売却して問題ありません。
ただし、他共有者が合意しない場合や「共有物分割禁止特約」を結んでいると、共有不動産を分割できない可能性もあります。
共有不動産を分割したいが合意を得られないケース
共有物分割請求をしたからといって、共有不動産の分割に他共有者が同意するとは限りません。
例えば、離婚する夫婦がどちらも「家を手放したくない」と主張している場合、一方が諦めない限り不動産の分割は不可能です。
また、共有物分割請求はあくまで話し合いでしかなく、強制的に分割させるというものではありません。
このように、共有物分割請求で解決できない場合、裁判所を通して強制的に共有物を分割できます。
共有物分割請求訴訟により裁判所命令で共有不動産を分割できる
「共有物分割請求訴訟」をおこなえば、裁判所命令で共有不動産を分割することができます。
共有物分割請求訴訟とは、裁判所に「共有不動産の適正な分割方法を決めてもらう」ための訴訟です。
民法第258条
共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。(以下略)引用:e-Govポータル「民法第258条」
具体的には、次の3つの方法で分割するよう、裁判所から判決がくだされます。
- 共有不動産そのものを分割して、それぞれの占有物にする「現物分割」
- 特定の共有者へ持分を譲る代償に、他共有者が金銭を受け取る「代償分割」
- 共有不動産を競売にかけて、落札代金を各共有者で分ける「換価分割」
「現物分割」が命令された場合、分割された後の不動産は単独名義になるので、自分の意思で売却可能です。
「代償分割や「換価分割」になった場合でも共有持分を現金化できるため、売却したのと同じことになります。
ただし、共有物分割請求訴訟にかかる裁判費用は数十万円を超える場合が多いため、経済的な負担は無視できないでしょう。
-
【共有物分割請求訴訟にかかる費用】
- 印紙代=不動産の固定資産税評価額によるが数万円程度
- 郵便切手代=6,000~8,000円程度
- 鑑定費用=数十万円程度
また、分割方法は裁判所が選ぶので自分の希望どおりにならない、換価分割の競売は一般的な売却より価格が安くなるというデメリットもあります。
共有物分割請求訴訟が棄却されることはほとんどないので、提訴すれば必ずなにかしらの方法で分割されます。
そのため、他共有者に「裁判で争うだけ無駄である」と伝え、できる限り話し合いで解決するとよいでしょう。
共有物分割請求訴訟についての詳細は、以下の記事を参考にしてください。
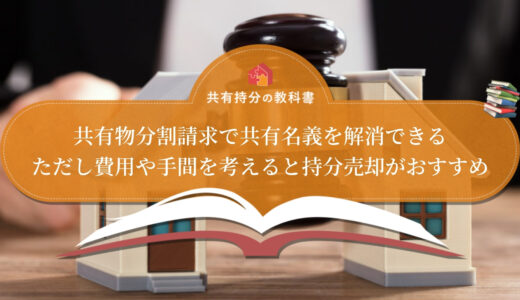 共有物分割請求とは?共有物の分割方法や訴訟の手順・費用を詳しく解説
共有物分割請求とは?共有物の分割方法や訴訟の手順・費用を詳しく解説
相続した共有不動産の売却について揉めるケース
相続によって共有持分を取得する人は多くいます。
主な事例としては、相続財産に共有持分が含まれていたパターンや、1つの不動産を複数人で相続するために共有名義で相続するパターンなどがあります。
しかし、誰が相続するかでトラブルになるケースも珍しくありません。
このように、共有不動産の相続について話がまとまらない場合は、裁判所を通して遺産の分け方を決めることができます。
 共有持分の相続は「売却」でリスクを防げる!相続から売却までの流れを解説します
共有持分の相続は「売却」でリスクを防げる!相続から売却までの流れを解説します
遺産分割審判によって裁判所命令で売却が可能
遺産相続における共有不動産のトラブルを解決するには、3段階のステップがあります。
- 共有者同士で「遺産分割協議」をして、相続する遺産の分け方を決めます。
- 遺産分割協議で話がまとまらない場合「遺産分割調停」で裁判所を交えて、再度話し合います。
- 遺産分割調停でも解決できない時は「遺産分割審判」によって、裁判所が遺産の分け方を決定します。
遺産分割審判でも、共有物分割訴訟と同じように「現物分割」「代償分割」「換価分割」といった方法で、共有不動産を分割するよう指示されます。
遺産分割審判の決定には法的な強制力があるため、裁判所命令で共有不動産を売却することが可能です。
他共有者と連絡が取れずに共有不動産を売却できないケース
「共有不動産を売却したいけれど他共有者と連絡が取れない」というケースもあります。
他共有者が行方不明などで連絡が取れないと、共有不動産の売却に必要な合意を得ることができません。
こうした場合であっても、勝手に共有不動産を売却すると、損害賠償を請求される可能性があります。
民法第117条
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。(以下略)引用:e-Govポータル「民法第117条」
他共有者と連絡が取れない場合「不在者財産管理人」という代理人を立てれば、共有不動産を売却することが可能です。
裁判所命令で不在者財産管理人を選べば売却できる
「不在者財産管理人選任」をすると、連絡の取れない共有者の代理人を選べます。
ただし、連絡のつかない共有者に代わる不在者財産管理人の選定には、家庭裁判所の許可が必要です。
もし他共有者が自分に親しい人物を代理人にした場合、元の所有者が不利益になる恐れがあるためです。
連絡のつかない共有者の代わりに不在者財産管理人から合意を得られば、共有不動産の売却ができます。
ただし、不在者財産管理人の申請から決定まで約2~3カ月かかる点には注意しましょう。
不在者財産管理人の選任方法については、以下の記事を参考にしてください。
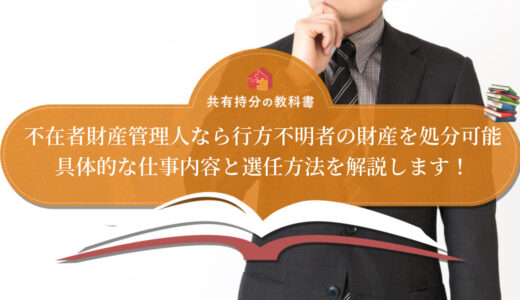 不在者財産管理人とは?仕事内容や選任方法をわかりやすく解説
不在者財産管理人とは?仕事内容や選任方法をわかりやすく解説
認知症の共有者がいるため共有不動産を売却できないケース
二世帯住宅などの増加によって「共有者が認知症になり共有不動産を売却できない」というケースも近年増えています。
認知症などで判断能力が低下すると、共有不動産を売却するための合意を得ることが困難になります。
このように他共有者が判断能力に欠ける場合、本人の意思決定を補助する「成年後見制度」を利用すれば、売却が可能になります。
民法第7条
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。引用:e-Govポータル「民法第7条」
共有者の代わりに後見人から同意を得られれば、共有不動産を売却することができます。
ただし、後見人の選び方が認知症になる前と後で異なるため注意が必要です。
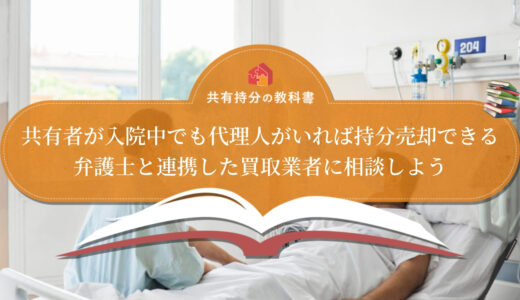 共有者が入院中に持分を売却する方法とは?マイホームの維持が困難なときの対処法も解説します!
共有者が入院中に持分を売却する方法とは?マイホームの維持が困難なときの対処法も解説します!
「任意後見制度」で代理人を選んでおけば売却できる
認知症になる前であれば「任意後見制度」によって本人の意思で後見人を決めておくことが可能です。
本人の意思で選んだ「任意後見人」に、共有不動産の売却をはじめとした意思決定を任せることができます。
任意後見契約に関する法律第4条
精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任する。(以下略)引用:e-Govポータル「任意後見契約に関する法律第4条」
認知症の共有者本人でなくても、任意後見人の合意があれば、共有不動産を売却することが可能です。
ただし、共有者本人から同意を得ている旨を公正証書として残す必要があります。
「法定後見制度」で共有者を変更すれば売却できる
認知症になってから後見人を選ぶ場合「法定後見制度」という方法でおこないます。
法定後見人制度は、前もって後見人を決めていない場合に、家庭裁判所を通して後から後見人を選ぶ制度です。
家庭裁判所によって認知症の共有者の代理人に選ばれた人物を「法定後見人」といいます。
認知症の共有者に代わって、法定後見人の合意を得ることができれば、共有不動産を売却することが可能です。
ただし、法定後見人は家庭裁判所が決めるため、その人物が必ずしも共有不動産の売却に合意するとは限りません。
また、任意後見人に比べて制限が多く、できることが限られるため注意が必要です。
共有不動産を売却できない場合は共有持分だけで売るのがベスト
ここまで、共有不動産の売却でトラブルの起こる原因と解決法を紹介しました。
しかし、裁判や手続きが必要になるため、費用や時間のかかる方法も少なくありません。
そこで、共有持分だけであれば手間もなくトラブルを避けて売却ができます。
ここまで紹介したトラブルも、共有持分のみの売却で全て解決可能です。
他共有者がどのような状況でも問題なく売却できる
共有持分は個人の所有物なので、個人で自由に売却ができます。
もしも持分の売却に他共有者が反対したとしても、法律的には一切問題ありません。
ただし、ローン残債や抵当権のある共有持分は、売却できる条件が限られるため注意が必要です。
抵当権設定されている共有持分に関しては、以下の記事で詳しく説明しています。
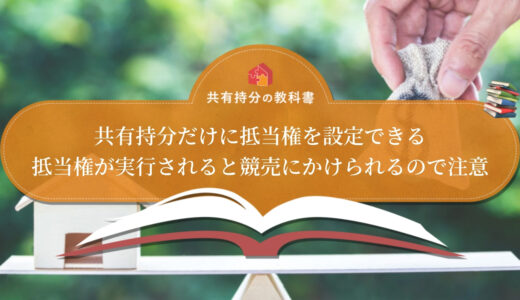 抵当権設定された共有持分はどうなる?競売後に落札者へ地代を請求する方法も解説
抵当権設定された共有持分はどうなる?競売後に落札者へ地代を請求する方法も解説
既に起きている共有不動産トラブルから離脱できる
共有持分を売ることで、権利を手放して共有関係を解消することができます。
手放した権利は持分を購入した買主に移るため、売却後は一切責任を負う必要はありません。
既にトラブルが起きている場合でも、問題なく共有関係から離脱することができます。
他共有者が先に持分を売却したときはどうするか
自分ではなく他共有者が共有持分を売却したとき、なにか注意すべき点があるのか気になる人は多いでしょう。
他共有者が持分を第三者へ売却した場合、考えられるリスクは「不動産会社から自分に対しても売買交渉を持ちかけられる」という点です。
自分も売却したいと思っており、不動産会社の条件に同意できれば問題ありません。
しかし、売りたくないと考えている場合や、不動産会社が不当に安い値段を提示してくる場合は、不動産会社との交渉をしなければなりません。
また、不動産会社から共有物分割請求訴訟を起こされた場合、判決を拒むことができないのもリスクといえるでしょう。
正当な価格で売買できるように不動産会社と交渉しよう
他共有者の持分が不動産会社の手に渡った場合、売買交渉自体はほぼ避けられないでしょう。
安価で買い叩かれないように、不動産会社と交渉する必要があります。
もしくは、自分で不動産会社から持分を買い取るという方法もあります。
いずれにしても、適正な価格で売買ができるように、妥協せず交渉をしていきましょう。
共有不動産に強い弁護士に相談して、対処方法のアドバイスや交渉の代行をしてもらうのもおすすめです。
トラブルなく売却するなら共有持分専門買取業者がおすすめ
トラブルなく共有持分を売却したいのであれば、不動産会社の選び方も重要になります。
一般の不動産会社ではなく、共有持分専門の買取業者に売却するとよいでしょう。
とくに、弁護士と連係をとっている専門買取業者なら権利関係の調整も得意なので、揉め事を起こさずスムーズに共有持分を買い取ってくれます。
共有持分を「早く」「安全に」「高く」売却したいときは、共有持分専門の買取業者へ相談するのがおすすめです。
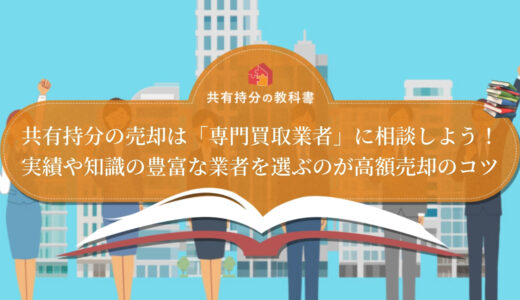 【共有持分の買取業者おすすめ28選!】共有名義不動産が高額買取業者の特徴と悪質業者の見極めポイント!
【共有持分の買取業者おすすめ28選!】共有名義不動産が高額買取業者の特徴と悪質業者の見極めポイント!
弁護士がトラブル解決のサポートをしてくれる
共有持分専門業者の中には、不動産トラブルに詳しい弁護士と提携している業者があります。
そうした業者であれば、法律的な問題も的確なアドバイスをしてもらえるうえ、必要であれば提携している弁護士を紹介してもらえます。
弁護士と提携している専門業者に売却すれば、トラブルが起きてもサポートを受けられるので安心して売却できるでしょう。
スピード買取によって早くトラブル解決できる
共有持分専門でない買取業者は、売却まで数週間~1カ月くらいかかります。売却まで時間がかかるほど、他共有者に知られてトラブルになる可能性が高いです。
専門買取業者なら2週間程度で素早く売却できるため、トラブルを起こさずに売却することも可能です。
既にトラブルが起きている場合でも、早急に共有関係を解消して離脱することができます。
トラブルを解決しつつ共有持分を高値で売却できる
共有持分を売却することで、トラブルを解決できるだけでなく、共有持分を現金化できます。
ただし、専門でない不動産会社に依頼をすると、共有持分を安く買い叩かれたり、買取拒否されるケースも少なくありません。
実績豊富な共有持分専門業者であれば、相場以上の価格での高額買取も可能です。
無料で査定をしている業者も多くあるので、まずは相談してみるとよいでしょう。
共有不動産についての売却トラブルは専門買取業者で解決できる
この記事では、トラブルを起こさずに共有不動産を売却するための具体例や解決策を解説しました。
共有不動産の売却でトラブルになっても、共有物分割請求訴訟や任意後見制度といった各種制度を利用すれば売却は可能です。
また、共有不動産自体の売却が難しい場合でも、共有持分だけを専門買取業者に売ればスムーズに利益化できます。
共有不動産や共有持分の売却で困った際は、弁護士・共有持分専門の買取業者など、専門家の知恵を借りるとよいでしょう。
共有不動産の売却についてよくある質問
もっとも注意すべきなのは、他共有者の同意です。共有者の1人でも売却に反対していると、共有不動産は売却できません。売却自体は同意をもらえても、売却価格で意見が合わないケースや、売買契約の直前で同意を取り消すようなケースがあります。共有者全員で事前に売却条件まで話し合い、書面に起こしておきましょう。
「共有物分割請求」で共有不動産の分割を求めることが可能で、不動産全体の売却だけでなく、共有持分を共有者間で売買するなどの方法を協議や裁判で決めます。また、自分の共有持分だけなら、他共有者の同意がなくても売却できます。
共有持分とは、複数人が共有する不動産において「各共有者がどれくらいの所有権をもっているか」を指すものです。「持分1/2」というように、割合で表記します。
共有持分の売買価格は、本来の価値から半額程度になるのが一般的です。ただし、売却相手や物件ごとの条件によっては高額になる場合もあり、すべての状況で共通する相場価格が決まっているわけではありません。
「弁護士と連携した共有持分専門の買取業者」なら、高額かつスムーズな取引が可能です。法律面から適切な手続きをしてもらえるのはもちろん、離婚協議や遺産分割などでトラブルになっている物件も、問題解決を含めたサポートが可能です。→弁護士と連携した買取業者はこちら