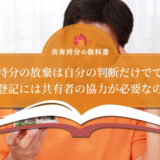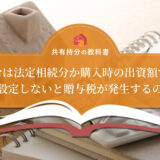共有持分とは、1つの不動産を複数人で共有しているとき、各共有者の所有権の割合を表すものです。
相続で共有持分を取得するケースとしては、共有持分そのものを相続する場合や、1つの不動産を複数の相続人で分割する場合があります。
共有持分を相続しても、共有不動産の使用や管理には他共有者の同意が必要なので、扱いにくくトラブルも起こりやすい傾向にあります。
そのため、共有持分を相続することになったら、専門の買取業者に買取してもらうとよいでしょう。
専門買取業者なら、最短48時間での現金化が可能です。相続後、他の共有者とトラブルが発生する前に売却できるので、リスクなく現金を取得できます。

- 共有持分を相続することになったら売却するのがおすすめ。
- 共有持分の相続には、公平な遺産分割や節税といったメリットもある。
- 共有持分を売却する際は、スムーズな売却が可能な「共有持分専門の買取業者」に相談する。
共有持分を相続することになったらどうする?
共有持分を相続するパターンとしては、次の2種類があります。
- 不動産を複数の相続人で分ける必要がある
- 相続財産に共有持分がある(被相続人が共有名義で不動産をもっていた)
いずれの相続パターンでも、相続することになった場合は次の選択肢から対応を選ぶことになります。
- 相続して売却する
- 相続して利用・運用する
- 分筆して相続する【土地限定】
- 相続放棄をする
それぞれの選択肢の具体的内容を、1つずつ見ていきましょう。
相続して売却する
共有持分が不要であれば、売却するとよいでしょう。現金に変えてしまえば、生活資金に回したり、別の資産に投資したりなど、幅広い活用が可能です。
売却する場合は、自分の共有持分だけ売却するか、他の共有者と一緒に不動産全体を売却するかという選択肢があります。
ただし、相続して売却するときは、下記のポイントに注意が必要です。
- 売却するときは名義変更をして相続手続きを終えている必要がある
- 不動産全体を売るときは共有者全員の承諾が必要
- 共有持分だけの売却は需要が低く資産価値も下がりやすい
まず、相続財産は名義を被相続人から相続人に変更しないと、売却ができません。そのため、共有持分を自分の名義に変更することが前提です。
次に、共有名義の不動産全体を売却するときは、共有者全員の同意が必要です。共有者が1人でも売却に反対すれば、不動産全体の売却はできません。
共有者が売却に反対しているのであれば、自分の共有持分だけを売ることになります。しかし、共有持分のみの売買は特殊な取引なので、不動産会社でも知識をもっているところは少数です。
普通の不動産会社だと売れないケースも多いため、共有持分の知識を豊富にもち、自社で直接物件を買い取る「共有持分専門の買取業者」に相談しましょう。
相続して利用する
共有持分を相続後、共有不動産に自分が居住したり、賃貸に出して収益化する方法もあります。
ただし、共有不動産の利用・運用は、行為の種類によって必要な持分割合が決まっています。「共有者のうちだれが住むかの決定」や「賃貸借契約の締結」には、持分割合の過半数が必要です。
共有持分を相続したからといって、共有不動産を自由に利用できるとは限りません。むしろ、だれがどのように利用するかで、共有者とトラブルになる恐れもあります。
持分割合の決まり方や、持分割当に応じて可能な行為の種類については、下記の関連記事を参考にしてください。
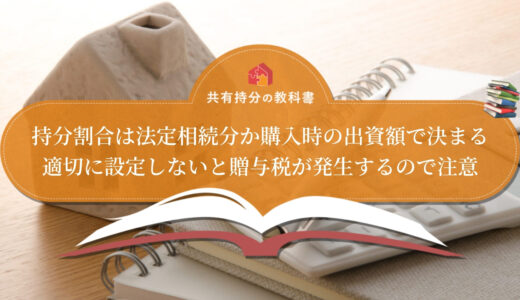 共有持分の割合はどう決まる?計算方法や持分割合に応じてできることを詳しく解説します
共有持分の割合はどう決まる?計算方法や持分割合に応じてできることを詳しく解説します
分筆して相続する【土地限定】
相続する共有持分が土地であれば、分筆してから相続するという方法があります。
1つの土地を切り分け、別の土地として分割する手続き。
相続予定の共有持分に合わせて土地を分筆すれば、単独名義の土地として相続が可能です。単独名義の土地であれば、売却も利用も自分の自由にできます。
ただし、土地の分筆は共有者全員の同意が必要です。共有者が1人でも反対していると分筆はできないので、持分売却のように単独でおこなえる方法を検討しましょう。
共有持分の分筆方法については、下記の関連記事で詳しく解説しています。
 共有持分にそって土地を分筆する手順|分筆のメリットとデメリットも解説!
共有持分にそって土地を分筆する手順|分筆のメリットとデメリットも解説!
相続放棄をする
共有持分が不要であれば、相続放棄をするのも1つの方法です。相続放棄をすれば、相続に関する話し合いや手続きに一切関わらなくて済みます。
また、相続財産に借金があっても、負担する必要がなくなる点も大きなメリットです。
一方、相続人としての権利すべてが消滅するため、共有持分以外の相続財産も放棄する必要があります。
相続財産が借金だらけで、トータルでマイナスとなるなら相続放棄は有効な手段です。しかし、少しでもプラスになるなら、相続して自分で運用・売却することをおすすめします。
 共有持分は相続放棄するべき?メリット&デメリットや手続き方法を解説します!
共有持分は相続放棄するべき?メリット&デメリットや手続き方法を解説します!
「相続して売却」でリスクを防ぎお得に遺産分割するのがおすすめ
共有持分を相続することになった場合、基本的には売却を前提に考えるとよいでしょう。
なぜなら、共有持分をもっていると多くのデメリットがあるからです。共有名義を維持せず早めに解消することで、将来のトラブルや固定資産税などの負担を回避できます。
ただし、共有持分を相続してから売却すると、公平な遺産分割が可能になる上、相続税の控除を多く受けられる可能性があります。
これらのことから、一旦は共有持分を相続した後、なるべく早いうちに売却する方法をおすすめします。
共有持分をもっていると多くのリスクが発生する
共有持分をもっていると、下記のように多くのリスクが発生します。
- 共有不動産の使い道を巡って揉める
- 「共有不動産の恩恵」がなくても税金や維持費の負担がある
- 二次相続で共有者が増えていく
- 知らないうちに第三者の共有者が増えてしまう
簡単にいえば、共有持分をもっていても不動産の使用には制限があり、コストや管理責任の負担に見合わない場合が多いのです。
また、共有者と利害が対立しやすく、トラブルとなるケースが少なくありません。共有不動産の扱いを巡って、裁判沙汰になるケースもあります。
これらのことから、不動産の共有名義はなるべく早く解消し、大きなトラブルが発生するのを未然に防ぐべきなのです。
共有持分のリスクについては、下記の関連記事でも詳しく解説しています。
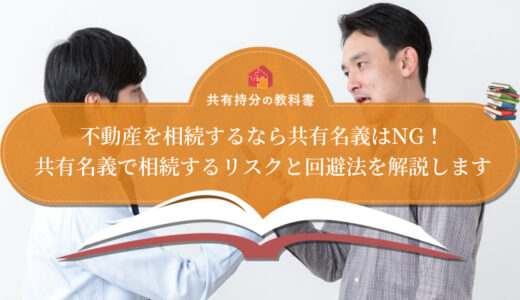 共有名義の不動産相続はリスクばかり!ベストな相続方法を解説
共有名義の不動産相続はリスクばかり!ベストな相続方法を解説
共有持分を相続して売却することのメリット
「共有持分にはリスクが多い」といいましたが、売却を前提として相続する場合、下記のようなメリットもあります。
- 相続不動産を公平に分割できる
- 相続人それぞれが「3,000万円特別控除」を利用して節税できる
避けるべきなのは「共有名義を維持し続けること」であって、最終的に共有持分をどうするか決めている(売却することを決めている)場合、有効な遺産分割の方法となるのです。
相続不動産を公平に分割できる
相続において、不動産という資産は分割がしにくい資産です
建物は物理的に分割することがむずかしいため、権利上の分割である共有持分での相続は、遺産分割を公平に進める有効な方法となります。
土地には分筆という方法もありますが、分筆は切り分けた後の形状や接道状況などで土地の資産価値が変わりやすいため、公平な分割をするには共有持分での相続が有効なのです。
相続人それぞれが「3,000万円特別控除」を利用して節税できる
相続した不動産が実家の場合、売却したときに譲渡所得税を減らせる特例が2つあります。
| マイホームを売ったときの特例 | 一定の要件を満たしているマイホームを売却した場合、課税対象となる売却益(譲渡所得)から3,000万円を控除できる制度。 |
|---|---|
| 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 | 被相続人が1人で住んでいたマイホームを売却し、一定の要件を満たしていた場合、課税対象となる売却益から3,000万円を控除できる制度。 |
要するに、相続した実家を売却したときに売却益が3,000万円以内なら、譲渡所得税がかからないという特例です。
そして、この特例は相続人それぞれが受けられるため、共有名義で相続してから不動産全体を売ることで、譲渡所得税を大幅に減らすことができます。
しかし、2人の共有名義で相続していたのであれば、控除の計算は「6,000万円-6,000万円=0円」なので、譲渡所得税は0円となるのです。
参照:国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
共有持分を相続して売却することのデメリット
共有持分のリスクについてはすでに解説しましたが、「共有持分を相続して売却する」という流れを取った場合、具体的には下記のデメリットが発生します。
- 意見を変える相続人が出てきて揉める恐れがある
- 共有持分のみの売却は専門の買取業者以外むずかしい
相続して売却する際は、これらのデメリットを踏まえて対策も講じましょう。
それぞれの詳しい内容を解説します。
意見を変える相続人が出てきて揉める恐れがある
相続では、相続人の1人が取り決めを破ってトラブルになるケースが少なくありません。
共有持分の場合、共有不動産全体の売却で合意していたのに、後になって「やっぱり売りたくない」といってくるケースがあります。
また、独断で価格を決めて勝手に売却してしまったり、占有状態にして他の共有者が使えなくするといったトラブルもありえます。
こういったトラブルを防ぐには、相続の取り決めを遺産分割協議書などの書面に起こし、後から意見を変えられないようにしましょう。
また、相続後は放置せず、なるべく早いうちに売却することで相続人の心変わりを防げます。
共有持分のみの売却は専門の買取業者以外むずかしい
共有持分の売却は一般的な不動産取引とはいえず、不動産業者でも取り扱い経験がない場合があります。
取引される金額が小さくなる(共有持分の売買価格は「不動産全体の価格×持分割合」が基本)ので、売買価格で仲介手数料が決まる仲介業者だと取り扱いを断られる恐れもあります。
そのため、共有持分の売却は、専門の買取業者に依頼するのが一般的です。
専門の買取業者は自社で共有持分を買い取り、権利関係の調整や他共有者との交渉を経て収益化するので、高額かつスピーディーな現金化が可能です。
共有持分を売却するときは、実績が豊富な専門買取業者に相談するようにしましょう。
共有持分を相続して売却するときの流れ
共有持分は、名義を被相続人のものから相続人のものに変えなければ売却できないため、相続手続きを先に済ませておく必要があります。
具体的には、下記の流れで相続手続きを進めていきます。
- 相続人全員で話し合って具体的な相続案を決定する
- 相続登記で名義変更をおこなう
- 相続税を申告して納付する
- 売却する
- 譲渡所得税を納める
相続手続きは自分でもおこなえますが、不安な場合は専門家である弁護士や司法書士に相談しましょう。書類の準備・作成や、必要な申請をサポートしてくれます。
1.相続人全員で話し合って具体的な分割案を決定する
まずは相続人全員が話し合い、共有持分を含めた相続財産全体の具体的な分割案を決定します。
共有者全員が分割案に合意したら、遺産分割協議書を作成しましょう。作成方法については、下記の関連記事で詳しく解説しています。
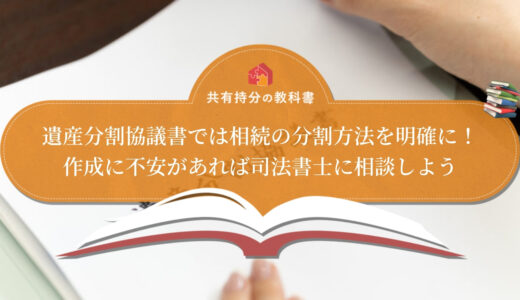 遺産分割協議書は相続人が作れる!ひな形通りの正しい書き方や作成依頼先も解説
遺産分割協議書は相続人が作れる!ひな形通りの正しい書き方や作成依頼先も解説
なお、遺言書が残されている場合はその内容に従うのが原則ですが、相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる内容で遺産分割をおこなうことも可能です。
2.相続登記で名義変更をおこなう
遺産分割協議が終わったら、その内容に従って相続登記をおこないましょう。
法務局に申請書類を提出し、共有持分の名義を被相続人から相続人のものに変更します。名義変更が終わればその資産は相続人のものになり、売却などが可能になります。
相続登記については、下記の関連記事もぜひ参考にしてください。
 共有持分の相続登記は要注意!共有持分の相続登記で発生するデメリットと対処法もあわせて解説します
共有持分の相続登記は要注意!共有持分の相続登記で発生するデメリットと対処法もあわせて解説します
3.相続税を申告して納付する
相続登記が終われば、取得した資産の評価額に従って、相続税を納めます。
ただし、相続税の申告は「相続が発生してから10ヶ月以内」が期限となっています。共有持分の売却益から相続税を納めたい場合は、先に売却手続きを進めるとよいでしょう。
申告・納付先は、被相続人もしくは財産を取得した人の住所地を所轄する税務署です。
なお、相続税は複雑な計算方法や申請様式があるので、正確に申告するためには、専門家である税理士に相談するとよいでしょう。
4.売却する
相続登記が終わったときから、相続財産の売却が可能になります。
具体的な売却先のパターンとして下記の3つがあげられます。それぞれのメリットを解説するので、状況に合わせて選びましょう。
- 共有持分を買取業者に売却するケース
- 共有不動産全体を売却するケース
- 共有持分を相続人の間で売買するケース
共有持分を買取業者に売却するケース
共有持分を専門の買取業者に売却すれば、スピーディーな売却が可能です。
買取業者は共有持分を自社で直接買い取るため、仲介業者のように買主を探す手間を省けます。需要が低く売れにくい共有持分でも、買取業者なら最短48時間で現金化が可能です。
なお、共有持分を買い取った業者は、他の共有持分も買い取って1つにまとめるなど、資産価値を高めてから再販売するといった方法で利益をあげます。
そのため、権利関係の調整や交渉が得意な買取業者ほど、共有持分の買取価格も高額になります。
このことから、共有持分の買取業者は「弁護士と連携している買取業者」がおすすめです。弁護士と協力して効率的に利益を得ることができるので、買取価格も高くなります。
【小型の共有持分でも高額買取!】弁護士と連携した買取業者はこちら
共有不動産全体を売却するケース
共有者全員が売却に同意しているのであれば、共有不動産全体を売却できます。
不動産全体を売り出すなら、単独名義の不動産と同じように売却できるため、スムーズな売却が可能です。
ただし、共有名義の不動産を売るときは、売買契約の締結や物件の引き渡し時に、共有者全員の立ち会いが必要です。
全員の立ち会いがむずかしいときは、代理人を立てることもできます。委任状の作成が必要となるので、下記の関連記事も参考にしてください。
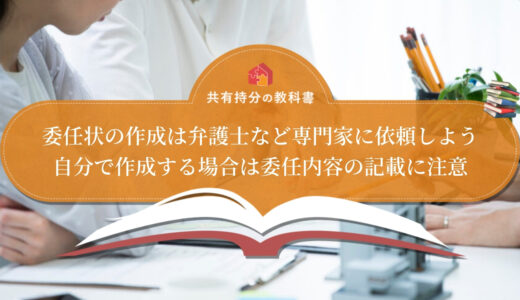 共有名義不動産を売却する時の委任状はどう書く?ひな形で書き方を解説!代理人の選定方法もあわせて説明します
共有名義不動産を売却する時の委任状はどう書く?ひな形で書き方を解説!代理人の選定方法もあわせて説明します
共有持分を相続人の間で売買するケース
当事者同士が合意していれば、共有持分を相続人の間で売買することも可能です。
相続人同士の売買に限り、相続登記の前に売買することもできます。正確には、遺産分割で「代償分割」という方法を取ることになります。
1人の相続人が不動産や共有持分を取得する代わりに、他の相続人に対して金銭を支払う遺産分割の方法。
相続人が「不動産や共有持分を売却したい人」と「そのまま持ち続けたい保有したい人」にわかれているとき、代償分割が有効な解決方法となります。
5.譲渡所得税を納める
共有持分の売却後、譲渡所得税を納める必要があります。譲渡所得税は、売買のあった年の翌年、2月16日から3月15日の間におこなわれる確定申告で納めます。
会社勤めの人などは、確定申告に慣れていない人も多いと思うので、不安があれば税理士に相談しましょう。
期間の終盤は税務署も混み合うため、なるべく早めの申告をおすすめします。また、e-Taxを使ったオンライン申告も可能です。
具体的な申告方法については、下記の関連記事も参考にしましょう。
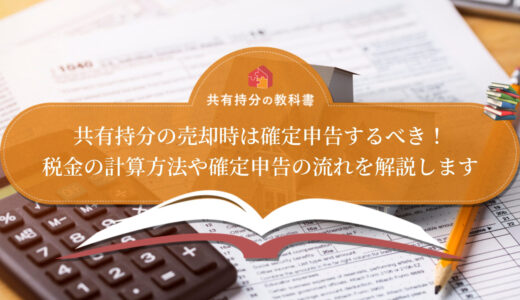 共有持分を売却したら確定申告は必要?税金の計算方法や申告の流れを解説します
共有持分を売却したら確定申告は必要?税金の計算方法や申告の流れを解説します
共有持分は一旦相続して必要なければ売却するのがベスト
共有持分は、もっていても共有不動産を自由に利用できるわけではなく、頻繁に共有者との話し合いが必要になります。
そのうえ、仮に自分が共有不動産を利用していなくても管理責任は発生するので、扱いにくい資産です。
ただし、共有持分だけ売却することも可能なので、相続することになったら売却を検討するとよいでしょう。相続後であれば、自分の意思でいつでも自由に売却できます。
専門の買取業者に頼めばスピーディーな現金化もできるので、相続財産のトータルがマイナスでなければ、売却して現金を得ることをおすすめします。