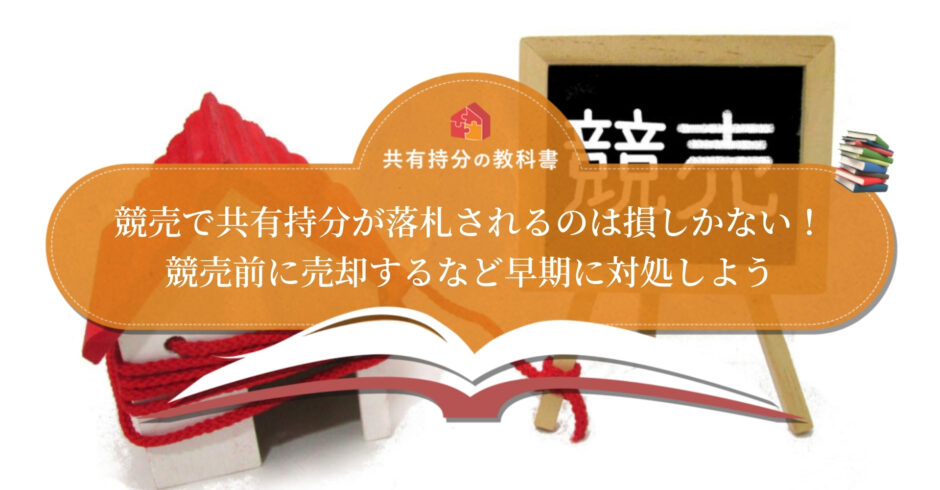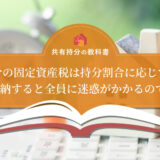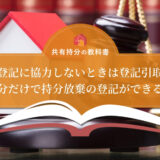「ローンの支払いを怠った他共有者が財産の差し押さえにあった」「共有者が共有持分を借金の担保にしていた」といった理由で、共有持分が競売にかけられる場合があります。
共有持分が競売に出され第三者に落札されると、その第三者と自分が共有関係になってしまいます。
落札して共有者となった第三者は、今度は自分に対して共有持分の売買をもちかけてきたり、強引に不動産全体の売却を迫ってくるかもしれません。
第三者との共有関係を避けるには、競売前に他共有者から共有持分を買取るなどの対応が必要です。しかし、買取るだけの資金がない人や、いっそのこと自分も処分したいという人もいるでしょう。
そういった人は、トラブルになる前に自分の共有持分を売ってしまうのもおすすめです。共有持分専門の買取業者に依頼すれば、高額かつ最短2日でのスピード買取が可能なので、まずは無料相談を受けてみましょう。
▶【トラブルがあってもOK】今すぐ共有持分を現金化するならこちら!

- 共有持分が競売かけられたときに起こりうるトラブルと解決法を知っておこう。
- 他共有者の持分が落札されたら共有関係から抜けるのがおすすめ。
- 競売にかけられる前に対処するのがベスト。
他共有者の共有持分が第三者に落札されるとなにが起きる?
競売にかけられた不動産は、基本的に市場価格より安い値段で落札されます。
競売にかけられた共有持分を落札するのは、主に不動産業者や投資家です。
共有持分を落札する不動産業者や投資家は、落札した共有持分をさらに売却するか、他共有者の共有持分を買い取って単独名義にします。
他共有者が売買を断ると、共有物分割請求訴訟を起こされるかもしれません。
競売で安く仕入れた共有持分を、価値を上げて売却・収益化するのが落札者の目的です。
落札者から持分の買取や売却を持ちかけられる
不動産業者や投資家が利益を出す方法の一つとして、共有持分を落札した価格よりも高値で売却することがあります。
共有持分は、持分だけ持っていても活用や売却が自由にできません。
そこで持分をすべて所有して活用しようと考えたり、上記を理由に共有者へ買取を持ちかけることが予想されます。
落札者である不動産業者or投資家との売買取引は、決して損ばかりではありません。通常であれば適正な価格での買い取りを持ちかけられるため、売却に同意するのも一つの解決方法です。
しかし、中には悪質な不動産業者や投資家もおり、著しく低い価格での買い取りを持ちかけられることもあるため注意しましょう。
不動産業者や投資家からの買取請求に強制力はありません。しかし、不動産売買のプロである不動産業者or投資家との交渉は、不利な条件になってしまうことも多くあります。
共有物分割請求訴訟を起こされる
不動産業者や投資家からの買取請求を拒否した場合に、共有物分割請求訴訟を起こされる可能性があります。
共有物分割請求権とは、共有物の分割を求める権利のことです。共有持分をもっていれば誰でも提起できます。
基本的には共有者から共有物分割請求をされたのちに話し合いの場を設けますが、話し合いで解決できないようであれば訴訟に進みます。
とくに、共有者が身内ではなく利益を出すことを目的とした第三者の場合、話し合いによる解決が難しく訴訟になってしまうケースが多くあります。
訴訟の結果次第では不動産全体を競売にかけることにもなりかねません。
共有物分割請求については、関連記事もご覧ください。
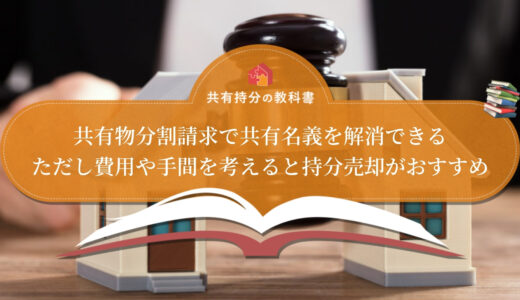 共有物分割請求とは?共有物の分割方法や訴訟の手順・費用を詳しく解説
共有物分割請求とは?共有物の分割方法や訴訟の手順・費用を詳しく解説
他共有者の共有持分が競売にかけられたときの解決方法5つ
他共有者の共有持分が競売となり、第三者の手に渡ってしまうと買取請求や訴訟を持ちかけられる可能性があるのは前述したとおりです。
ただ、なるべくなら訴訟などという事態は避けたいと思う人が多いのではないでしょうか。
そのためには、競売にかけられる前などなるべく早い時点で対処することが望ましくなります。
共有持分が競売となってしまったときの解決法について説明していきます。
1.競売にかけられる前であれば持分を任意売却で買い取る
他共有者の持分が差し押さえられそうなことが事前にわかっているなら、競売にかけられる前に他共有者の持分を任意売却で買い取り、自分の持分とする方法があります。
共有持分が差し押さえられる前であれば、不動産を取引することは自由なので共有者から直接買い取れます。
この場合、共有者間での交渉により自由に価格設定ができますが、あまりに市場相場よりも低く設定してしまうと贈与とみなされ、贈与税が発生することがあるので注意しましょう。
詐害行為取消となる可能性がある
詐害行為取消権とは、債務者が十分な返済資金を確保しないまま財産を処分したときに、その処分を債権者が取り消せる権利です。
債権者が不動産を担保にしており、かつ債務者が不動産を売却してしまうと返済ができなくなることを知った上で任意売却をしてしまうと、債権者は詐害行為取消権を行使する可能性があるので注意しましょう。
詐害行為取消権の詳細は民法第424条から426条を参考にしてください。
2.競売にかけられた他共有者の持分を自分で落札する
競売になった共有持分が落札前であれば、自分で落札することができます。
共有持分を落札することで、自分の持分割合が増えると共有不動産の利用もしやすくなります。
また、競売での価格は市場相場よりも低い価格であることがほとんどです。
そのため、不動産を手放したくなく、資金も用意できるなら自分で落札するのもよいでしょう。
3.債権者と交渉して競売を取り下げてもらう
競売にかけられた後も、競売の申立人である債権者と交渉すれば競売を取り下げてもらえるかもしれません。
債権者は貸したお金を回収できればよいので、その分のお金を支払うことで競売を回避してもらう方法です。
競売で共有持分を落札するのと同じように見えますが、競売で自分が確実に落札できるとは限りません。
万が一にも共有持分を第三者に渡したくないときは有効な方法といえるでしょう。
4.落札者へ持分の買取を持ちかける
落札後であれば、落札者に買取を持ちかける方法があります。
ただし、前の項目でも説明したように、落札者は利益を得る目的で共有持分を落札していることがほとんどです。
そのため、「落札価格+見込んでいた利益」でないと買取を拒否される可能性があります。
資金が用意できそうであれば、落札後に交渉するよりも自分で落札するほうがよいでしょう。
5.自分の持分を第三者に売却して共有関係から抜ける
前の項目で述べたように、他共有者の持分が第三者の手に渡ってしまうと、不動産業者や投資家から買取請求や訴訟を持ちかけられることがほとんどです。
そこで、自分の持分も第三者へ売却し、共有関係から抜けることで解決するとよいでしょう。
ただし、共有持分のみでの利用や売却は難しいため、個人の買主を探すのは難易度が高い作業となります。
共有持分の売却は専門の買取業者へ依頼するのがおすすめです。専門業者は共有持分を活用するノウハウを持っているため、一般的な不動産業者では取り扱い困難な共有持分も素早く・高値で買い取ってくれる可能性が高いです。
自分の持分を放棄して共有関係を解消する
共有関係から抜ける方法として「持分の放棄」があります。
持分の放棄は、自分の共有持分を放棄して他の共有者に分配させるというものです。他共有者の同意は必要なく、自分の意志だけでおこなえます。
ただし、放棄そのものは自分の意志でおこなえても、それを証明するための「登記」は他共有者の協力が必要になります。
持分の放棄により共有関係から抜けたい場合は、弁護士に相談するのがよいでしょう。
持分の放棄に関しては、別の記事で解説しています。
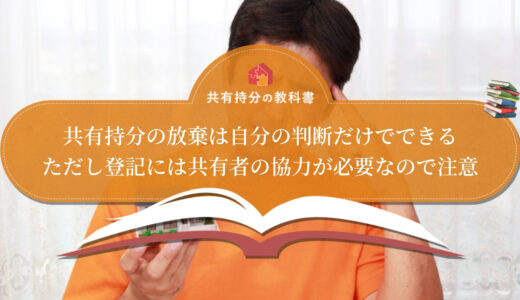 共有持分は放棄できる!放棄の手順や放棄後の登記も詳しく解説します
共有持分は放棄できる!放棄の手順や放棄後の登記も詳しく解説します
他共有者の共有持分が競売に陥る前にできること
競売にかけられた後でも対処できる方法があるとはいえ、できることなら競売となる前に解決したいと思う人が多いのではないでしょうか。
顔も知らない第三者と共有関係になる可能性など、面倒事を避けたいのであれば先手を取って対応する必要があります。
他共有者の共有持分が競売となる前にできることを説明していきます。
共有不動産全体で一括売却する
共有者と共同で不動産を一括売却し、その売却利益で負債を返済することで競売を阻止できます。
共有持分だけでの売却は需要が低く、市場相場よりも低い価格での売却となってしまうことがほとんどです。
それに比べて、一括売却であれば市場相場と変わらない価格で売却交渉ができるメリットもあります。
共有者の代わりに負債を支払う
債権者と交渉して、共有者の負債を代わりに支払うことで不動産が競売にかけられるのを防ぐ方法があります。
その場合は共有者に対して、のちに返還請求できるように借用書を作成しておくとよいでしょう。
競売になりかけた共有者は返済能力がないため、金銭での返還ではなく、共有持分を返還するケースが多いようです。
債権者や共有者との話し合いは、のちのトラブルを防ぐためにも、弁護士を挟んだ方がよいでしょう。
他共有者の持分が競売になったら自分の持分も売却しよう
競売で共有持分を落札するのは主に不動産業者や投資家です。
共有持分を落札した不動産業者や投資家は、買取請求や売却を持ちかけて利益を得ようとすることが一般的です。
買取請求に法的効力はありませんが、拒否すると共有物分割請求訴訟を起こされてしまうこともあります。
そういった事態を回避するには、自分の持分も売却して共有関係から抜けてしまうのが、手元に売却利益も入るのでおすすめです。
▶【トラブルがあってもOK】今すぐ共有持分を現金化するならこちら!
共有持分の競売についてよくある質問
競売で共有持分を落札した人が、他の共有者に対して、持分の売買や共有物分割請求をもちかける恐れがあります。
競売にかけられた他共有者の持分を自分で落札するか、自分の持分も第三者に売却して共有関係を解消しておくとよいでしょう。
共有不動産全体を一括で売却し負債の返済に充てる方法や、他共有者の負債を立て替える方法などで、競売を避けられます。
共有持分を専門としている買取業者のなかでも、弁護士と連携している専門買取業者に相談するのがおすすめです。借金トラブルから共有持分の売却まで、総合的なサポートを受けられます。→弁護士と連携した買取業者はこちら
市場価格の6~7割ほどになります。もともと、共有持分の市場価格は低くなる傾向にあるので、競売では本来の価値から大きく安くなることが予想されます。競売にかけられるより、高額で買取可能な専門買取業者に買取ってもらったほうが高値で売れやすいでしょう。