不動産を共有している場合「共有名義人の片方が亡くなったら持分はどうなるのか?」と不安に思う方は多いでしょう。
共有名義人が死亡した場合の相続は、法定相続人が優先されるため、他の共有者が相続人でない場合は自動的に持分を取得できるわけではありません。
共有名義人が亡くなった場合、引き継がれる際の優先順位は以下のとおりです。
- 遺言があれば原則として遺言で指定された人物が持分を相続する
- 遺言がなければ基本的に死亡した共有者の法定相続人が相続する
- 法定相続人がいない場合は特別縁故者に相続財産分与される
- 相続人も特別縁故者もいなければ、生きている共有者に帰属する
相続手続きは、遺言の有無を確認し、相続人や財産を調査したうえで遺産分割協議を行い、その後に相続登記や税務申告を行うのが一般的です。
ただし、相続人が複数に分かれたり疎遠だったりすると、協議が進まず売却や活用に支障をきたすケースもあります。
こうしたトラブルを避けるには、生前に遺言を残しておく、生前贈与する、家族信託の活用といった対策が有効です。
すでに相続が発生してしまった場合でも、「共有持分を放棄する」「第三者に売却する」といった方法で共有状態を解消できます。
しかし、共有持分は単独での利用価値が低く、一般の不動産会社や個人が購入することはほとんどありません。そのため、複数の専門業者に査定を依頼し、価格や提案を比較することが重要です。
とはいえ、共有持分を専門に扱う業者は限られており、ご自身で探して交渉するのは大きな負担です。
そこでおすすめなのが、「イエコン一括査定」です。厳選された共有持分・訳あり不動産の専門業者にまとめて査定を依頼でき、しつこい営業電話もなく、弁護士や税理士との連携サポートも整っています。
お問い合わせ実績は3万件を超えており、多くの方が安心して利用しています。
まずは無料査定で、あなたの共有持分がどれくらいの価格で売却できるのか確認してみてください。
共有名義人の片方が死亡した場合、不動産はどうなる?
「共有名義で不動産を持っていた相手が亡くなったが、持分はどうなるのか?」というご相談は少なくありません。
共有名義人の一方が亡くなった場合、その人の持分は相続の対象です。ただし「自動的に生きている共有者に移る」わけではなく、法律に従って次の優先順位で引き継がれます。
- 遺言があれば原則として遺言で指定された人物が持分を相続する
- 遺言がなければ基本的に死亡した共有者の法定相続人が相続する
- 法定相続人がいない場合は特別縁故者に相続財産分与される
- 相続人も特別縁故者もいなければ、生きている共有者に帰属する
不動産を共有している場合、売却や抵当権設定などの重要な手続きには原則として共有者全員の同意が必要です。そのため、共有者の人数が増えるほど意思決定が難しくなるという特徴があります。
例えば、夫婦で2分の1ずつ持分を共有し、子どもが2人いる場合、夫が亡くなると夫の持分は妻と子どもに分けられます。その結果、妻と子ども2人の3人が共有者となり、売却や管理の意思決定が複雑になりやすいのです。
死亡した共有者の持分がどう処理されるかは相続人の有無や関係性によって大きく異なります。以下でケースごとに詳しく解説します。
「法定相続人」や「特別縁故者」について詳しく知りたい場合、こちらの記事もあわせてご覧ください。
 特別縁故者とは?認められる要件や遺産を取得する方法を詳しく解説
特別縁故者とは?認められる要件や遺産を取得する方法を詳しく解説
死亡した共有者の共有持分は法定相続人が相続する
共有名義人が亡くなると、その人の持分は相続財産として扱われ、民法第887条・889条・890条で定められた法定相続人に引き継がれます。
よく誤解されがちですが、もう一方の共有者が自動的に取得できるわけではありません。
法定相続人の範囲と順位は以下のとおりです。優先順位が高い人がいる場合、後順位の人には相続権がありません。
- 常に相続人となる:配偶者
- 第1順位:子ども(子が死亡している場合は孫)
- 第2順位:直系尊属(父母、いなければ祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹(死亡している場合は甥・姪)
相続割合(法定相続分)は民法第900条で定められており、遺産分割協議を行う際の基準となります。
| 相続人の組み合わせ | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者のみ | 配偶者がすべて相続 |
| 配偶者と子 | 配偶者1/2、子ども1/2(複数なら均等に分ける) |
| 配偶者と直系尊属 | 配偶者2/3、直系尊属1/3(複数なら均等に分ける) |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(複数なら均等。異父母兄弟はさらに1/2=1/8) |
このように、誰がどの割合で相続するかは法律で明確に決まっています。
なお、ここで紹介する相続例は、遺言がなく、法定相続割合どおりに分けた場合を前提としています。
遺言がある場合はその内容が優先され、遺言がなくても相続人全員の合意があれば法定相続分と異なる分け方も可能です。
夫婦や親子で共有していた場合、具体的にどのような相続が発生するのか解説します。
参照:国税庁「相続人の範囲と法定相続分」
参照:民法第887条・889条・890条・900条
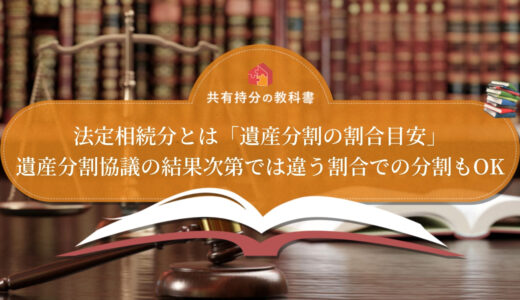 法定相続分とは?遺産分割における法定相続分の割合と優先順位をわかりやすく解説します
法定相続分とは?遺産分割における法定相続分の割合と優先順位をわかりやすく解説します
夫婦で共有していた場合の相続例
夫婦でそれぞれ2分の1ずつ不動産を所有していたケースを考えてみましょう。
夫が亡くなった際、子どもや親、兄弟姉妹といった他の相続人がいない場合には、妻が夫の持分すべてを相続するため、妻の単独所有になります。
一方、相続人が妻と子ども2人だった場合、夫の持分1/2は「妻と子ども全体で半分ずつ」に分けられます。そして子どもの持分は、さらに人数で等分されるのです。
法定相続割合は妻が1/2、子ども2人がそれぞれ1/4となり、夫の持分1/2をこの割合に当てはめると以下のようになります。
- 妻:1/4(夫の持分1/2 × 1/2)
- 子どもA:1/8(夫の持分1/2 × 1/4)
- 子どもB:1/8(夫の持分1/2 × 1/4)
この結果、相続後の持分は以下のとおりです。
- 妻:3/4(自分の1/2+相続1/4)
- 子どもA:1/8
- 子どもB:1/8
残された妻だけで単独所有になるのではなく、子どもも新たに共有者となります。共有者が増えると売却や抵当権設定などに全員の同意が必要になり、不動産を思うように活用できなくなるおそれがあります。
親子で共有していた場合の相続例
次に、父親と長男がそれぞれ1/2ずつ不動産を共有していたケースです。
父親が亡くなり、相続人が母・長男・次男だった場合、父の持分1/2は法定相続分にしたがって分割されます。
この場合、母と子ども全体で半分ずつ分け、さらに子どもは人数で等分するため、割合は母1/2、長男1/4、次男1/4です。これを父の持分1/2に当てはめると、以下のようになります。
- 母:1/4(1/2 × 1/2)
- 長男:1/8(1/2 × 1/4)
- 次男:1/8(1/2 × 1/4)
相続後の持分は以下のとおりです。
- 母:1/4
- 長男:5/8(自分の1/2+相続1/8)
- 次男:1/8
このように、もともとの共有者である長男が自動的に父の持分をすべて引き継ぐわけではなく、他の相続人も共有者となります。
遺言があれば法定相続人以外も相続人になる
被相続人が遺言を残せば、法定相続人以外の人物を相続人にすることが可能です。
法定相続人以外に財産を残すことを「遺贈」といい、被相続人が遺言書で相続人や分割方法を指定します。
例えば、長年介護をしていた親族や同居していた孫などを遺言で指定するケースが考えられるでしょう。
ただし、民法第1042条で定められた「遺留分」という最低限の取り分が法定相続人には保障されています。
遺留分とは、配偶者や子ども、直系尊属など一定の相続人に認められた、必ず受け取れる相続財産の割合です。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
もし遺言で遺留分を侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」によって最低限の財産を取り戻せます。
遺留分の割合は次のとおりです。
| 相続人 | 配偶者の遺留分 | 子どもの遺留分 | 直系尊属の遺留分 |
|---|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1/2 | – | – |
| 配偶者と子 | 1/4 | 1/4 | – |
| 配偶者と直系尊属 | 1/3 | – | 1/6 |
| 子のみ | – | 1/2 | – |
| 直系尊属のみ | – | – | 1/3 |
仮に「全財産を孫に相続させる」と遺言に書いても、配偶者や子どもには遺留分があるため、その一部は必ず確保されます。
上記の場合、配偶者と子ども2人が相続人なら、遺留分は以下のとおりです。
- 妻:全体の1/4
- 子どもA:全体の1/8
- 子どもB:全体の1/8
遺言は有効に使えば相続トラブルを減らせますが、書式の不備で無効になったり、遺留分を巡る争いが発生したりするリスクもあります。確実に効力を発揮させたい場合は、弁護士など専門家に相談して作成するのが安心です。
参照:民法第1042条
法定相続人がいない場合は特別縁故者に共有持分が財産分与される
共有名義人が亡くなり、配偶者や子どもなどの法定相続人が一人もいない場合には、残された共有者にすぐ持分が移るわけではありません。まずは「特別縁故者」と呼ばれる人物に、家庭裁判所を通じて財産分与されます。
特別縁故者に分与するかどうかは家庭裁判所が判断し、債務を清算した後に残った財産を一部または全部取得できます。
民法第958条の3
(前略)家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
ただし、特別縁故者への相続財産分与は自動的におこなわれるわけではなく「相続財産管理人選任の申立」によって、自分が特別縁故者であることを主張する必要があります。
相続財産管理人について詳しく知りたい人は、こちらの記事もあわせて参考にしてください。
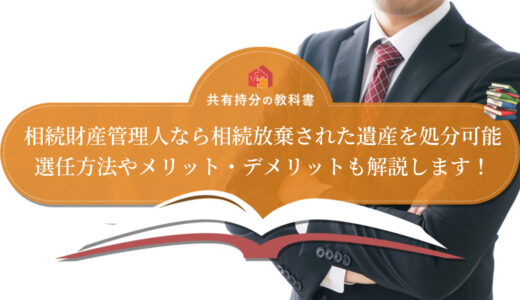 相続財産管理人とは?必要なケースや選任方法をわかりやすく解説
相続財産管理人とは?必要なケースや選任方法をわかりやすく解説
特別縁故者の条件
家庭裁判所が特別縁故者として認めるのは、次のいずれかに該当する場合です。
| 条件 | 典型例 |
|---|---|
| 被相続人と生計を同じくしていた者 | 内縁の妻、同居して家計を支えていた親族 |
| 被相続人の療養看護に努めた者 | 無償で介護や看病を続けていた親族・知人 |
| その他、被相続人と特別の縁故があった者 | 口約束で財産を譲ると約束されていた友人など |
実際には、次のようなケースがあります。
独身のAさん(共有持分1/2を所有)が亡くなり、配偶者や子どもなどの相続人がいなかったケースでは、長年介護をしていた弟の妻が家庭裁判所に申し立て、特別縁故者として持分の取得が認められました。
どの条件に当てはまるかは家庭裁判所が判断するため、申立てを行う際には弁護士や司法書士に相談すると安心です。
法定相続人も特別縁故者もいなければ、最終的に共有者へ帰属する
共有名義人が亡くなり、配偶者や子どもなどの法定相続人もおらず、特別縁故者にも該当する人がいない場合、法律上は残された共有持分が他の共有者に帰属します(民法255条)。
民法第255条
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
引用:e-Govポータル「民法第255条」
他共有者への帰属は、それぞれの持分割合の比率にしたがって分配されます。
Cが死亡したとき、Cの持分は「AとBの持分割合の比率(3:1)」で分割されます。
◆帰属後のAの持分割合
・1/5(Cの共有持分)×3/4 = 3/20
・3/5(Aの持分)+3/20 = 3/4
◆帰属後のBの持分割合
・1/5(Cの共有持分)×1/4 = 1/20
・1/5(Bの持分)+1/20 = 1/4
仮に不動産が2,000万円の価値だった場合、Aは持分3/4=1,500万円、Bは持分1/4=500万円を取得する計算になります。
ただし、実際に登記簿上の名義を移すには「相続財産管理人選任の申立」が必要です。申立てをしなければ、帰属しても登記ができず、不動産の売却や担保設定などの手続きが進められません。
「共有者への帰属」より「特別縁故者へ相続財産分与」が優先される判例がある
民法には、相続人がいなければ「共有者に帰属する」とする民法255条と「特別縁故者に分与できる」とする民法958条の3の両方が規定されています。
一方は「残りの共有者に移る」と定め、もう一方は「縁故者に分けられる」と定めているため、どちらを優先すべきかが問題となってきます。
平成元年11月24日の最高裁判例では、共有者への帰属よりも特別縁故者への財産分与が優先されると判断されました。つまり、内縁の妻や長年介護していた親族など特別縁故者がいる場合、まずはその人への分与が優先されます。
ただし、この判例には反対意見もあり、状況によって解釈が分かれる可能性も残されています。実際に申立てを考える場合は、弁護士などに相談するとよいでしょう。
共有名義人の片方が死亡した場合の相続手続きの流れ
共有持分を相続する手続きは、通常の不動産相続と大きな違いはありません。
ただし、共有不動産では新たに相続人が加わると、共有者の人数が増える可能性があります。
共有者が増えると、不動産を売却したり担保に入れたりする際に全員の同意が必要になり、話し合いがまとまらず手続きが進まないリスクがあります。
相続手続きの流れは大きく分けて次の5段階です。
- 遺言書の有無を確認する
- 相続人・財産を調査・確定する
- 遺産分割協議をする
- 相続登記をする
- 相続税の申告と納税をする
それぞれの手順について、詳しく解説します。
 共有持分の相続は「売却」でリスクを防げる!相続から売却までの流れを解説します
共有持分の相続は「売却」でリスクを防げる!相続から売却までの流れを解説します
遺言書の有無を確認する
まずは、遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書があれば、遺言書のとおりに遺産分割をおこないます。
遺言書には主に次の3種類があります。
| 種類 | 保管場所 | 特徴・確認方法 |
|---|---|---|
| 公正証書遺言 | 公証役場 | 公証人が作成するため有効性が高い。公証役場で検索できる。 |
| 自筆証書遺言 | 自宅・貸金庫・法務局 | 本人が作成。2020年以降は法務局の保管制度を利用でき、法務局で検索可能。 |
| 秘密証書遺言 | 自宅など | 本人が作成し封印。実務ではほとんど利用されず、発見が難しい。 |
実際に調べる際は、以下のような方法を取ります。
- 公証役場で検索する(公正証書遺言)
- 法務局で検索する(自筆証書遺言の保管制度を利用している場合)
- 自宅・貸金庫など本人が保管していそうな場所を探す
遺言書を見落とすと、後から相続がやり直しになるリスクがあります。必ず可能性のある場所を丁寧に確認しましょう。
相続人・財産を調査・確定する
遺言書の有無を確認したら「誰が相続人になるのか」「どんな財産や負債があるのか」を調べて確定します。
相続人の範囲を確定するためには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集めなければなりません。戸籍を集めることで、認知された子や養子など、隠れた相続人がいないかを確認できます。
財産については、プラスの財産とマイナスの財産の両方を把握しましょう。
| 財産の種類 | 確認方法 |
|---|---|
| 不動産 | 登記事項証明書・固定資産税評価証明書で確認 |
| 預貯金 | 銀行に残高証明書を請求 |
| 株式・投資信託 | 証券会社から取引報告書を取得 |
| 借金・ローン | 契約書・督促状・残高証明書などを確認 |
相続人や財産の調査を怠ると、後から「隠れた相続人がいた」「借金があった」と判明した場合、協議や相続税申告をやり直すリスクがあります。
とくに借金が見つかると、相続放棄や限定承認といった選択肢が取れなくなるおそれがあります。
◆限定承認:プラスの財産の範囲でのみ借金を返済する制度。
そのため、早い段階で調査を進めることが重要です。
調査は自分でも可能ですが、不動産登記は司法書士、相続人調査や紛争対応は弁護士、税金の確認は税理士といった専門家に依頼するとよいでしょう。
参照:裁判所「相続財産管理人の選任」
参照:国税庁「相続税の課税対象」
遺産分割協議をする
相続人が確定したら、法定相続人で遺産分割協議をおこないます。
遺産分割は、基本的には法定相続分や遺言書の内容に従って行います。
ただし、相続人全員の同意があれば異なる割合での分割も可能です。1人でも反対があると協議は成立しないため、全員の合意を得ることが欠かせません。
義務ではありませんが、遺産分割協議が完了したら「遺産分割協議書」を作成しておくとよいでしょう。
相続登記や銀行での預貯金払戻しなどの手続きにも必要になるだけでなく、後日、トラブルが発生した際も有効な証拠となります。
遺産分割協議書は相続人本人が作成することもできますが、記載ミスを防ぐために弁護士や司法書士に作成を依頼するのが一般的です。作成費用は法律事務所によってさまざまですが、おおむね5〜10万円程度で、遺産額によってはさらに高額になる場合があります。
なお、話し合いがまとまらない場合は「遺産分割調停」を家庭裁判所に申し立てることになります。
裁判ほど形式は厳しくなく、費用も比較的抑えられるため、まずは調停から利用するケースが多くみられます。
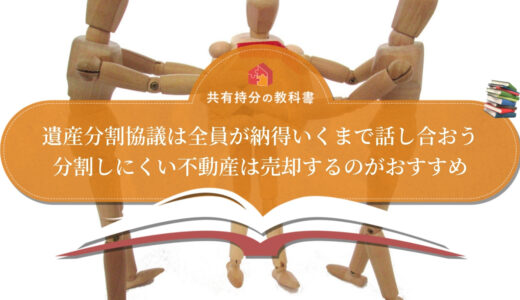 相続発生時における遺産分割協議の基礎知識と流れを解説!遺産分割は相続人全員で協議しよう!
相続発生時における遺産分割協議の基礎知識と流れを解説!遺産分割は相続人全員で協議しよう!
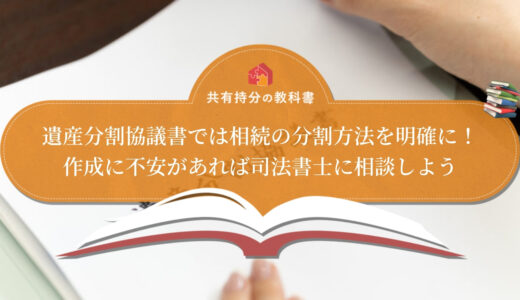 遺産分割協議書は相続人が作れる!ひな形通りの正しい書き方や作成依頼先も解説
遺産分割協議書は相続人が作れる!ひな形通りの正しい書き方や作成依頼先も解説
相続登記をする
共有持分の分割割合が決まったら、法務局で相続登記をおこないます。
相続登記に必要な書類の例は次のとおりです。
- 被相続人の戸籍謄本・住民票除票
- 相続人の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(または遺言書)
- 不動産の登記事項証明書
詳しい書類や記載例は関連記事を参考にしてください。
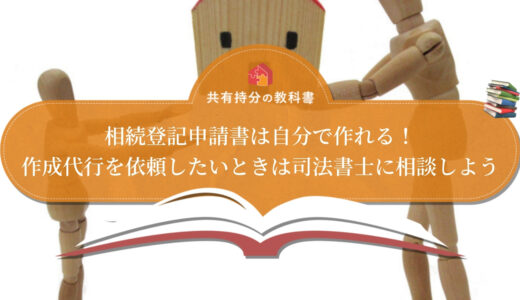 相続登記申請書の記載例をひな形を使って解説!必要書類や登記申請の方法も説明します
相続登記申請書の記載例をひな形を使って解説!必要書類や登記申請の方法も説明します
なお、2024年4月から相続登記は義務化され、相続開始を知った日から3年以内に登記をしないと10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
登記費用は「登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)」+「司法書士報酬(依頼する場合)」が基本です。
例えば遺産額が1,000万円の場合、自分で申請すれば登録免許税などで約5万円、司法書士に依頼した場合は6〜10万円が目安です。遺産額や法律事務所によって異なるため、事前に確認しましょう。
 共有持分の登記費用と節約方法を解説!登記の手順や必要書類も説明します
共有持分の登記費用と節約方法を解説!登記の手順や必要書類も説明します
相続税の申告と納付をする
相続税の申告と納税は、税務署でおこないます。
申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。期限を過ぎると、無申告加算税(原則15%〜20%)や延滞税が課されるため、早めの準備が必要です。
申告は、被相続人の住所地を管轄する税務署でおこないます。
この基礎控除の範囲内であれば、申告や納税は不要です。
相続税の具体的な計算方法や控除の特例については以下の記事を参考にしてください。
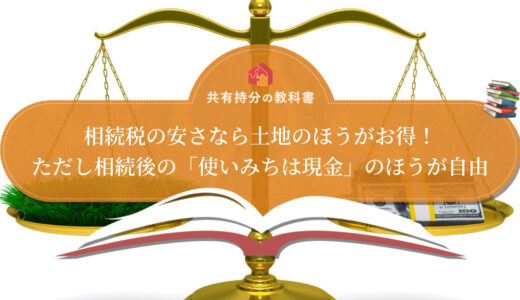 相続するなら土地と現金どっちがお得?それぞれのメリットとデメリットを解説
相続するなら土地と現金どっちがお得?それぞれのメリットとデメリットを解説
遺産分割が終わらないときは仮申告が必要
相続税の申告期限は10ヵ月以内ですが、遺産分割協議が長引くと期限までに分割が終わらないケースがあります。
その場合は、いったん法定相続分どおりに分割したと仮定して申告しましょう。仮申告後、遺産分割が確定したら実際の分割割合にそって追加納税や還付を行います。
また、3年以内に分割予定であることを記載した「3年内分割見込書」を提出しておけば、各種控除の特例を適用できます。
死亡した共有者に法定相続人がいない場合の手続きと流れ
法定相続人がいない場合、共有持分は「特別縁故者への相続財産分与」または「共有者への帰属」となります。
ただし、どちらの場合もまず「相続財産管理人選任の申立」が必要です。あ申立人となるのは、財産を取得しようとする特別縁故者や共有者です。
相続財産管理人を経由しなければ登記手続きができず、売却や担保設定などの活用も進められません。裁判所を通さずに直接取得することはできない点に注意しましょう。
全体の流れには時間がかかり、申立から持分の取得まで通常1年以上を要します。特に相続人の捜索は官報公告を通じて2〜6ヵ月程度かかるのが一般的です(事案によって短縮されるケースもあります)。
手続きの流れは大きく分けて次の3段階です。
- 家庭裁判所に「相続財産管理人選任」を申し立てる
- 相続財産管理人が債権者への支払いや相続人の捜索をおこなう
- 残った財産を特別縁故者または共有者が取得する
それぞれ詳しく解説します。
相続財産管理人選任を申し立てる
相続財産管理人の申立は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所でおこないます。
選任申立に必要な書類は、次のとおりです。
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 財産を証明する資料(不動産であれば不動産登記事項証明書)
- 利害関係を証明する資料
上記の資料と、裁判所のホームページでダウンロードできる相続財産管理人の選任の申立書を記入して提出します。
必要書類はケースによって異なる場合があるため、弁護士に相談しながら進めるとよいでしょう。
相続財産管理人選任の申立費用
相続財産管理人の申立にかかる費用は以下のとおりです。
- 申立費用:収入印紙800円
- 予納郵便切手:1,000円程度(裁判所による)
- 官報公告費用:4,230円
- 予納金:数十〜数百万円
予納金は、相続財産管理人の報酬や管理費用にあてる費用です。相続財産を処分しても不足する場合に備えて、不足分の費用を申立人があらかじめ納付します。
遺産から支払いができれば予納金は返金されますが、遺産が少ないと返金されず申立人の負担となる場合があります。事前に裁判所や弁護士に金額の目安を確認しておきましょう。
相続財産管理人が債権者への支払いや相続人の捜索をおこなう
家庭裁判所は申立を受けて相続財産管理人を選任します。相続財産管理人は弁護士や司法書士が選ばれるのが一般的です。
管理人は、被相続人の財産を管理し、債権者への支払いと相続人の捜索をおこないます。
相続人の捜索は官報公告を通じて複数回おこなわれ、一定期間経過しても相続人が現れなければ「相続人不存在」が確定します。
債権者への支払い後に残った共有持分を特別縁故者もしくは共有者が引き継ぐ
相続人の不存在が確定し、債権者への支払いも終了したら「特別縁故者に対する財産分与の審判」を家庭裁判所に申し立てます。
家庭裁判所が調査し、特別縁故者と認められれば、財産の一部または全部の取得が可能です。特別縁故者がいない場合や、分与後に財産が余った場合には、民法255条に基づき共有者に持分が帰属します。
ただし、いずれの場合も自動的に持分が移転するわけではありません。家庭裁判所への申立てや登記の手続きを経てはじめて正式に権利が移ります。
共有名義人の片方が死亡した場合に不動産を単独名義に変更する方法
共有名義だった不動産を相続した場合、複数人で持分を分け合う「共有状態」が続きます。
しかし、共有不動産は売却や担保設定の際に共有者全員の同意が必要で、手続きが進みにくいリスクがあります。また、相続人同士の考えが合わないと、売却や活用をめぐってトラブルに発展するおそれもあるでしょう。
そのため、将来的なトラブルや手続きの停滞を防ぐために、できるだけ早めに単独名義へ変更しておくことが望ましいといえます。
単独名義に変更する主な方法は次の3つです。
- 代償分割で他の相続人に代わりの財産を渡す
- 他の相続人から持分を買い取る
- 共有物分割請求を行う
それぞれの方法を詳しくみていきましょう。
代償分割で他の相続人にかわりとなる遺産を渡す
不動産は現金のように分けやすい財産ではないため、共有状態のまま相続すると将来のトラブルにつながりやすいです。そのため、単独名義にしたいときに活用される方法のひとつが「代償分割」です。
代償分割とは、不動産など分けにくい財産を相続人の1人が取得し、その代わりに他の相続人へ代償金を支払う方法です。
たとえば、父親と長男が1/2ずつ所有していた評価額4,000万円の不動産を相続するケースを考えてみましょう。父親の持分(2,000万円)と現金2,000万円を相続するのは、長男と次男の2人です。
長男が不動産を相続すると、長男は不動産4,000万円、次男は現金2,000万円しか取得できず不公平が生じます。
そこで長男が次男に1,000万円を支払えば、双方ともに最終的に3,000万円ずつ取得し、公平が保たれます。
このように代償分割は、不動産を第三者に売却せずに相続人の1人が単独所有できるというメリットがあります。住み慣れた家を残したい場合や、将来の売却を見据えて共有関係を避けたい場合に有効です。
一方で、代償金を支払う資金力がなければ実現できない点がデメリットです。
代償金は原則現金一括で支払いますが、相続人全員の合意があれば分割払いにすることも可能です。
なお、代償金を受け取った相続人には譲渡所得税がかかる可能性があります。居住用不動産の場合は「3,000万円特別控除」などの特例が使えるケースもあるため、税務面の確認も欠かせません。
相続人から持分を買い取る
単独名義にしたい人が、他の相続人から共有持分を「売買」という形で取得する方法もあります。
対価を支払うことで相手の同意を得やすく、円満に解決しやすい方法といえるでしょう。
代償分割が「遺産分割の一環」として代償金を支払うのに対し、こちらは相続人間での通常の売買契約となる点が異なります。
不動産の評価額が3,000万円で兄弟2人が1/2ずつ相続した場合、兄が弟から持分1/2(1,500万円相当)を買い取れば、兄の単独名義にまとめることができます。
この方法のメリットは、他の相続人が現金を得られるため合意が得やすく、トラブルが少ないことです。さらに、単独名義にしておけば将来の売却や担保設定がスムーズにできるため、資産活用の自由度も高まります。
一方で、買い取る側にまとまった資金が必要です。融資を受ける場合でも、金融機関の審査に通らなければ実行できません。
また、売却した相続人には譲渡所得税が課される可能性があります。取得費や特例の有無によって税額は変わるため、税務上の確認は必ず行いましょう。
共有物分割請求を行う
共有者同士の話し合いがまとまらない場合は、民法第258条(共有物分割請求)に基づき、裁判所に「共有物分割請求」の申し立てができます。
裁判所では、まず不動産を物理的に分ける「現物分割」が可能かを検討します。たとえば土地を分筆してそれぞれに所有させるなどですが、建物のように物理的に分けられないケースや、分筆で著しく価値が下がるケースも多くあります。
そのため、実務上は不動産を競売にかけて売却し、代金を持分割合に応じて分配する「換価分割」が命じられるのが一般的です。
裁判によって強制的に共有状態を解消することはできますが、必ずしも自分の望む形で解決できるとは限りません。競売になれば市場価格より低い金額で売却されるリスクが高く、資産価値の目減りにつながります。
また、弁護士費用や裁判にかかる時間的コストも発生するため、実務上は「最終手段」と位置づけられています。
共有物分割訴訟は、目安として数ヵ月から1年以上かかることが多く、時間と費用の負担が大きい点を覚悟する必要があるでしょう。
共有物分割請求は法律的な主張や裁判所への対応が必要になるため、実務上は弁護士に依頼するのが一般的です。
参照:民法第258条
共有名義人の片方が死亡した場合の注意点
共有名義人が亡くなると、残された相続人に持分が承継されます。一見シンプルに思えても、実際には思わぬトラブルやリスクが潜んでいます。
とくに注意すべきポイントは次の3つです。
- 知らない相手や関係の悪い相手と新たに共有関係になるリスクがある
- 相続登記を放置すると「数次相続」で共有者がどんどん増える
- 亡くなった共有者が住宅ローン契約者だった場合、残債や団信の影響を受ける
これらを理解しておくことで、将来のトラブルを防ぎやすくなります。
それぞれの注意点を詳しく解説します。
知らない相手・関係性の悪い相手と共有関係になる可能性がある
共有名義人が亡くなると、その持分は法定相続人に承継されます。相続人は法律で定められているため、疎遠な親族や関係性の悪い人と新たに共有関係になるリスクがあります。
たとえば、兄弟の一方が亡くなり、その子ども(甥や姪)や再婚相手の子が相続人となった場合、遺産分割協議や不動産の売却で協議する必要があるのです。
また、民法第251条により、共有物の処分や変更には共有者全員の同意が必要です。1人でも反対すれば売却や担保設定が進められず、話し合いがまとまらないリスクがあります。
このような事態を避けるため、遺言書の作成や生前贈与など、早めの対策を取っておくことが望ましいでしょう。
放置すると「数次相続」が発生し共有者が増える
数次相続とは、遺産分割や登記が終わる前に相続人の1人が亡くなり、その相続分がさらに次の相続人へ承継されることをいいます。
たとえば、父が亡くなったあとに母と子2人で共有していた不動産を、そのまま登記せずに放置して母が亡くなったケースを見てみましょう。
| 相続の段階 | 共有者 | 持分割合 |
|---|---|---|
| ①父死亡時 | 母・長男・次男 | 母1/2、長男1/4、次男1/4 |
| ②母死亡時 | 長男・次男 | 長男3/4、次男1/4 |
| ③長男死亡時(妻と子が相続した場合) | 長男の妻・子、次男 | 妻3/16、子3/16、次男1/4 |
このように相続を放置すると、世代交代のたびに共有者が増え、持分も細分化して複雑化します。
売却や担保設定などの合意がますます難しくなり、最悪の場合は不動産の利用や処分が困難な状態になってしまいます。
数次相続を防ぐには、できるだけ早めに遺産分割協議を行い、相続登記を済ませることが重要です。
なお、2024年4月から相続登記は義務化されており、放置すれば10万円以下の過料の対象となる可能性もあります。
共有者が住宅ローン・団信加入者だった場合の影響
共有者の1人が亡くなったときに住宅ローンを組んでいる場合、そのローン残債務も相続の対象となります。団体信用生命保険(団信)に加入していれば、死亡時に保険金でローンが完済されるため、相続人が返済義務を負うことはありません。
ただし、団信は契約者本人の死亡分しか保障されないため、ペアローンや連帯債務型ではもう一方の債務は残り、引き続き返済を続ける必要があります。
住宅ローンや団信の有無を確認するには、次のような方法があります。
- 不動産の登記簿を確認する
- 故人の自宅や書類から金融機関のローン契約を探す
- 借入先の金融機関に問い合わせる
また、団信に加入していなかった場合はローン全額が相続されます。その結果、不動産を相続したつもりが実際には住宅ローン残債の方が多く、マイナスの財産となるケースもあるため、必ず団信加入の有無や残高を確認しましょう。
共有名義不動産の相続トラブルを防ぐ方法
共有名義のまま相続すると、知らない相手との共有や数次相続による複雑化など、トラブルが生じやすくなります。
生前の準備や制度の活用によって、トラブルを未然に防ぎ、スムーズに相続を進めることが可能です。
共有名義不動産の相続トラブルを防ぐ主な方法は次のとおりです。
- 共有者に遺言書を作成してもらう
- 共有者から生前に持分の贈与や売却をしてもらう
- 家族信託を活用して管理・承継を明確化する
- 相続放棄をする
それぞれの方法について詳しく解説していきます。
共有者に遺言書を作成してもらう
共有名義不動産のトラブルを防ぐためには、生前に誰へ持分を承継させるかを明確にしておくことが大切です。遺言書を作成しておけば、共有持分を誰に相続させるかを指定できるため、相続人同士の争いを防ぐことができます。
たとえば、父親と長男で共有している不動産について「父の持分は長男に相続させ、次男には預貯金を相続させる」といった指定をしておくとよいでしょう。
遺言があれば遺産分割協議を経ずに、登記や名義変更などの手続きも円滑に進められます。
また、遺言書は方式を満たしていないと無効になるため、自筆証書遺言よりも公正証書遺言を選ぶ方が安全です。公正証書遺言なら公証人が作成するため形式不備の心配がなく、原本も公証役場で保管されるので紛失や改ざんのリスクを減らせます。
共有者から生前に持分の贈与や売却をしてもらい単独所有化しておく
生前のうちに共有持分を移転しておけば、相続後の複雑な共有関係を避けられます。
たとえば、父親と長男で不動産を共有している場合に、父が生前に自分の持分を長男へ贈与または売却しておけば、長男の単独所有とすることが可能です。
生前贈与で単独所有にしておけば、相続の段階で持分が分散せず、トラブル防止につながります。
ただし、生前贈与には次のような注意点があります。
- 贈与の場合、年間110万円を超えると贈与税がかかる
- 贈与を受けた相続人には「特別受益」として持ち戻しを主張されるリスクがあるため、遺言書の作成もあわせて行うのが望ましい
- 当事者の判断能力が低下(認知症など)すると契約自体が無効になる可能性がある
一方、売却であれば贈与税は発生しませんが、売却益が出た場合には譲渡所得税が課税されるため、利益が出れば確定申告が必要になります。購入時の取得費や特例の適用有無によって税額が変動する点にも注意が必要です。
このように、生前に持分を整理しておけば相続後の負担を大きく減らせますが、税務リスクや法的リスクも伴うため、税理士や弁護士、不動産に詳しい司法書士など専門家に相談しながら進めることが重要です。
家族信託を活用して管理・承継を明確化する
家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理・運用・処分を託す契約です。高齢者の認知症対策として利用されるケースが多いですが、相続対策にも有効です。
特に共有名義不動産では、将来の承継先をあらかじめ定めておけるため、数次相続による持分の細分化を防げます。
たとえば、父親と長男で不動産を共有している場合、次のように承継順序をあらかじめ決めることが可能です。
- 父が亡くなったときは、父の持分を母に承継させる
- 母が亡くなったときは、母の持分を長男に承継させる
このように指定しておけば、相続が重なるたびに共有者が増えて複雑化するのを防げます。
また、遺言と異なり、家族信託は「次の承継者」だけでなく「その次の承継者」まで指定できるため、より長期的に自分の意思を反映できます。
さらに、不動産を信託財産にする場合は「信託登記」を行う必要があるため、登記手続きも視野に入れて準備することが重要です。
一方で、契約内容の設計に高度な知識が必要で、対応できる専門家がまだ少ないのがデメリットです。信託契約を検討する際は、司法書士・弁護士・家族信託専門士など、実務に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。
他の財産も不要であれば相続時に相続放棄をする
他の財産も不要な場合は、相続放棄を選択するのも1つの方法です。
相続放棄とは、財産や借金を一切受け継がず放棄することを指します。
相続放棄をすれば、共有持分を含むすべての相続財産を引き継がずに済みます。そのため、共有持分を相続して他人と共有関係になるのを避けたい場合にも有効です。
ただし、相続放棄は共有持分だけを選んで放棄することはできず、預貯金などプラスの財産も含めて一切相続できなくなります。思わぬ不利益につながることもあるため、判断は慎重に行う必要があるでしょう。
また相続放棄は、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。期限を過ぎると単純承認(すべてを相続)したとみなされるため、早めの対応が求められます。
参照:裁判所「相続放棄の手続」
相続した後に不動産を手放したい場合の対処法
相続で不動産の共有持分を取得したものの、「使い道がなく負担になる」「他の共有者との関係が不安」といった理由で手放したいと考える人も少なくありません。
相続した後に共有持分を手放す主な方法は次の2つです。
- 共有持分を放棄する
- 不動産を第三者に売却する
次の項目から、それぞれの具体的な手続きと注意点を解説します。
共有持分を放棄する
遺産分割を終えて共有持分を取得したあとに、その持分だけを放棄する方法です。
持分放棄をすると、その持分は民法255条に基づき、他の共有者に帰属します。
法律上は他の共有者の同意は不要で、自分の判断だけで放棄できます。そのため、「持分はいらないが他の遺産は相続したい」という場合に有効です。
ただし、持分放棄は無償で行うため、処分しても対価は得られません。また、実務上は登記手続きで「贈与」や「譲渡」の形式をとる必要があり、登記申請自体は他の共有者と共同で行わなければなりません。
登録免許税も相続登記とは異なり、「固定資産税評価額×2%」が課税されます(相続登記は0.4%)。司法書士へ依頼する場合は、報酬を含めて数万円〜十数万円程度の出費が必要になるケースもあるため、費用負担が大きい場合は、売却など他の方法と比較して検討することも重要です。
不動産を第三者に売却する
共有持分を相続したあとに、第三者へ売却する方法もあります。
共有持分の処分は法律上自由であり、他の共有者の同意は不要のため、自分の意思だけで売却可能です。遺産分割を終えていれば、その後は単独で売却できます。
もっとも、共有持分は単独での利用価値が低いため、一般の不動産会社や個人が購入することはほとんどなく、買い手が限られます。
そのため、確実に売却したい場合は共有持分の専門買取業者に依頼するのが現実的です。
共有持分を専門業者に売却するメリットは次のとおりです。
- スピーディーかつ確実に売却できる
- 仲介手数料がかからず費用負担を抑えられる
- 契約不適合責任を免責してもらえるケースが多い
- 周囲に知られずに売却でき、プライバシーが守られる
一方で、買取り業者に売却する場合、市場価格の2〜5割程度にとどまるのが一般的です。
とはいえ、持分を確実に売却したい人にとっては、有効な選択肢といえるでしょう。
弊社クランピーリアルエステートは、共有持分の買取に特化した不動産会社です。スピーディーかつ安全に現金化できるほか、弁護士や税理士とも提携しており、法務・税務面の安心サポートも可能です。
「共有関係を早く解消したい」「煩雑な手続きを避けたい」という方はぜひご相談ください。
まとめ
共有名義者の片方が死亡した場合、まずは相続人が誰で何人いるのかを確認することが大切です。相続人がいなければ、その持分は生きている共有者に帰属しますが、相続人がいる場合は新たな共有関係が発生します。
共有持分を相続すると、疎遠な親族と共有関係になるリスクや、数次相続による持分の細分化、住宅ローンや税金の負担など、さまざまな問題が生じやすくなります。
こうしたリスクを防ぐには、遺言や生前贈与、家族信託といった生前対策を講じておくことが有効です。
すでに共有持分を相続した後でも、持分放棄や売却といった方法で共有状態を解消できます。
特に持分売却を選ぶ場合は、共有持分の買取に特化した専門業者に相談することで、スピーディーかつ確実に現金化でき、複雑な共有関係から解放されるでしょう。
弊社クランピーリアルエステートは、共有持分の買取に特化し、弁護士や税理士と連携したサポートを提供しています。「共有関係を早く解消したい」「相続後のトラブルを避けたい」とお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
共有者の死亡に関してよくある質問
相続人の一部と連絡が取れない場合、遺産分割協議を進めることはできません。
その場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立て、代理人を通じて遺産分割協議を行うことが可能です。不在者財産管理人は不在者の財産を管理し、裁判所の許可を得て協議に参加する役割を担います。
連絡が取れない相続人がいるからといって放置せず、裁判所の制度を利用して早めに対応することが大切です。
なお、不在者財産管理人の選任には時間と数万円~数十万円程度の費用がかかります。選任までに数か月を要するケースもあるため、余裕をもって家庭裁判所へ相談しておくと安心です。
相続権の有無は「死亡時点で婚姻関係があるかどうか」で決まります。
- 婚姻中に夫(または妻)が亡くなった場合:配偶者として法定相続人となり、相続権があります
- 離婚成立後に元配偶者が亡くなった場合:すでに配偶者ではないため、相続権はありません
ただし、元配偶者との間に生まれた子どもには親子関係が存続するため、子どもは法定相続人となります。
なお、婚姻届を提出していない「内縁関係(事実婚)」の配偶者にも相続権は認められていません。もっとも、元配偶者や内縁の配偶者に財産を残したい場合は、遺言書による遺贈で対応することが可能です。
参照:民法887条


