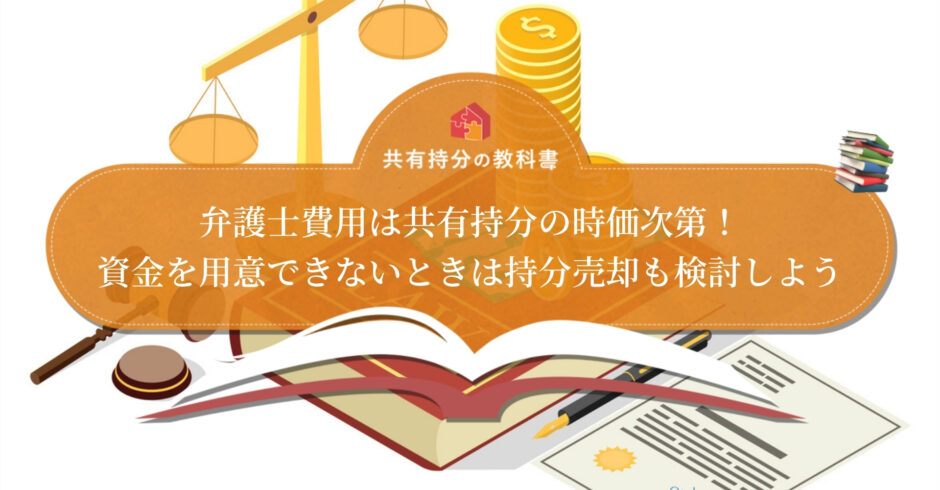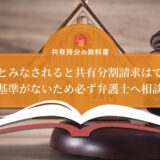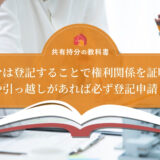共有不動産を分割し、共有状態を解消する方法として「共有物分割請求」があります。協議や裁判によって、他共有者に共有不動産の分割を求める手続きです。
共有物分割請求には法律の知識が必要なので、手続きを弁護士に代行してもらうのが一般的です。
弁護士費用は各弁護士事務所によって異なりますが、主に「共有持分の時価1/3から報酬金を算出するパターン」と「共有持分の時価5~10%を報酬金とするパターン」があります。
具体的な計算式は各弁護士事務所が独自に決めているので、依頼前にしっかりと見積もりを出してもらいましょう。
また、弁護士用を用意できない場合、共有物分割請求ではなく「自分の共有持分を売却する」という方法もおすすめです。専門買取業者なら、高額買取と最短数日での現金化も可能なので、無料査定を受けて検討してみるとよいでしょう。
>>【最短12時間で価格がわかる!】共有持分の買取査定窓口はこちら

- 共有物分割請求の弁護士費用は、共有持分の時価から算出できる。
- 着手金や相談無料の弁護士に依頼すれば、弁護士費用を抑えられる。
- 弁護士費用の捻出が難しいときは、共有持分を売却して共有関係を解消するのがおすすめ。
共有物分割請求は訴訟に発展すると弁護士費用も高くなる
共有物分割請求とは、共有者に対して、共有不動産を分割するよう求める行為です。
共有物分割請求の弁護士費用は、請求が訴訟に発展すると高くなります。
共有物分割請求は訴訟に発展するまで、次のように進行します。
- 共有者で協議をする
- 協議で解決できなければ調停を申し立てる
- 協議や調停で解決できなければ訴訟を起こす
調停はせず、協議の後すぐに訴訟を起こすことも可能です。
協議や調停によって解決できれば、弁護士費用は安く済みます。
ただし、弁護士費用の内訳は弁護士事務所によって異なるため、注意が必要です。
弁護士に相談・依頼する際は、実費なども含めた合計の支払い額をしっかりと確認するのをおすすめします。訴訟後に、想定より弁護士費用が大幅に高額となってしまうのを防ぐためです。
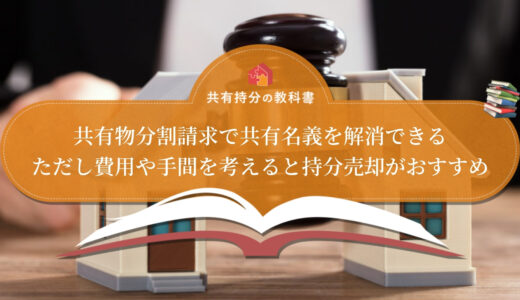 共有物分割請求とは?共有物の分割方法や訴訟の手順・費用を詳しく解説
共有物分割請求とは?共有物の分割方法や訴訟の手順・費用を詳しく解説
協議や調停で解決すると弁護士費用は2/3程度で済む
共有物分割請求が協議や調停の段階で解決すると、弁護士費用は訴訟に発展したときの2/3程度で済むことが一般的です。
例えば、訴訟に発展した場合の弁護士費用が50万円だとしたら、協議や調停の段階で解決できたときの弁護士費用は約35万円となります。
協議や調停は訴訟よりも手続きが少ないため、弁護士費用も安くなるのです。
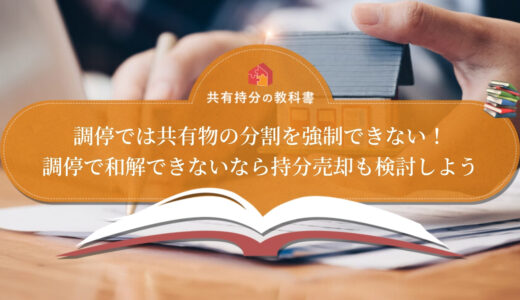 調停だけでは解決されない?共有物分割請求以外に共有状態を解消する方法も紹介
調停だけでは解決されない?共有物分割請求以外に共有状態を解消する方法も紹介
話し合いや調停は弁護士に依頼すべき?
協議や調停は、弁護士に依頼しなくても自分自身でおこなえます。
しかし、実際は弁護士に依頼するのが一般的です。
共有物の分割に反対している共有者がいる場合、法律知識と客観的な視点で交渉できる弁護士が間に入ると、協議がスムーズに進みます。共有者が行方不明の場合も、弁護士なら戸籍調査などが可能です。
調停は、裁判所に選出された調停員を挟んだ話し合いです。調停でも、法的根拠に基づいた主張ができた方が有利になります。
これらのことから、交渉や調停であっても自分でおこなうより弁護士へ依頼したほうがよいでしょう。
ただし、調停の段階でも訴訟と同じ費用がかかる弁護士事務所もあるので、費用はしっかりと確認しておきましょう。
弁護士費用の内訳
弁護士費用の内訳は、基本的に以下のとおりです。
- 相談料・・・弁護士に依頼の相談をする費用。
- 着手金・・・弁護士が依頼を引き受ける際の費用。結果に関わらず必ず発生する。
- 報酬金・・・案件の成功に応じて発生する費用。
- 実費・・・収入印紙代、郵便切手代、交通費、通信費、宿泊費など弁護士が依頼を解決する際に発生する費用。
相談料の相場は1時間あたり1万円ですが、無料で相談を受け付けている弁護士事務所も多くあります。
実費は後に大きな出費となるケースもあるので、依頼する際に弁護士とよく話し合っておきましょう。
例えば、移動の際は電車を利用するかタクシーを利用するか、宿泊での出張が伴うなら宿泊施設はどこを利用するかなどを、あらかじめ確認しておくことが大切です。
共有物分割請求にかかる弁護士費用の算出方法は2パターン
共有物分割請求にかかる弁護士費用は共有持分の時価に比例するため、相場を一概にはいえません。
ただし、弁護士事務所が設定する着手金と報酬金の算出方法は、2つのパターンにわけられます。
算出方法を明示している弁護士事務所がほとんどなので、共有持分の時価がわかればおよその金額が算出できます。
共有物分割請求における、着手金と報酬金の算出方法をそれぞれ詳しく説明します。
共有持分の時価1/3を経済的利益の額として報酬金を算出するパターン
まずは、共有持分の時価1/3を経済的利益の額として算出するパターンです。
経済的利益とは依頼した案件が解決した際に、依頼者が得られる経済的な利益です。これをお金に換算して計算します。
このパターンでは、着手金も経済的利益に比例するのが一般的です。
経済的利益の額によって、以下のよう算出表を定めている弁護士事務所が多いです。
| 経済的利益 | 着手金 | 成功報酬 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 8% | 16% |
| 300万円を超え3,000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18 万円 |
| 3,000万円を超え3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
| 3億円を超える | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
例えば共有持分の時価が300万円の場合、経済的利益の額は100万円です。そして着手金が経済的利益の8%、成功報酬は16%としている弁護士事務所に依頼をした場合は、以下の算出方法となります。
・報酬金=100万円(経済的利益)×16%(0.16)=16万円
上記の着手金と報酬金に加えて、実費や相談料がかかります。
共有持分の時価5~10%を報酬金とするパターン
次に、共有持分の時価5~10%を報酬金として算出するパターンです。共有持分の時価1/3で計算しない代わりに、金額によるパーセンテージの変動はありません。
このパターンでは、着手金の金額は30万円に設定している弁護士事務所が多いです。
前の項目と同様に時価が300万円である共有持分の分割請求を、着手金が30万円、経済的利益の5%を報酬金としている弁護士事務所に依頼した場合の弁護士費用を算出してみます。
・報酬金=300万円(共有持分の時価)×5%(0.05)=15万円
着手金と報酬金に加えて、実費や相談料がかかります。
共有物分割請求における弁護士費用の具体例
すでに解説したとおり、共有物分割請求における弁護士費用の算出方法は次の2パターンです。
B:共有持分の時価5~10%を報酬金とするパターン
300万円以上の共有持分なら、どちらの算出方法でも総額はほとんど変りません。
具体的な金額をあてはめて、実際にどのくらいの費用になるか見ていきましょう。
共有持分の時価が1,000万円の場合の算出方法
【Aパターン】
着手金=333万(経済的利益)×5%+9万≒26万円
報酬金=333万(経済的利益)×10%+18万≒51万円
着手金+報酬金=77万円
【Bパターン】
着手金=30万円
報酬金=1,000万(共有持分の時価)×5%=50万円
着手金+報酬金=80万円
共有持分の時価が3,000万円の場合の算出方法
【Aパターン】
着手金=1,000万(経済的利益)×5%+9万=59万円
報酬金=1,000万(経済的利益)×10%+18万=118万円
着手金+報酬金=177万円
【Bパターン】
着手金=30万円
報酬金=3,000万(共有持分の時価)×5%=150万円
着手金+報酬金=180万円
共有持分の時価が5,000万円の場合の算出方法
【Aパターン】
着手金=1,666万(経済的利益)×5%+9万=92万
報酬金=1,666万(経済的利益)×10%+18万=185万
着手金+報酬金=277万円
【Bパターン】
着手金=30万円
報酬金=5,000万(共有持分の時価)×5%=250万
着手金+報酬金=280万円
訴訟が失敗した際も着手金はかかるので注意
具体的な計算例を見てわかるように、AとBどちらの方法で算出しても合計金額に大きな差異はありません。
注意点として、訴訟が失敗した際も着手金はかかることは覚えておきましょう。
そのため、共有持分の時価に比例して着手金が高くなるAより、着手金が固定であるBの方法を採用している弁護士事務所の方が、訴訟失敗時のコストを下げられる場合があります。
共有物分割請求で弁護士費用を抑える方法
共有物分割請求における弁護士費用の算出方法は、前の項目で解説したとおりです。
ただし、着手金や経済的利益における報酬金の割合などは、弁護士事務所が自由に決めることができます。
そのため、着手金の安い弁護士事務所や相談が無料の弁護士事務所を選べば、弁護士費用を抑えられます。
また、司法書士への依頼や本人訴訟でも、弁護士費用を抑えることが可能です。
もしも経済的な事情で弁護士に依頼が難しい場合は、法テラスの費用立て替え制度を利用するのもよいでしょう。
次の項目から、弁護士費用を抑える方法を詳しくお伝えします。
相談無料や着手金が安い弁護士に依頼する
着手金は、弁護士事務所がそれぞれ設定できます。
そのため、着手金が安い弁護士事務所に依頼をすれば弁護士費用を抑えられます。
また、報酬金の割合を低く設定している弁護士事務所を選ぶのも、弁護士費用を抑える方法の1つです。
初回の相談は無料でおこなっている弁護士事務所も多くあるので、そのような弁護士事務所に依頼するのもよいでしょう。
着手金などの金額は、弁護士事務所のホームページで確認できます。
ホームページに金額が載っていない場合は、弁護士事務所に直接問い合わせてみましょう
法テラスの費用立て替え制度を利用する
法テラスは、国民が法的支援を受けやすいように国が設立した機関です。
法テラスでは、法的トラブルに関する相談を無料で受け付けています。
また法テラスには、経済的事情で弁護士へ依頼するのが難しい方へ向けた「費用立て替え制度」があります。
- 収入等が一定額以下であること
- 勝訴の見込みがないとは言えないこと
- 民事法律扶助の趣旨に適すること
上記の法テラスが定めた基準を満たせば弁護士費用を立替えてもらうことができ、その後分割で法テラスへ返していきます。
さらに法テラスでは、電話やオンラインでの相談も受け付けているので、活用するとよいでしょう。
参照:参照:法テラス
司法書士に依頼する
共有物分割請求は、弁護士ではなく司法書士にも依頼ができます。
司法書士への依頼費用は、弁護士よりも安いことが一般的です。
ただし、司法書士は140万円を超える案件を扱うことが法律で禁止されています。
そのため、共有持分の時価が140万円を超える場合は、司法書士ではなく弁護士に依頼しましょう。
本人訴訟を検討する
本人訴訟とは、弁護士に依頼せず自分で裁判の手続きをおこなうことです。
本人訴訟であれば、弁護士費用をかけずに共有物分割請求ができます。
請求金額が弁護士費用よりも低い見込みの場合などに、よく使われる手段です。
ただし、訴訟は法的根拠に基づく主張が有利なのが一般的です。そのため、相手に弁護士がついている場合の本人訴訟は、法的知識がないと非常に不利となるので注意しましょう。
共有物分割請求以外で共有関係を解消する方法
共有物分割請求は、弁護士に依頼しないと不利になることが多かったり、状況によっては権利濫用が適用されて棄却されることもあります。
そうなると共有物の分割ができないどころか、弁護士費用が無駄になることも考えられます。
そのため、共有物分割請求ではなく、他の方法で共有関係を解消でないかも検討してみるとよいでしょう。
費用をほとんどかけずにおこなえる方法や、他共有者の同意がなくても実行可能な方法もあります。
この項目では、共有物分割請求以外で共有関係を解消する方法をお伝えします。
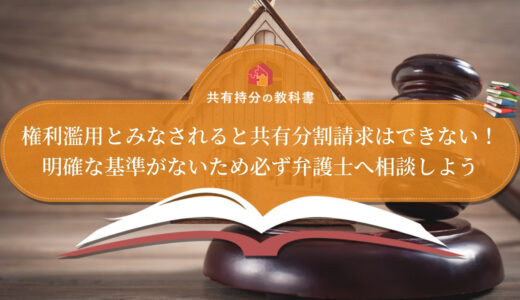 【共有物分割請求が権利濫用となるケース】棄却されたときの対処法も解説
【共有物分割請求が権利濫用となるケース】棄却されたときの対処法も解説
他共有者に共有持分を買取ってもらう
他共有者に共有持分を買取ってもらうことで、共有関係を解消できます。
他共有者への交渉が必要ですが、他共有者が共有不動産を利用している場合などは交渉に応じてくれるケースも多いです。
ただし、共有者同士の買取請求に強制力はなく、他共有者が共有不動産を利用しているからと無理に買取らせることはできないので注意しましょう。
他共有者が買取に同意した場合は、自由に価格設定ができます。
相場よりも大幅に低い金額で売買すると売主から買主へ譲渡されたとみなされる可能性があるので、価格設定は相場を参考にして大幅な差異がないようにするとよいでしょう。
他共有者の共有持分を買取って不動産全体を売却する
他共有者から共有持分を買取って、単独不動産として売却する方法があります。
誰も共有不動産を利用していない場合に、交渉が成立しやすいです。
共有持分を買取るための資金が必要になりますが、単独不動産として売却できれば十分に回収できます。
また、共有不動産が利用できる状態であれば、住居や駐車場などとして貸出して利益を得るのもよいでしょう。
共有持分のみを売却する
自分の共有持分のみであれば、他共有者の同意なく売却ができます。
共有者が共有不動産を手放すことを拒否したり、買取請求にも応じてもらえない場合におすすめの手段です。
ただし、共有持分のみの売却は不動産全体の売却よりも、大幅に価格が下がってしまうことがほとんどです。
また共有持分はそのままでの活用が難しく、買取をしていない不動産業者も多くあります。
そこで、共有持分専門の買取業者に買取を依頼するのがおすすめです。
共有持分専門の買取業者は、共有持分を買取った後に収益化する手段を持っており、共有持分のみでも相場と変わらない値段での買取が可能です。
また弁護士と提携している専門業者もあります。
そのような業者は、手放すことを反対している共有者へも法的根拠に基づいて買取の説得ができます。
そのため、共有物分割請求が棄却されたような事情のある共有持分でも、積極的に買取しているケースも多いです。
無料査定をおこなっている業者も多くあるので、まずは相談してみるとよいでしょう。
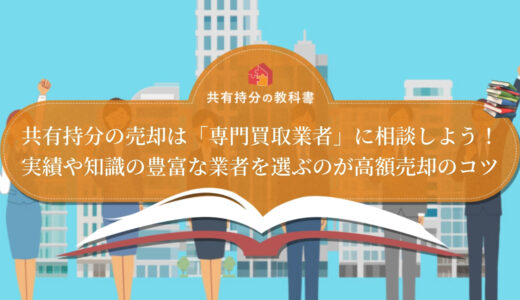 【共有持分の買取業者おすすめ27選!】共有名義不動産が高額買取業者の特徴と悪質業者の見極めポイント!
【共有持分の買取業者おすすめ27選!】共有名義不動産が高額買取業者の特徴と悪質業者の見極めポイント!
共有持分を放棄する
共有持分を放棄することでも、共有関係を解消できます。
共有持分の放棄は他共有者の同意なくできますが、共有持分を無償で手放すことになります。
また、放棄した持分は他共有者へ持分割合に応じて分配されるため、特定の共有者に多く譲ったり第三者に共有持分を譲ることはできません。
そのため共有持分の対価を得たい場合や、特定の人に共有持分を譲りたいときは放棄以外の方法を選択するのがよいでしょう。
また共有持分の放棄を完了させるための登記は、他共有者の協力が必要です。
共有持分の放棄については、以下の記事で詳しく説明していますので参考にしてください。
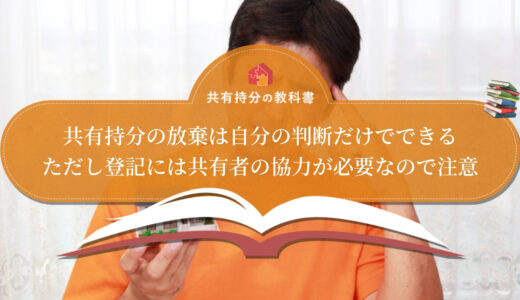 共有持分は放棄できる!放棄の手順や放棄後の登記も詳しく解説します
共有持分は放棄できる!放棄の手順や放棄後の登記も詳しく解説します
共有持分の時価を調べてから弁護士の無料相談を受けてみよう
共有物分割請求における弁護士費用は、共有持分の時価を把握することでおよその金額が算出できます。
ただし、弁護士事務所によって着手金が異なったり、交渉内容によっては実費がかさむこともあるので注意が必要です。
弁護士費用を事前に知りたいときは、共有持分の時価を調べて無料相談をしている弁護士事務所に相談するのがよいでしょう。
また不動産業者と提携している弁護士事務所であれば、時価の算出手段も持ち合わせていることが多いのでおすすめです。
また、共有持分の売却や放棄であれば、ほとんど費用をかけずに共有関係を解消できます。
共有持分をすぐに現金化することもできるので、まずは共有持分専門の買取業者に査定を依頼するのがおすすめです。
共有物分割請求についてよくある質問
共有持分をもつ人が、他の共有者に対して「共有物の分割」を求める行為です。共有物分割請求は拒否できないため、だれかが請求したら必ず分割に向けた話し合いをする必要があります。
共有不動産を売却して売却益を分割する「換価分割」や、共有者間で持分売買をおこなう「代償分割」のほか、不動産を切り分けて単独名義にする「現物分割」があります。
弁護士によって独自に料金体系を決めているため、どの弁護士に依頼するかにもよります。基本的には「共有持分の時価1/3から報酬金を算出するパターン」と「共有持分の時価5~10%を報酬金とするパターン」のどちらかであることが一般的です。
共有持分の時価が140万円以下であれば、弁護士より費用相場の低い司法書士に相談することも可能です。また、法律知識は必要になりますが、弁護士を利用せずに自分で請求・訴訟の手続きをおこなうこともできます。
自分の共有持分を売却すれば、すぐに共有関係を解消できます。とくに、共有持分専門の買取業者であれば、高額かつ最短数日のスピード買取も可能です。また、弁護士と連携した買取業者なら、共有物分割請求も含めた総合的なアドバイスを聞けるのでおすすめです。→弁護士と連携した買取業者はこちら