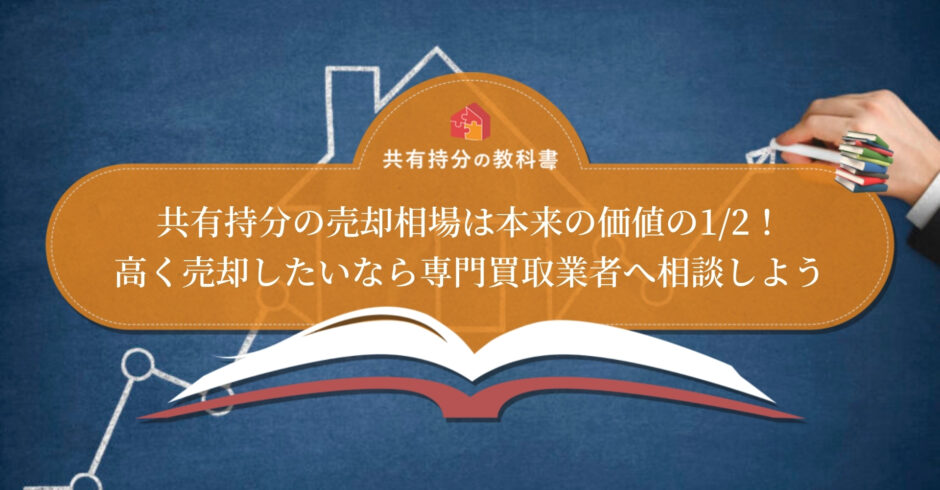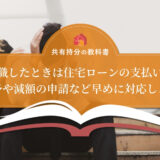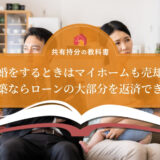共有持分の売却を検討している人にとって、1番気になるのは「どれくらいの価格で売れるのか」でしょう。
しかし、共有持分の売却相場は「不動産全体の価格×持分割合×1/2」が一般的とされています。なぜなら、需要が少ないため、市場価値も低くなってしまうからです。
共有持分をできるだけ高く売りたいなら、共有持分専門の買取業者に買取してもらう方法が一番です。
共有持分専門の買取業者は、多くの法律知識といままで共有持分を取り扱ってきた経験・ノウハウがあります。
共有持分の売却を検討しているなら、まずは以下のフォームから「あなたの共有持分がいくらで売れるか?」を無料で査定してみましょう。
共有持分の売却相場は市場価格よりも安くなるのが一般的!「不動産全体の価格×持分割合×1/2」が目安と考えておこう
共有持分の売却相場は、市場価格よりも安くなるのが一般的です。共有不動産の状態や立地、築年数などによって実際の売却金額は変わりますが、あくまで目安としては「不動産全体の価格×持分割合×1/2」が共有持分の売却相場になるとされています。
持分割合とは、不動産全体に対して共有持分がどれほどの割合になるかを表すものです。
たとえば、5,000万円の共有不動産に対して、持分割合1/5の共有持分をもっていたとします。
この場合で本来の価値を考慮すれば、共有持分は1,000万円で売れると考えるかもしれません。しかし、売却相場では「5,000万円×1/5×1/2=500万円」となります。
なお、売却相場はあくまで目安であって、絶対的な基準ではありません。「共有持分の売却相場は低くなる」と解説しましたが、それはあくまでも傾向であり、本来の価値以上で売却できる可能性もあります。
面積や築年数、周辺環境などの条件がよい不動産であれば、共有持分であっても高値で売却できるケースもあります。また、共有者との権利調整や売却相手との価格交渉といった工夫をすることでも、高値売却につながることも少なくありません。
共有持分の売却を検討している場合、売却相場を踏まえたうえで、より高値で売却するための工夫ができないかを考えておくのも良いでしょう。
共有持分の売却相場が市場価格よりも安くなりやすい理由
共有持分の売却相場が市場価格よりも安くなりやすい理由は、共有持分の需要が少ないことにあります。さらに具体的にいえば、下記のデメリットがあるためです。
- 共有持分だけを購入しても不動産全体を自由に活用できない
- 他の共有者とのトラブルに巻き込まれる可能性がある
ここからは、共有持分の売却相場が市場価格よりも安くなりやすい理由について、それぞれ解説していきます。
共有持分だけを購入しても不動産全体を自由に活用できない
不動産を共有している場合、共有者全員にその不動産の所有権がある状態といえます。そのため、共有持分を購入した後に買い手が単独で共有不動産を活用することはできません。
なお、共有不動産に関する行為は以下の種類があり、共有持分を所有している人が単独で行えるのは「保存行為」のみです。
| 使用方法 | 使用例 |
|---|---|
|
変更行為 処分行為 |
・不動産全体の売却 ・不動産の建て替え ・不動産の解体 など |
| 管理行為 |
・賃貸借契約 ・賃料改定 ・大規模修繕 など |
| 保存行為 |
・部分的な修繕 ・法定相続 ・不法占拠者に対する明け渡し請求 など |
たとえば、建物の部分的な修繕や相続登記であれば、不動産の共有者であれば誰でも単独で行えます。しかし、不動産全体の売却や建て替え、賃料の改定といった行為には、ほかの共有者からの同意が必須になります。
通常の不動産とは異なり、単独で行えることが限られているため、共有持分の需要は低くなりやすく、売却相場も安くなる傾向があるのです。
他の共有者とのトラブルに巻き込まれる可能性がある
共有不動産を所有している場合、不動産の使用方法や修繕、賃貸借契約など、さまざまな場面で共有者たちと話し合いをしなければなりません。その際には、他の共有者とのトラブルに巻き込まれてしまう可能性もあります。
たとえば、投資家が賃貸収入を得るために共有持分を取得しても、共有不動産を貸出すには他の共有者の同意が必要です。また、得られた賃貸収入も、共有者全員で分配する必要があります。
この際に、「共有不動産を貸すことに同意がなかなか得られない」「賃貸収入の配分で揉めてしまった」といったトラブルが起きる可能性もあるのです。
場合によっては、「収益を出すために共有持分を購入したのに、利益が全く得られなかった」というケースにもなりかねません。このようなリスクも考慮されやすく、共有持分の需要は下がりやすく、売却相場も安くなる傾向があります。
共有持分の売却価格を決める要因
「共有持分を売却相場より高く売りたい」「相場よりも安値になるのは避けたい」のように考えている場合、共有持分の売却価格を決める要因を理解しておくのもよいでしょう。
売却価格を決める要因を把握しておくことで、売却予定の共有持分がどのくらいで売れるのかを予測できます。売却価格の予測が立てば、価格交渉もしやすいでしょう。
共有持分の売却価格を決める要因としては下記が挙げられます。
- 共有不動産全体の市場価格
- 共有持分の割合
- 売却する持分が「土地」か「建物」か
- 隣接地との境界
- 住宅ローンの残債
- 「事故物件」「再建築不可物件」といった訳あり物件ではないか
- 共有者や賃借人との権利トラブル
- 共有者の所在把握
次の項目から、共有持分の売却価格を決める要因を解説していきます。
共有不動産全体の市場価格
共有している不動産全体がいくらになるのか調べなければ、共有持分の価値もわかりません。そのため、共有持分の売却相場を調べる際にも、所有している共有不動産全体の市場価格を調べておきましょう。
不動産の市場価格を調べるには、同じ地域の不動産売買情報を見るとよいでしょう。不動産の情報サイトで、近隣地域にある似た条件の不動産を見れば、おおよその市場価格もつかめます。
また、固定資産税評価額や公示地価など、国や自治体が使う公的な価格データもあります。
くわしくは、下記の関連記事を参考にしてください。
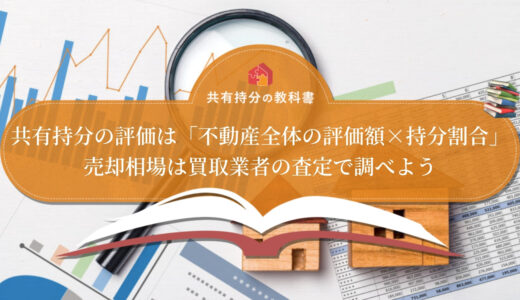 【共有持分の価格を知ろう】共有不動産の評価基準を徹底的に解説します!
【共有持分の価格を知ろう】共有不動産の評価基準を徹底的に解説します!
共有持分の割合
不動産全体の市場価格を持分割合で割れば、共有持分の「本来の価値」がわかります。
しかし、ここで注意すべきなのは、不動産に対して可能な行為が持分割合によって変わるという点です。
共有不動産に対する行為は、持分割合によって「保存行為」「管理行為」「変更行為」にわけられます。
| 行為の種類 | 必要な持分割合 | 具体的な例 |
|---|---|---|
| 保存行為 | 共有持分を少しでも持っていれば可能 | ・不動産の修繕 ・不法占拠者への明け渡し請求 |
| 管理行為 | 持分割合の過半数 | ・短期の賃貸借契約 ・不動産の使用方法の決定 |
| 変更行為 | 持分割合の全体(共有者全員) | ・建物の新築や取り壊し ・長期の賃貸借契約 |
持分割合の過半数をもっていれば、不動産に対して可能な行為が増えるため、共有不動産においての権限が強くなるといえるでしょう。
そのため、持分割合が少ないほど売却価格は下がりやすく、反対に持分割合が多いほど売却価格は高くなる傾向にあります。
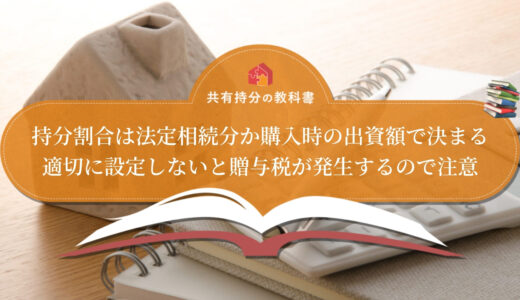 共有持分の割合はどう決まる?計算方法や持分割合に応じてできることを詳しく解説します
共有持分の割合はどう決まる?計算方法や持分割合に応じてできることを詳しく解説します
売却する持分が「土地」か「建物」か
売却する持分が土地と建物のどちらなのかも、売却価格に影響があります。
建物は経年劣化によって価値も下がりやすいので、将来的に見込まれる利益は少ないといえます。一方、土地も価格の変動はありますが、建物と比べれば緩やかです。
不動産を長期的に運用する場合、価値の下がりにくい土地の方が建物よりも有利になるのが一般的です。
そのため、共有持分の売却価格に関しても、土地は本来の価値より安くなりにくい傾向にあります。
隣接地との境界
隣接地との境界が明確になっているかどうかも、共有持分の売却価格を決める大きな要因です。
登記簿上の境界と、土地所有者の認識している境界がずれているケースは、それほど珍しくありません。測量したのが数十年も昔で、古い測量技術で境界を決めていることで、実際の面積と権利上の面積が大きく違う場合もあります。
土地の共有持分を売却するときは、必要に応じて土地の測量や境界の確定を土地家屋調査士に依頼しましょう。
住宅ローンの残債
住宅ローンの残債が残っている不動産は、抵当権が設定されています。返済が滞れば、差し押さえを受けて競売にかけられてしまうでしょう。
自分とは別の共有者が返済を延滞させてしまい、差し押さえになってしまうというケースも考えられます。
共有持分を購入しても、差し押さえられると損失にしかなりません。そのため、住宅ローンのある不動産は需要が低く、市場価値も下がってしまいます。
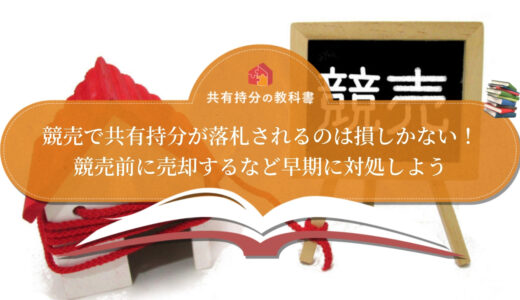 他共有者の共有持分が「競売となったとき」の5つの解決法|競売に陥る前にできることも解説します
他共有者の共有持分が「競売となったとき」の5つの解決法|競売に陥る前にできることも解説します
「事故物件」「再建築不可物件」といった訳あり物件ではないか
事故物件や再建築不可物件など、いわゆる「訳あり物件」といわれるような不動産は、市場価値も大きく下がります。
訳あり物件はおおまかに4種類あり、次のように分類できます。
| 心理的瑕疵 |
・事故や事件(火災や自殺など) ・心霊現象 ・古くからの言い伝え |
|---|---|
| 物理的瑕疵 |
・建物のひび割れ ・シロアリ被害 ・地盤沈下や液状化 |
| 環境的瑕疵 |
・暴力団施設 ・墓地 ・ゴミ処理場 |
| 法的瑕疵 |
・再建築不可物件 ・旧耐震物件 ・その他の違法建築 |
なんらかの瑕疵がある物件は、市場価値も低くなってしまいます。そのため、訳あり物件の共有持分の場合は、市場価格よりもさらに売却価格が下がりやすくなります。
共有者や賃借人との権利トラブル
共有持分を売却する時点で、なんらかの権利トラブルを抱えている物件は市場価値も下がりやすいです。
共有者と共有不動産の使用方法でもめている場合や、賃借人と賃料の支払いでもめている場合など、トラブルの起こっている物件を進んで買いたがる人は多くないでしょう。共有者や賃借人とは、日頃から良好な関係を築いておきましょう。
共有者の所在把握
共有持分は相続によって細分化されるため、共有者が会ったこともない遠縁の親戚であるケースも少なくありません。
共有者の所在がわかっていない場合、話し合いができず、不動産の管理に支障が出てしまいます。そのため、共有持分を売却するときは「共有者と連絡が取れるかどうか」が大切な要素です。
共有者の所在は、登記簿や住民票、戸籍の調査などで時間が必要な場合もあります。書類の取り寄せなど各種手続きに不安があるときは、弁護士に相談してみましょう。
共有持分を高く売るためにできること
共有持分を売却する場合、なにをすれば高く売れるかの工夫の仕方を見ていきましょう。
- 不動産の瑕疵や権利トラブルを解消しておく
- 土地を測量して隣接地との境界を確定しておく
- 他の共有者との関係を少しでも良くしておく
- 複数の業者に共有持分を査定してもらう
それぞれの工夫は、自分でできることもあれば、弁護士や土地家屋調査士など専門家の協力が必要な場合もあります。
すべてを完璧にしようとは思わず、可能な範囲で取り組んでいきましょう。
不動産の瑕疵や権利トラブルを解消しておく
不動産の瑕疵や権利トラブルを可能な限り解消しておけば、共有持分の売却価格も高くなると考えられます。
建物のひび割れやシロアリ被害といった物理的瑕疵なら、修理や駆除を依頼すれば解消できます。耐震補強工事をするなど、法的瑕疵についても解消できるものはあるでしょう。
ただし、不動産の瑕疵を解消するには一定の費用は必要になります。そのため、手元の資金や予想売却価格を踏まえて、損失とならないように判断しましょう。
権利トラブルは、話し合いで解決しない場合は調停や訴訟が必要になるかもしれません。適切な交渉や手続きを取れるよう、必要に応じて弁護士に相談してみましょう。
土地を測量して隣接地との境界を確定しておく
土地の測量をして、隣接地との境界を明確にしておくのも、共有持分を高額で売却するための有効な方法です。
買主としても、境界があいまいな土地や古い測量技術で境界が決められた土地より、最新の技術で正確に決められた境界の方が安心しやすいでしょう。
境界を確定する測量や登記申請は、土地家屋調査士に依頼します。
注意すべき点は、共有不動産の境界確定は「変更行為」になることです。つまり、共有者全員が立ち会って境界を決定するのが原則です。
ただし、共有者の数があまりにも多い場合は、代表者が1人で立ち会うケースもあります。
他の共有者との関係を少しでも良くしておく
共有持分を購入する人の目的として、その不動産を活用して利益を得ることが挙げられます。
前述したように不動産を活用するためには、他の共有者からの同意が必要です。他の共有者からも同様に持分を買い取った場合でも、無視できないコストがかかります。
共有者間でトラブルが起きていると、共有持分を買い取った人が不動産を活用するためのコストがさらにかかると予測されます。そのため、トラブルが起きている場合には売却価格が安くなってしまうのが一般的です。
共有持分を高値で売却するためにも、他の共有者との関係を良くしておくことも考えておきましょう。
複数の業者に共有持分を査定してもらう
共有持分を高値で売却するためにも、事前に複数の業者へ査定を依頼しておくのが得策です。
査定をしてもらうことで、共有持分の売却金額の目安を業者から提示してもらえます。査定の方法や基準は業者によって異なると考えられ、複数社に査定をしてもらうことで、最も高い査定額を提示してもらえた業者を見つけられる可能性があるのです。
共有持分を高く売りたい場合は、複数業者に査定を依頼して査定額を比較したうえで、依頼先を決めるのがよいでしょう。
共有持分を売却するなら専門の買取業者に依頼することも検討する
前述したように、共有持分だけでは需要が低くなりやすく、仲介ではなかなか買い手が現れないケースも少なくありません。そのため、共有持分の売却を検討している場合には、共有持分専門の買取業者に依頼することを検討してみてください。
共有持分を専門とする買取業者であれば、買い取った共有持分を活用するためのノウハウがあります。ほかの業者では扱いが難しい共有持分であっても、専門の買取業者であればスピーディーに買い取ってもらうことに期待できるのです。
また、共有持分専門の買取業者に依頼することには、下記のようなメリットもあります。
- 数日〜1か月程度で共有持分を現金化できる
- 共有者間でトラブルが起きていても対応してもらえるのが一般的
- 仲介手数料がかからない
ここからは、共有持分を専門の買取業者に売却するメリットについて、それぞれ解説していきます。
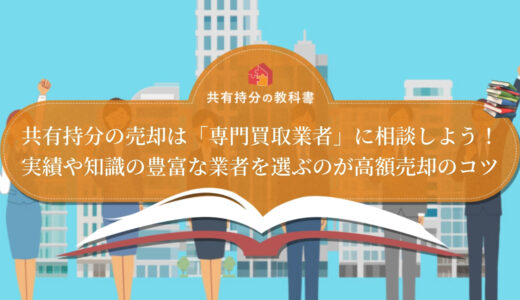 【共有持分の買取業者おすすめ27選!】共有名義不動産が高額買取業者の特徴と悪質業者の見極めポイント!
【共有持分の買取業者おすすめ27選!】共有名義不動産が高額買取業者の特徴と悪質業者の見極めポイント!
数日〜1か月程度で共有持分を現金化できる
共有持分を専門とする買取業者であれば、スピーディーな買取を実現できます。買取が完了するまでの期間は業者によって異なりますが、数日〜1か月程度であるのが一般的です。
仲介では通常の不動産であっても3か月〜6か月程度の期間はかかると言われていますが、買取であればその業者が直接買い取ってもらえるため、スピーディーな買取にも対応できるのです。
「共有持分をすぐに現金化したい」「できるだけ早く共有状態から抜け出したい」といった場合には、共有持分専門の買取業者に依頼することも検討してみてください。
共有者間でトラブルが起きていても対応してもらえるのが一般的
共有持分の売却を検討している人のなかには、「共有者間でトラブルが起きているけど売却できるのか」のように考えている人もいるかもしれません。
共有持分を専門とする買取業者であれば、弁護士をはじめとした士業と連携している業者もあり、そのような業者であればトラブルの解消にも対応しつつ買取を進めてもらえるのが一般的です。
すべての買取業者が士業と連携しているわけではないため、「共有者間でトラブルが起きている」という場合に共有持分の売却を検討しているのであれば、そのような専門業者を検討してみてください。
仲介手数料がかからない
不動産会社に仲介を依頼して物件売却をした場合、仲介手数料を支払うのが一般的です。仲介手数料の金額は業者によって異なりますが、数十万〜数百万円ほどかかることも珍しくありません。
一方、買取業者であれば仲介が不要になるため、仲介手数料は発生しません。共有持分の売却にかかる費用を抑えられるメリットもあるのです。
共有持分を高額で買い取る業者の見極め方
共有持分専門の買取業者のなかでも、できるだけ高く買い取ってもらえる業者に依頼したいのが当然の心理です。共有持分を高額で買い取ってくれる業者の見極め方として、次の要素があげられます。
- 共有持分の取り扱い実績が豊富
- 弁護士など法律の専門家と連携している
- 価格交渉ができる、契約を急かさない
専門買取業者を謳う以上、共有持分の取り扱い実績が豊富なのは最低条件です。ホームページに掲載されている実績はもちろん、会社の経営年数なども見てみましょう。
共有持分の取り扱いは権利関係の調整も頻繁に発生するため、法的な手続きが多くなりがちです。そのため、弁護士など法律の専門家と強いつながりをもつ業者は、買い取りから収益化までの時間を短縮でき、コストを押さえられます。
「価格交渉ができる」「契約を急かさない」といった買取業者は、経営に余裕のある買取業者といえます。売主の意向をないがしろにしない業者は、高額での買い取りが期待できるでしょう。
共有持分を売却するときの手順
共有持分を売却するときの具体的な手順は、次の5段階にわけられます。
- 買主を探す
- 必要書類の準備
- 売買契約の締結
- 法務局に持分移転登記を申請
- 譲渡所得税の納付
また、不動産の瑕疵・権利トラブルの解消や、境界確定のための測量などは時間がかかります。これらの手順より早めに取りかかり、並行して進めていくとよいでしょう。
1.買主を探す
まずは買主を探さなければなりません。すでに伝えているとおり、買取業者や他の共有者に売却するのがおすすめです。
とくに、買取業者に相談すれば最短数日での現金化も可能です。また、不動産を現状のまま買い取ってくれる場合が多いのも特徴でしょう。
瑕疵・権利トラブルの解消や、境界確定のための測量など、面倒なことはすべて買取業者に任せてしまうのも1つの方法といえます。
2.必要書類の準備
共有持分の売却で必要な書類は、次のとおりです。
- 登記済証または登記識別情報(持分取得時に法務局から発行されたもの)
- 固定資産税の納付書や証明書(市町村役場や都税事務所で発行可能)
- 住民票(発行3ヶ月以内のもの)
- 本人確認書類(免許証、パスポートなど)
- 印鑑証明証(発行3ヶ月以内のもの)
上記の他、実印も必要になります。
また、必要に合わせて建築確認通知書や検査済証、マンションの管理規約などが必要になります。
3.売買契約の締結
売買契約書を作成し、売主と買主が署名・捺印すれば契約締結です。
売買契約書には、次のような内容を盛り込みます。
- 売買物件の表示(登記簿にもとづく不動産の所在や持分割合など)
- 売買代金や手付金、支払期日
- 持分の引き渡し時期
- 費用の負担(契約書に貼付する印紙税などの負担)
- 瑕疵の修復
- 負担の消除(買主の所有権を阻害するような要因について)
- 引渡し前の物件滅失・毀損における対応
- 公租公課等の精算基準
- 契約違反による解除
- 反社会的勢力の排除
- ローン特約
- その他特約について
買取業者に依頼した場合、売買契約書も作成してくれます。個人間で売買するときは、司法書士に相談しながら作成するとよいでしょう。
4.法務局に持分移転登記を申請
売買契約が成立した後、法務局で持分移転登記をしなければなりません。
持分移転登記は自分でもできますが、司法書士に代行してもらうこともできます。
詳しくは、下記の記事を参考にしてください。
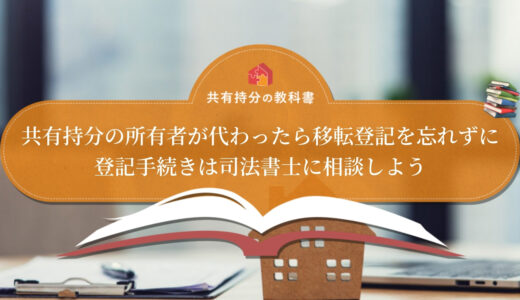 共有持分の移転登記が必要な状況を詳しく解説!登記費用や税金についても説明します
共有持分の移転登記が必要な状況を詳しく解説!登記費用や税金についても説明します
5.譲渡所得税の納付
登記が済んでも、それで終わりではありません。
共有持分の売却で得た利益に対して、譲渡所得税を納付する必要があります。
確定申告(不動産を売却した年の翌年2月16日から3月15日の期間)で、税務署へ売却利益を申告します。
税額の計算方法などは、下記の関連記事を参照してください。
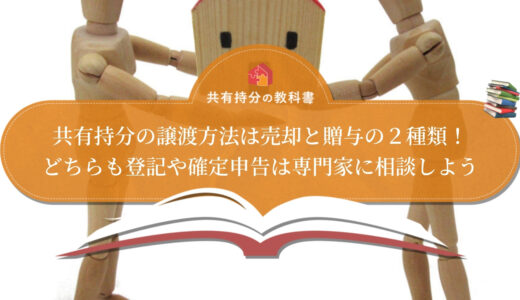 【共有持分の譲渡の仕方】やり方と方法別の税金制度についても解説!
【共有持分の譲渡の仕方】やり方と方法別の税金制度についても解説!
共有持分の売却は「市場価格の1/2」を基準にして高く売る工夫をしよう
共有持分は、取得しても不動産に対する多くの制限があるため、売却相場も低くなりがちです。
しかし、権利トラブルの解消など、売主の工夫次第で価値を上げることは可能です。
共有持分の売却価格は「不動産全体の価格×持分割合×1/2」を基準に考え、これより高い金額で買い取ってくれる買主を探しましょう。
高額買取の可能性がある売却先としては、共有持分専門の買取業者や、他の共有者がおすすめです。
共有持分についてよくある質問
共有持分とは、複数人が共有する不動産において「各共有者がどれくらいの所有権をもっているか」を指すものです。「持分1/2」というように、割合で表記します。
はい、売却できます。自分の共有持分であれば自分の意思のみで売却可能で、他共有者に確認を取る必要もありません。ただし、共有不動産全体を売却したいときは、全共有者の同意が必要です。
共有持分の取り扱いに不慣れな大手不動産会社より、共有持分を専門としている買取業者のほうが高額で買い取ってもらえるでしょう。また、離婚協議などでトラブルになっている場合は、弁護士と連携している専門買取業者に相談するのがおすすめです。→弁護士と連携した買取業者はこちら
共有持分の売買価格は、本来の価値から半額程度になるのが一般的です。ただし、売却相手や物件ごとの条件によっては高額になる場合もあり、すべての状況で共通する相場価格が決まっているわけではありません。
他の不動産会社が買取を断った物件でも「共有持分専門の買取業者」なら、売却できる可能性があるでしょう。共有不動産は権利関係が複雑なため、コストを気にする会社では取り扱いを断る場合があります。共有持分の専門買取業者なら共有持分の活用ノウハウがあるので、積極的に買い取ってもらえます。