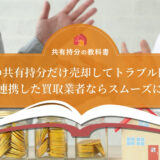持分移転登記とは、共有名義不動産における共有持分を、売買・相続・贈与・離婚の財産分与などに伴って他者へ移転させるための法的手続きです。
普段の生活で何度も行うものではないため、「費用がどのくらいかかるのか」「どんな税金が発生するのか」といった不安の声を、日々のご相談でもよくいただきます。
持分移転登記に必要となる費用は大きく分けて、司法書士に依頼する報酬、登録免許税、書類取得のための実費があります。加えて、ケースによっては、不動産取得税・相続税・贈与税・譲渡所得税などの税金が課税される場合もあるため、事前に整理しておくことが重要です。
以下に、代表的な費用や税金の目安をまとめました。
| 種類 | 費用の目安 |
|---|---|
| 司法書士に支払う報酬 | 1件あたり3〜5万円程度 |
| 登録免許税 | 固定資産税評価額の2%(軽減税率の適用あり) |
| 必要書類を揃えるための手数料 | 数千円程度 |
| 不動産取得税 | 固定資産税評価額の3%もしくは4% |
| 相続税 | 取得金額の10~55% |
| 譲渡所得税 | 譲渡所得の20%もしくは39% |
| 贈与税 | 取得金額の10〜55% |
注意点として、不動産取得税は相続や離婚による財産分与では課税されません。また、相続税や贈与税は基礎控除の範囲内であれば発生せず、譲渡所得税も売却益が出なければ課税されません。
ただし、「費用がかかりそうだから」と登記を先延ばしにすると、権利を主張できない、売却や融資が進められないなど、後々大きなトラブルに発展しかねません。
そのため、所有者が変わった時点で、できるだけ早めに持分移転登記を済ませることが肝心です。
本記事では、持分移転登記にかかる費用や税金の整理だけでなく、登記が必要となるケース、登記を怠った場合のリスク、さらには「自分で申請する場合の流れ」まで、実務経験に基づいて詳しく解説していきます。
共有持分の移転登記とは?
持分移転登記とは、共有名義不動産における共有持分を、他の人に移すための手続きです。ここでいう「共有持分」とは、複数人で所有している共有名義不動産のうち、それぞれがもつ所有権の割合を指します。
例えば、兄と弟がそれぞれ2分の1ずつの共有持分をもっている場合、弟の持分を兄に譲る際に持分移転登記を行います。この登記によって、登記簿上の名義が兄へと変更され、兄が不動産を単独で所有していることを正式に主張できるようになります。
なお、持分移転登記は専門的には「所有権移転登記」の一種として扱われます。違いを整理すると、所有権移転登記は不動産全体の所有者が丸ごと変わるときに行う登記であるのに対し、持分移転登記は共有状態の一部の持分だけを移すときに行う登記です。つまり、持分移転登記は所有権移転登記の部分的なケースにあたると理解すると分かりやすいでしょう。
共有持分の移転登記にかかる費用
持分移転登記を行う際には、登記手続きに必要な手数料(登録免許税)に加え、司法書士への報酬や必要書類の取得費用など発生します。主な内訳は次のとおりです。
- 司法書士に支払う報酬│1件あたり3〜5万円程度
- 登録免許税|固定資産税評価額の2%(軽減税率の適用あり)
- 必要書類を揃えるための手数料|数千円程度
司法書士に支払う報酬│1件あたり3〜5万円程度
持分移転登記は自分で申請することも可能ですが、登記書類の作成や法務局での手続きには専門知識が必要になるため、司法書士に依頼するのが一般的です。
司法書士に依頼して持分移転登記を行う場合、費用の目安は1件あたり3〜5万円程度です。なお、持分移転登記は、持分を譲渡する人ごとに1件扱いとなるため、人数に応じて登記手続きと費用が発生します。例えば、A・B・Cの3人の共有名義不動産で、B・Cの共有持分をAに移す場合は、2人分の登記手続きと費用が発生します。
ただし、司法書士事務所によって料金体系は異なります。1件あたり3万円程度で請け負う事務所もあれば、複数の持分移転登記をまとめて対応し、合計で10万円前後となるケースもあります。そのため、実際に依頼する際は事前に見積もりを出してもらい、内容を確認してから依頼すると安心です。
登録免許税|固定資産税評価額の2%(軽減税率の適用あり)
登録免許税とは、不動産の登記を行うときに法務局へ納める税金です。持分移転登記を行う際には、以下の計算式で求めます。
固定資産税評価額は、市区町村から毎年送付される「固定資産税課税明細書」で確認できます。登録免許税の税率は、売買・相続・贈与といった登記の理由によって異なります。
また、登記原因が売買の場合には軽減税率が適用されます。土地については、用途にかかわらず令和8年3月31日まで税率が2%から1.5%に軽減されます。一方、建物については居住用家屋の取得に限り、令和9年3月31日まで税率が2%から0.3%に軽減されます。
| 登記の理由 | 税率 |
|---|---|
| 売買 |
土地:2%(1.5%) ※令和8年3月31日までは「軽減税率1.5%」を適用 建物:2%(0.3%) ※令和9年3月31日までは住宅用家屋の取得に限り「軽減税率0.3%」を適用 |
| 相続 |
土地:0.4% 建物:0.4% |
| 贈与 |
土地:2% 建物:2% |
| 遺贈 |
土地:2% 建物:2% |
| 財産分与(離婚) |
土地:2% 建物:2% |
例えば、土地の評価額が2,000万円、建物の評価額が1,000万円の不動産のうち、2分の1の共有持分を売買で移転する場合(建物は居住用)の登録免許税は、以下のように計算できます。
建物:1,000万円 × 1/2(共有持分) × 0.3%(軽減税率)= 1万5,000円
合計:16万5,000円
必要書類を揃えるための手数料
持分移転登記を行う際には、本人確認や不動産の権利関係を証明するための書類をそろえる必要があります。主な書類と費用の目安は以下のとおりです
| 書類 | 費用の目安 | 取得場所 |
|---|---|---|
| 住民票 | 約300円 | 市区町村役場 |
| 印鑑登録証明書 | 約450円 | 市区町村役場(税務課など) |
| 登記事項証明書(不動産登記簿謄本) | 600円 | 法務局 |
| 委任状(司法書士に依頼する場合) | 自作したものを使用 | ― |
| 売買契約書・贈与契約書など | 契約時に当事者間で作成したものを使用 | ― |
住民票や印鑑登録証明書の費用は自治体によって異なります。また、持分移転登記を行う理由によって、必要になる書類も変わります。例えば、相続で持分を移転する場合は戸籍謄本や遺産分割協議書、離婚による財産分与の場合は離婚協議書や調停調書が必要になるケースがあります。
書類の種類や費用は状況によって変動するため、事前に自治体や法務局に確認しておくと安心です。なお、 司法書士に依頼して進める場合は、必要書類の確認から登記手続きまで一括して任せられます。
共有持分の移転登記にかかる可能性のある税金
持分移転登記を行う場合、以下のような税金が発生する可能性があります。
| 税金の種類 | 概要 | 税率 |
|---|---|---|
| 不動産取得税 | 不動産を購入・贈与・新築したときにかかる税金。取得した人が支払う。 | 固定資産税評価額の3%もしくは4% |
| 相続税 | 人が亡くなったときに、財産(不動産・預金など)を相続した人にかかる税金。基礎控除を超えた場合に課税される。 | 取得金額の10~55% |
| 譲渡所得税 | 不動産を売却して利益(譲渡所得)が出たときに発生する税金。売却した人が支払う。 | 譲渡所得の20%もしくは39% |
| 贈与税 | 個人から財産を贈与されたときに発生する税金。受け取った人が支払う。 | 取得金額の10〜55% |
ただし、不動産取得税は相続や離婚による財産分与では課税されず、相続税や贈与税は基礎控除があるため一定額以下であればかかりません。さらに、譲渡所得税も利益が出なければ発生しません。
このように、持分移転登記に関連して発生する税金は状況によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
不動産取得税|固定資産税評価額の3%もしくは4%
不動産取得税とは、不動産を購入したり、贈与を受けたり、新築したりしたときに課される税金です。一方で、相続や離婚に伴う財産分与では課税されません。共有名義不動産については、共有持分を新たに取得した人に対して課税されます。
持分移転登記により不動産を取得する場合の計算方法は次のとおりです。
税率は不動産の種類によって異なります。
| 不動産の種類 | 税率 |
|---|---|
| 土地 |
4%(3%) ※令和9年3月31日までは「軽減税率3%」を適用 |
| 建物(住宅) |
4%(3%) ※令和9年3月31日までは「軽減税率3%」を適用 |
| 建物(非住宅) | 4% |
例えば、土地の評価額が2,000万円、建物(住居用)の評価額が1,000万円の不動産の2分の1の共有持分を取得した場合は、以下のように計算します。
建物:1,000万円 × 1/2(共有持分) × 3%(軽減税率)= 15万円
合計:45万円
不動産取得税の特例措置
住宅用の土地や建物を取得する場合には、一定の条件を満たすことで、不動産取得税が減額されます。
| 不動産の種類 | 内容 | 条件 | 適用期限 |
|---|---|---|---|
| 新築住宅を取得する場合 | 評価額から1,200万円控除(長期優良住宅などは1,300万円) | 床面積50㎡以上240㎡以下(マンション等の貸家用は40㎡以上) | 令和9年(2027年)3月31日まで |
| 中古住宅を取得する場合 | 新築時と同額を控除(1,200万円または1,300万円) | 耐震基準を満たす、築年数が一定以下などの条件あり | 令和9年(2027年)3月31日まで |
| 住宅用地を取得する場合 |
(1)(2)のいずれか大きい額を土地の税額から軽減 (1)150万円 × 税率 (2)土地1㎡当たりの価格×住宅の床面積の2倍(1戸当たり200㎡を上限)×税率 |
一定期間内に住宅を建てるなどの要件あり | 令和8年(2026年)3月31日まで |
参照:総務省|不動産取得税
参照:国土交通省|不動産取得税に係る特例措置
例えば、 2024年の東京都の平均的な一戸建て住宅は、建物の評価額が1,174万円(床面積97.8㎡)、土地が142.6㎡でした。この場合、住宅用地の特例が適用され、不動産取得税は実質的に非課税となります。
相続税|取得金額の10~55%
共有持分を相続して持分移転登記を行う場合は、相続税にも配慮する必要があります。相続税とは、亡くなった人の財産を相続する際に、その財産の合計額に応じて課税される税金です。共有持分などの不動産の他、預貯金や有価証券などのすべての財産を合算して計算され、相続人が納付します。
ただし、 相続税には基礎控除が設けられており、一定額までは税金がかかりません。基礎控除の金額は以下の式で計算します。
例えば、法定相続人が2人の場合は、4,200万円が基礎控除となり、相続財産がこの範囲に収まるのであれば、相続税が発生しません。
相続財産が基礎控除を超えた場合、その超えた部分について以下の税率表に基づき相続税が課されます。
| 金額 | 税率 | 控除金額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | – |
| 1,000万円超3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
参照:国税庁|相続税の税率
なお、相続税の計算では「小規模宅地等の特例」が設けられており、被相続人(亡くなった人)が住んでいた土地などについては、最大で評価額の80%が減額されるケースがあります。例えば、居住用の土地(330㎡まで)は大幅に評価額が下がるため、課税対象額を小さくでき、結果的に相続税がかからないケースも多くあります。
参照:国税庁|相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
譲渡所得税|譲渡所得の20%もしくは39%
共有持分を売却して移転登記を行う場合、売却した人には「譲渡所得税」がかかる可能性があります。 譲渡所得税とは、不動産を売却して利益(譲渡所得)が出たときに、その利益に対して課される税金です。
計算式は次のとおりです。
譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率
税率は、不動産の所有期間によって異なります。
| 事故物件の所有期間 | 譲渡所得税の税率 |
|---|---|
| 長期譲渡所得(5年超) | 20%(復興所得税含む) |
| 短期譲渡所得(5年以下) | 39%(復興所得税含む) |
例えば、共有持分の売却価格が1,000万円、不動産の取得費が800万円、譲渡費用が50万円だった場合の譲渡所得税の計算は以下のとおりです。
譲渡所得税(所有期間が5年超):150万円 × 20% = 30万円
譲渡所得税(所有期間が5年以下):150万円 × 39% = 58万5,000円
ただし、売却したのがマイホームの場合は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が適用されるため、譲渡所得税が発生しません。また、以下のような譲渡の場合は、一定額を差し引ける特別控除が適用される可能性があります。
- 収用(公共事業による土地建物の買収など)で売却した場合:5,000万円控除
- マイホームの売却した場合:3,000万円控除
- 被相続人の空き家を売却した場合:3,000万円控除
- 土地区画整理事業のために土地を売却した場合:2,000万円控除
- 住宅地造成事業のために土地を売却した場合:1,500万円控除
- 2009年・2010年に取得した土地を売却した場合:1,000万円控除
- 農地の合理化のために売却した場合:800万円控除
- 低未利用土地を売却した場合:100万円控除
贈与税|10〜55%
共有持分の贈与によって持分移転登記を行う場合は、贈与税の対象となります。贈与税とは、個人から財産を贈与されたときに受け取った側が支払う税金です。共有持分を贈与した場合も、受け取った側に課税されます。
贈与税の計算方法は以下のとおりです。
なお、贈与には一般贈与と特例贈与の2種類があり、特例贈与のほうが税率が低めに設定されており、控除額も大きくなります。
- 一般贈与財産:親以外(例えば兄弟や配偶者の親など)からの贈与
- 特例贈与財産:直系尊属(父母や祖父母など)から18歳以上の子や孫への贈与
一般贈与財産と特例贈与財産の税率は以下のとおりです。
一般贈与財産の税率
| 一般贈与財産の課税価額 | 税率 | 控除金額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ー |
| 200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 600万円超1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
特例贈与財産の税率
| 特例贈与財産の課税価額 | 税率 | 控除金額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ー |
| 200万円超400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円超600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 600万円超1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,000万円超1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 3,000万円超4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
例えば、贈与された共有持分の評価額が800万円で、贈与者が父、受贈者が18歳以上の子である場合、この贈与は「特例贈与財産」として計算されます。
贈与税額(特例贈与):690万円 × 30%(税率) − 90万円(控除額) = 117万円
なお、婚姻期間が20年以上の夫婦の間でマイホームを贈与した場合には、「おしどり贈与」と呼ばれる制度が適用され、基礎控除110万円に加えて最高2,000万円までの控除を受けられます。条件に該当し、持分の評価額が控除内に収まれば、贈与税が発生しません。
参照:国税庁| 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
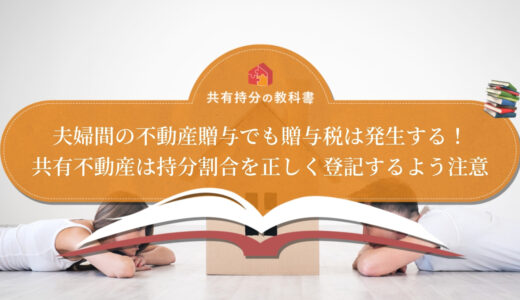 夫婦の共有不動産でも持分を変更すれば贈与税がかかる!贈与税を減らせる控除も解説します
夫婦の共有不動産でも持分を変更すれば贈与税がかかる!贈与税を減らせる控除も解説します
共有持分の移転登記が必要なケース
持分移転登記は、不動産の権利関係が変わるときに必ず行わなければならない手続きです。放置してしまうと法的に権利が移ったことが認められず、売却や利用の際に大きなトラブルにつながるおそれがあります。
具体的に登記が必要となるのは、次のようなケースです。
- 共有持分を売買した場合
- 共有持分を相続した場合
- 財産分与で共有持分を得た場合
- 共有持分を贈与された場合
- 共有持分を放棄した場合
- 共有物分割請求の判決が代償分割だった場合
共有持分を売買した場合
共有持分を売買した場合は、売主が持分を手放し、その権利が買主に移るため、必ず持分移転登記が必要です。通常は売買契約を締結した日に登記を行います。
共有持分の売買に該当するのは、共有者同士で持分を売買する場合や、買取業者など第三者に対して持分を売却する場合などです。
なお、共有者間での売買は親族同士で行われることも多いですが、その際に相場よりも極端に安い価格を設定すると、実質的に贈与とみなされて贈与税が課される可能性があります。近隣相場を参考にしながら、価格設定をしましょう。
また、親戚や知人同士だからといって手続きを省略してしまうケースも見られますが、持分移転登記を行わなければ、法的に権利の移転は認められません。売却後のトラブルを防ぐためにも、共有持分を売買する際は必ず移転登記を行いましょう。
共有持分を相続した場合
共有持分を相続した場合も、被相続人(亡くなった人)から相続人へ権利を移すために、持分移転登記を行う必要があります。
2024年4月1日からは法律が改正され、相続によって不動産を取得した場合には、「相続により所有権を取得したことを知った日」または「遺産分割が成立した日」から3年以内に登記を行うことが義務化されました。相続人が多数で戸籍の収集に時間がかかるなど、正当な理由なく登記を怠った場合は、10万円以下の過料が科されるおそれがあります。
なお、2024年4月1日より前に発生した相続についても、改正法に基づき3年間の猶予期間が設けられており、その間に登記を行う必要があります。
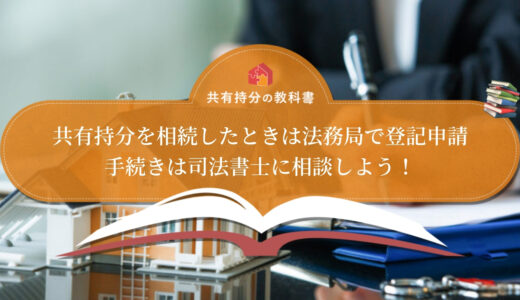 共有持分相続時は持分全部移転登記を!手順や費用も詳しく解説します
共有持分相続時は持分全部移転登記を!手順や費用も詳しく解説します
財産分与で共有持分を得た場合
離婚の際には、夫婦で築いた財産を原則として半分ずつ分け合います。財産のなかに共有名義不動産が含まれている場合には、どちらか一方の単独名義にするために持分移転登記を行う必要があります。
例えば、夫婦が登記上それぞれ2分の1ずつの持分を持っている自宅を離婚後に妻が引き継ぐ場合、夫の持分を妻に移す登記手続きを行わなければなりません。
なお、離婚後も共有名義の状態を続けてしまうと、将来的に売却や管理の際に、共有者である元配偶者の同意が必要になり、トラブルにつながるおそれがあります。そのため、財産分与で不動産を分ける際には、持分移転登記を行い、単独名義にしておくことをおすすめします。
共有持分を贈与された場合
共有持分を贈与された場合も、贈与者から受け取った人に権利を移すため、持分移転登記を行う必要があります。
例えば、親が子どもに自宅の持分の一部を生前贈与するケースや、夫が妻に自宅の持分を贈与するケースなどが該当します。
贈与の場合は、贈与税が課される可能性があります。先述した「贈与税|10〜55%」で、贈与税の額や特例の適用になるかを確認のうえ、贈与を実際に受けるか判断すると良いでしょう。
共有持分を放棄した場合
自分の持っている共有持分を放棄すると、その持分は他の共有者に移ります。放棄は「持分を手放す」という意思を示すだけでは法的な効力はなく、正式に効力を持たせるためには持分移転登記を行う必要があります。
例えば、兄弟で不動産を共有している場合に、一方が「もう管理に関わりたくない」として持分を放棄するようなケースが該当します。この場合、兄弟で協力して持分移転登記を行うことで、放棄された持分が残った共有者に移ります。
なお、共有持分の放棄は「贈与」とみなされることもあります。その場合、受け取った共有者に贈与税が課される可能性があります。税務上の扱いを確認したうえで、司法書士や税理士に相談しながら進めると安心です。
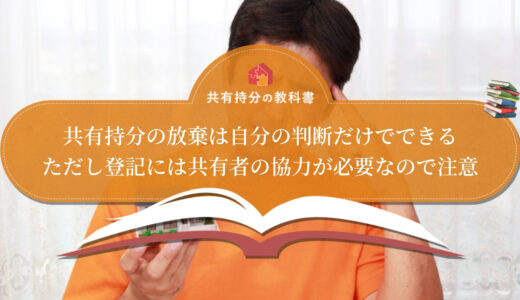 共有持分は放棄できる!放棄の手順や放棄後の登記も詳しく解説します
共有持分は放棄できる!放棄の手順や放棄後の登記も詳しく解説します
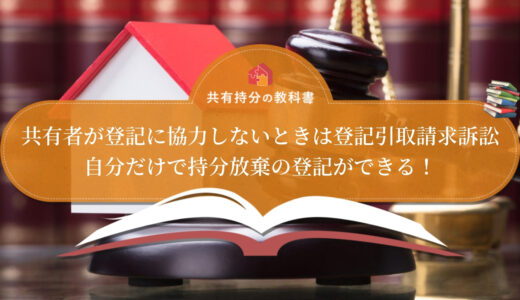 持分放棄後の未登記は登記引取請求訴訟で解決!概要や費用について詳しく解説します
持分放棄後の未登記は登記引取請求訴訟で解決!概要や費用について詳しく解説します
共有物分割請求の判決が代償分割だった場合
共有物分割請求とは、共有者の1人が「このまま共有名義では使いにくいので、共有状態を解消したい」と求める手続きです。調停もしくは訴訟によって解決します。
訴訟となった場合、裁判所の判決で共有物の分割方法が決まります。
- 現物分割:土地や建物を物理的に分けて所有する方法
- 代償分割:1人が不動産を取得し、代わりに他の共有者へお金を払う方法
- 換価分割:不動産を売却し、その代金を共有者で分ける方法
このうち「代償分割」が命じられた場合は、特定の共有者が他の共有者の持分をすべて買い取り、その不動産を単独で所有することになります。例えば、兄弟3人で実家を共有していたが、長男が代償金を支払い、実家を単独で引き継ぐケースなどが該当します。
代償分割では持分の所有者が変わるため、法務局で共有持分移転登記を行わなければなりません。
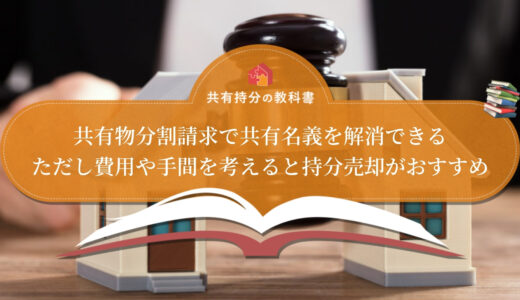 共有物分割請求とは?共有物の分割方法や訴訟の手順・費用を詳しく解説
共有物分割請求とは?共有物の分割方法や訴訟の手順・費用を詳しく解説
共有持分の移転登記をしないと起こり得る主なリスク
持分移転登記を怠ると、実際には権利が移っていても登記簿上に反映されないため、第三者から見れば「まだ前の持ち主のもの」と扱われてしまいます。その結果、思わぬトラブルや不利益を招く可能性があります。
不動産の現場では、以下のようなリスク・トラブルがよくみられます。
- 自分の不動産であると主張できない
- 前の登記名義人が勝手に売却・担保設定してしまう
- 売却・担保設定・融資などの手続きができない
- 相続人が増え、相続時にトラブルの火種になる
- 後から登記しようとしても、関係者と連絡が取れず手続きが困難になる
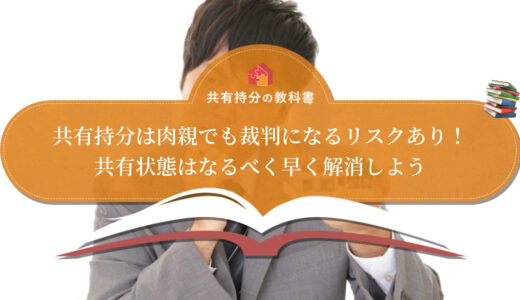 共有持分のリスクが生じるケースと具体的な対処法を丁寧に解説!
共有持分のリスクが生じるケースと具体的な対処法を丁寧に解説!
自分の不動産であると主張できない
持分移転登記を行わないと、登記簿の名義は前の所有者のままです。売買や相続、贈与、離婚による財産分与などで実際には権利が移っていても、登記をしていなければ第三者に対して「自分のものだ」と主張できません。
不動産の現場でも、実際に「すでに代金を支払って引き渡しを受けているのに、登記がされていないために自分の所有権を認めてもらえない」といったトラブルは少なくありません。特に売却や担保設定などの手続きを進めようとした際に、登記簿上の名義人と実際の所有者が異なっていることで、大きな問題に発展するケースがあります。
そのため、不動産の権利を確実に守るためには、契約が成立した段階で速やかに持分移転登記を済ませておくことが重要です。
前の登記名義人が勝手に売却・担保設定してしまう
持分移転登記を行わないままにしておくと、登記簿上では前の所有者に権利がある状態が続きます。その結果、前の名義人がその権利を利用して、第三者に持分を売却したり、担保に差し入れてお金を借りたりするリスクがあります。
実際に「売買契約で代金を支払ったのに、登記をしていなかったために、前の所有者が別の人に売却してしまった」といったトラブルもあります。こうした場合、登記簿上の名義を持っている人が優先されるため、本来の買主が権利を主張できず、大きな損失につながります。
共有持分を取得した際には、「後でやろう」と放置せず、速やかに持分移転登記を行うことが重要です。特に、親族間のやり取りや小規模な売買では軽視されがちですが、実務上は必ず押さえておくべき重要な手続きといえます。
売却・担保設定・融資などの手続きができない
不動産の所有者として権利を主張するためには、登記簿上の名義と実際の所有者が一致していなければなりません。持分移転登記を行っていない場合、実際には共有持分を取得していても、登記上は前の所有者の名義のままです。そのため、不動産を売却することも、不動産を担保にして融資を受けることもできません。
実務でも「未登記のまま放置されている物件」は少なくありません。売却や融資を受けようとして初めて登記簿を確認した際に、「まだ前の所有者の名義のままだった」と気づくケースもあります。
こうしたトラブルを避けるためには、権利を取得した時点で速やかに登記を済ませましょう。特に、将来的に融資や売却を検討している場合は、登記が済んでいなければ手続きが進まないため、早めに司法書士や不動産会社に相談しておくことをおすすめします。
相続人が増え、相続時にトラブルの火種になる
共有持分を持つ人が亡くなった場合、その持分は法定相続人に引き継がれます。相続人が複数いれば、それだけ共有者も増えることになります。もし相続が発生しても持分移転登記を行わないまま放置すると、登記簿上では亡くなった人が所有者のままとなり、次の相続が発生したときに誰がどの割合を引き継いだのか分からなくなってしまいます。
不動産の現場でも、調査を進めると「相続を繰り返すうちに共有者が10人以上に増えていた」というケースは珍しくありません。このように権利関係が複雑になるほど、売却や活用の話を進めようとしても全員の同意を取るのが難しくなり、トラブルに発展しやすくなります。
将来の相続人に余計な負担をかけないためにも、相続が発生したら速やかに持分移転登記を行うことが大切です。また、可能であれば相続の段階で共有名義は避け、単独名義にまとめるか、不動産を売却して代金を分け合うといった整理をしておくことをおすすめします。
後から登記しようとしても、関係者と連絡が取れず手続きが困難になる
持分移転登記は、持分を手放す側(登記義務者)と取得する側(登記権利者)が共同で行う必要があります。そのため、登記を後回しにすると、いざ手続きを進めようとしたときに当事者と連絡が取れなくなり、登記が進められないリスクがあります。
不動産の現場でも「売買契約は済ませていたが、相手が転居して所在不明になった」といったケースは実際にあります。持分移転登記が進まないと、売却や担保設定ができず、物件の活用が大幅に制限されてしまいます。
なお、関係者とどうしても連絡が取れない場合は、家庭裁判所に「登記手続請求」を申し立てるといった法的手続きを検討することも可能です。登記手続請求とは、登記義務者が協力してくれない、あるいは所在不明などで連絡が取れない場合に、裁判所の判断で登記を実現できるようにする手続きです。
ただし、裁判所を通した手続きは費用がかかり、解決まで長期化することもあります。そのため、基本的には権利を取得した時点で、持分移転登記を済ませておくことが、リスク回避につながります。
共有持分の移転登記を自分で行う流れ
持分移転登記は司法書士に依頼するのが一般的ですが、必要な書類や手続きを理解していれば自分で行うことも可能です。費用を抑えたい場合や、共有者が2人で手続きが比較的簡単な場合は、自分で手続きを進めるのも良いでしょう。
自分で持分移転登記を行う際は、以下のような流れで進めます。
- 必要書類を準備する
- 登録免許税を計算する
- 必要書類を法務局へ提出する
- 「登記識別情報通知書」を受け取る
必要書類を準備する
持分移転登記を自分で行う場合には、登記の原因(売買・相続・贈与など)に応じて複数の書類を揃える必要があります。不備があると受理されないため、事前に準備しておきましょう。
以下は代表的な必要書類と取得先・費用の目安です。
| 書類 | 概要 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 登記申請書 | 登記の内容を記載する書類。法務局の窓口やサイトからダウンロードして自作する。 | 無料 |
| 住民票 | 登記名義人の住所を証明する書類。市区町村役場で取得する。 | 約300円 |
| 印鑑証明書 | 登記義務者(持分を移す側)の本人確認に使用。市区町村役場で取得する。 | 約450円 |
| 登記識別情報通知(権利証) | 過去に登記した際に法務局から交付された12桁の英数字。所有者が保管している書類。 | 無料 |
| 登記原因証明情報 | 共有持分が移転する理由を証明する書類。売買契約書、遺言書、遺産分割協議書、財産分与契約書などが該当する。 | ― |
| 固定資産評価証明書 | 登録免許税を計算するために必要。市区町村役場で取得する。 | 約300円 |
| 戸籍謄本一式(相続の場合) | 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本。相続関係を証明するために使用。市区町村役場で取得する。 | 1通450円程度 |
※費用は自治体によって異なる場合があります。
特に相続による移転登記の場合、戸籍を揃えるのに時間と手間がかかることが多いため、早めに準備しておくことが重要です。不安な場合や書類収集が難しい場合は、司法書士に依頼するのがおすすめです。
登録免許税を計算する
持分移転登記を行う際には、登記を受け付けてもらうための手数料として「登録免許税」を法務局に納めます。事前に、登録免許税を計算しておくと、申請時に慌てません。
登録免許税の計算方法は以下のとおりです。
固定資産税評価額は、市区町村から毎年送られる固定資産税課税明細書や、役所で取得できる固定資産評価証明書で確認できます。登記の原因によって計算が複雑になることもあるため、不安な場合は司法書士に確認してもらうと安心です。
なお、登録免許税は軽減税率が設けられています。詳しくは、「登録免許税|固定資産税評価額の2%(軽減税率の適用あり)」を参考にしてください。
必要書類を法務局へ提出する
必要書類を揃えたら、管轄の法務局に提出して登記申請を行います。申請時には、登記申請書に収入印紙を貼り付けて、登録免許税を納付します。収入印紙は、法務局の窓口や郵便局で購入可能です。
法務局の窓口だけでなく、「登記・供託オンライン申請システム」よりオンライン申請も可能です。オンライン申請の場合は、電子納付で登録免許税を納めます。
「登記識別情報通知書」を受け取る
登記申請が法務局で受理されると、手続き完了後に「登記識別情報通知書」が交付されます。これは従来の「権利証」にあたるもので、共有持分の所有者であることを証明する大切な書類です。
登記完了までの期間は、書面申請の場合でおおむね1〜2週間、郵送での受け取りを希望すると2〜3週間程度かかります。オンライン申請を利用した場合は、1週間前後で通知を受け取れることもあります。
登記識別情報通知書は、将来、共有持分を売却したり、担保に入れたりする際に必要になるため、紛失しないよう厳重に保管しておきましょう。
まとめ
相続や売買、贈与、離婚による財産分与などで共有持分の所有者が変わる場合には、必ず持分移転登記を行う必要があります。登記にかかる費用は、登録免許税や司法書士に依頼する場合の報酬、住民票や固定資産評価証明書などの取得費用です。
さらに、登記の理由によっては不動産取得税や相続税、譲渡所得税、贈与税といった税金が発生することもあります。費用や手間はかかりますが、持分移転登記をしないままにしておくと、不動産の権利を法的に主張できず、売却や融資ができない、相続時にトラブルが起きるなど大きなリスクにつながります。所有者が変わった場合は、できるだけ早めに登記を済ませ、将来のトラブルを未然に防ぐことが大切です。